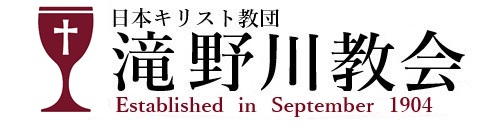2025年9月7日 主日礼拝説教「霊の家に造り上げられる」 東野尚志牧師
イザヤ書 第28章16~18節
ペトロの手紙一 第2章4~8節
今から何年か前のことになります。東京の日本橋から小さな船に乗って、神田川や隅田川をめぐる1時間半ほどのクルーズに参加したことがあります。私たち夫婦は、そんな洒落た観光コースがあることなど全く知りませんでした。実は、聖学院を隠退された小倉義明先生が、すべて計画して、私たち夫婦をこの魅力的なクルーズに誘い出してくださったのです。普段見慣れた地上の風景とは違って、船から見る景色は斬新でした。
特に印象深かったのは、いろんなところに、昔の江戸城の石垣が残っているということでした。しかも、場所によって、石の組み方に違いがあるのが、実に興味深いことでした。自然の石の形を生かしながら、上手く組み合わされた石垣があるかと思えば、石と石の間を、小さな石で埋めている石垣もありました。きっちり削って組み合わされた石垣もありました。恐らく、造られた年代が違うのだと思われます。いずれにしても、簡単に崩れてしまうことのないように、石と石がしっかり組み合わされて、土台となる石垣が築かれていたのです。
日本では、石を土台にすることはあっても、石を積み重ねるようにして家を建てることはあまりありません。石よりも木の方が身近にあったからだと思います。土台がしっかりすれば、あとは豊富な木材を用いて、容易に骨組みを造り、板で壁や天井をはることができました。けれども、木材が少なく、代わりに石や石材が豊富にとれたパレスチナの地方では、建築資材として石が用いられました。大きな石を用いて、祭壇を造ったり、契約のしるしとして石碑や石柱を建てたりしました。モーセがシナイ山で神から授かった掟である十戒は、二枚の石の板に刻まれたのです。そして、大事な建物を建てるとき、神の家である神殿を建てる際には、切り出した石を積み重ねて、しっかりと建て上げていきました。
聖書の舞台となったパレスチナの地方では、石や石材が便利に用いられました。だからこそ、聖書の中では、しばしば、身近にあった石がたとえに用いられることになります。先ほど朗読したペトロの手紙の箇所を日本語で読んでも、石に関わる言葉がいくつか出て来ました。「生ける石」、「選ばれた尊い隅の親石」、「捨てた石」、「つまずきの石」、そして、「妨げの岩」。なかでも、私たち自身が「生ける石」として、「霊の家に造り上げられる」という5節の言葉は心に残ります。「あなたがた自身も生ける石として、霊の家に造り上げられるようにしなさい」と告げるのです。たくさんの石が組み合わされて、堅固な石垣が造られるように、私たち一人ひとりが、「生ける石」、つまり生きた石として組み合わされて、「霊の家」に造り上げられて行くというのです。
「霊の家」、それは、教会を指しています。教会というのは、教会の建物のことではない、ということが、しばしば言われます。教会というと、すぐ目に見える教会堂のことを思い浮かべてしまうことへの戒めとして言われます。確かに、教会堂がなくても教会はあるのです。宗教改革者は言いました。御言葉の説教が純粋に語られ、聖礼典がキリストの制定に従ってふさわしく行われているところに教会がある。たとえ教会堂はなくても、御言葉の説教と聖礼典を中核として集められた群れこそが教会なのです。そのことを良く弁えた上で、ペトロが教会を建物にたとえたことの意味を味わいたいと思います。それは、目に見える建物ではありません。私たち自身が生きた石として用いられ、組み合わされて建て上げられていく、霊的な家だというのです。
石垣は、いろんな形の石が組み合わされ、積み上げられていきます。同じように、教会という霊的な家を造り上げる石もまた、いろんな形をしています。形が揃っているわけではありません。とがったところ、へこんだところ、歪んだところ、そのままでは、落ち着きの悪い石です。色も違えば、大小さまざまな石があります。私たち自身においては、見栄えの良くない、道端に転がっている石ころと変わりない存在なのです。あるいは、この石というたとえは、私たちの頑なな心、閉ざされた心を表わしていると言えるかもしれません。けれども、そのような何の値打ちもない、欠けて薄汚れた道端の石ころを拾い上げ、手に取ってくださった方があります。石ころのような私たちを、拾い上げて、教会という霊的な家に組み込んでくださった方があるのです。この霊の家を造り上げるために無くてはならない、かけがえのない石として、私たちを選んでくださった方、それが主イエス・キリストです。主イエス・キリストを信じて、洗礼を受けることによって、私たちは生きた石として、教会の中に組み込まれるのです。
さまざまな個性を持った、バラバラであった石が組み合わされ、積み上げられて、ひとつの家としての教会に造り上げられるためには、まず何よりも、土台がしっかり据えられていなければなりません。土台がいい加減であれば、地震が来れば崩れてしまいます。洪水に遭えば押し流されてしまいます。そうならないように、私たちが生きた石として用いられるため、自らを土台として献げてくださった方がおられるのです。ペトロは言います。「主のもとに来なさい。主は、人々からは捨てられましたが、神によって選ばれた、尊い、生ける石です」(2章4節)。ここで「主」と言われているのは、主イエス・キリストのことです。私たちが「生ける石」と呼ばれるのに先立って、主イエスご自身が「生ける石」と呼ばれています。主イエスが、まず「生ける石」として、ご自身を献げてくださり、教会という霊の家の確かな土台になってくださったというのです。
ただし、ここには、主イエスについて、二つの相反する見方が描かれています。一つは、「人々からは捨てられた」石だということです。もう一つは、「神によって選ばれた、尊い、生ける石」だということ。この二つの相反する見方を説明するために、旧約聖書から二つの言葉が引用されています。最初は6節「聖書にこう書いてあるからです。『見よ、私は選ばれた尊い隅の親石を シオンに置く。これを信じる者は、決して恥を受けることはない』」。先ほど、ペトロの手紙と合わせて朗読したイザヤ書第28章の言葉からの引用です。そして、二つ目は7節です。「それゆえ、この石は、信じているあなたがたには掛けがえのないものですが、信じない者にとっては、『家を建てる者の捨てた石 これが隅の親石となった』」といわれます。こちらは、先ほど交読した詩編118編からの引用となります。双方の引用箇所に共通するのは「隅の親石」という言葉です。
「隅の親石(すみのおやいし)」というのは、とても面白い言葉だと思います。通常は、石造りの建築をする際、隅に置かれた押さえの石を意味すると考えられます。現代建築においては、「礎石」と呼ばれるものにあたるのでしょう。建物全体を支える土台となる大事な石です。以前の口語訳聖書では「隅のかしら石」と訳されていました。また新共同訳聖書の中では「かなめ石」と訳されたところもあります。この言葉はまた、丸いアーチ状の構造物を造る際、あるいは、巨大なドーム型の屋根を造る際、両側から、あるいは四方から石を積み上げていって、最後にはめ込まれるてっぺんの石を指す言葉としても用いられます。その場合は、まさに「かしら石」「かなめ石」という言い方が分かりやすいかもしれません。最後にこのかしらの石がはめ込まれることで、建物全体ががっちりと組み合わされて安定するようになります。建物全体のかしらに置かれ、かなめの石となるわけです。
一方では、神ご自身が、主イエス・キリストをお選びになり、尊い隅の親石として、シオン、すなわち、エルサレムに据えられたと言います。この親石である主イエスを信じる者は、恥を受けることはない。私たちの信仰を支える確かな土台であり、この世の嵐に翻弄される私たちをがっちりと安定させる信仰のかなめとなってくださいます。しかし、もう一方で、主イエス・キリストは、人々からは捨てられた石、家を建てる専門家によって、役に立たない石、邪魔な石として捨てられた石であったのが、実際に家が建ってみると、その捨てられた石が隅の親石になっていた、というのです。人々から見捨てられ、十字架につけられた主イエスが土台になって、霊的な家としての教会が造り上げられるというのは、そのような不思議な神の御業であったというのです。人間の思いを超えて、主イエスに敵対し、主イエスを亡き者にしようとした人々の悪巧みをさえ用いて、神は救いの御業を成し遂げてくださいました。交読した詩編118編には「これは主の業 私たちの目には驚くべきこと」と歌われていました。(詩編118編23節)。
そこには、主の御業を信じようとしない者たちに対する警告も含まれています。ペトロの言葉を7節から8節まで続けて読んでみます。「それゆえ、この石は、信じているあなたがたには掛けがえのないものですが、信じない者にとっては、『家を建てる者の捨てた石 これが隅の親石となった』のであり、また、『つまずきの石 妨げの岩』なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからであって、そうなるように定められていたのです」。私たちが、十字架につけられ殺された主イエスを、私の救い主として信じ受け入れるのは、決して当たり前のことではありません。私たちが自分の知恵と力で見いだせるものではありません。私たちの理解を超えています。奥義というほかありません。主の業は、私たちの目には驚くべきことなのです。それを、信じ受け入れることができるのは、聖霊なる神が、私たちの石のような硬い心に働きかけてくださり、死んだ石に命を吹き込んで、生きた石として用いてくださるからです。聖霊なる神が、私たちを、霊の家に造り上げようとしてくださるのです。
それならば、主イエスの十字架による救いを信じ、生きた石として、霊の家へと造り上げられることで、私たちは何をするのでしょうか。ペトロは、5節の後半で語ります。5節の始めから続けて読んでみます。「あなたがた自身も生ける石として、霊の家に造り上げられるようにしなさい。聖なる祭司となって、神に喜んで受け入れられる霊のいけにえを、イエス・キリストを通して献げるためです」。私たちが「生ける石」、生きた石として、霊の家に造り上げられるとき、私たちは「聖なる祭司」として立てられるというのです。イエス・キリストを信じる私たちは、神さまにお仕えする「聖なる祭司」であるというのです。
旧約の時代において、祭司の大事な働きは、動物の犠牲を繰り返し献げることでした。それを罪の償いとすることで、人は罪赦されて神の前に出られるようになりました。しかし、私たちは、もはや、動物の犠牲を献げる必要はありません。主イエス・キリストが十字架の上でご自身の血を注ぎ、その命を犠牲として永遠の贖いを成し遂げてくださったからです。だからこそ、ペトロは、霊的ないけにえを、イエス・キリストを通して献げるようにと記すのです。イエス・キリストこそは、ただ一度ご自身をいけにえとして献げて、永遠の贖いを成し遂げてくださったまことの大祭司です。私たちの罪を取り除き、神との和解の道を開いてくださいました。復活して天に昇られた後も、今に至るまで、父なる神の右に座して、私たちのために執り成してくださっています。そのイエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊的ないけにえを献げるようにと、ペトロは言うのです。
「神に喜んで受け入れられる霊のいけにえ」とは何でしょうか。ヘブライ人への手紙は、その第13章15節と16節で、記しています。「だから、イエスを通して、賛美のいけにえ、すなわち御名をたたえる唇の実を、絶えず神に献げましょう。善い行いと施しとを忘れてはなりません。このようないけにえこそ、神は喜ばれるのです」。私たちは礼拝において、神さまの御名をほめたたえる賛美の歌を歌います。神を礼拝することによって、私たち自身を神に喜ばれる霊のいけにえとして献げます。そして、私たちも永遠の大祭司である主にならって、執り成しの業を担うのです。
私たちが、主の日毎に共に集い、神の御前に立って礼拝を献げるのは、私たち自身のためだけではありません。この礼拝堂の中にはいない家族や信仰の仲間たちに代わって、その祈りと信仰を執り成しながら礼拝を献げます。さらには、神に愛され、神にかたどって造られ、神の命の息を吹き入れられているにもかかわらず、今もなお神の御前から失われてしまったままであるすべての魂を代表するようにして、やがてすべての造られたものが主の前に膝をかがめる日が来ることを信じ、すべての被造物に先立って、執り成し祈り、礼拝をしているのです。私たちは、終わりの日の栄光に満ちた礼拝を先取りするようにして、喜び祝うのです。
ペトロは言います。「イエス・キリストを通して」。ここにすべての鍵があり、礼拝の根拠があります。執り成しの源があります。すべては、イエス・キリストによって成し遂げられ、私たちに恵みとして与えられているのです。父なる神さまが、私たちの献げる礼拝を喜んで受け入れてくださることを信じ、主の御手にすべてをお委ねしたいと思います。