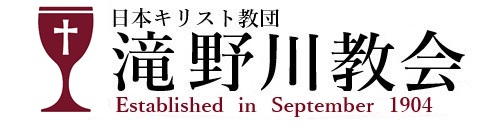2025年9月21日 主日礼拝説教「何のために生まれ、何をして生きるのか」 東野尚志牧師
イザヤ書 第61章1~4節
ペトロの手紙一 第2章9~10節
「あなたは誰ですか」。そんなふうに問われたら、皆さんは何とお答えになるでしょうか。もちろん、問われた場所や状況によって、答えは違ってくるかも知れません。けれども、「あなたは誰ですか」と問われたら、恐らくほとんどの人が、自分の名前を名乗るのではないかと思います。「はい、私は東野尚志です。滝野川教会の牧師をしています」。そんなふうに答えるのが自然であろうと思います。
今からちょうど30年前のことになります。アメリカ合衆国長老教会が、聖書と教団の信仰告白書に基づいて、新しいカテキズム、信仰問答書の作成を決議しました。3年ほどの取り組みを経て、子ども向けと青年以上に向けてと、2種類のカテキズムが作られました。子ども向けのカテキズムは、10歳位からの子どもたちが最初に学ぶカテキズムという位置づけで、「わたしたちは神さまのもの―はじめてのカテキズム」という題がつけられました。青年以上を対象とするカテキズムは、実用的に「学習用カテキズム」というのです。子ども向けに作られた「はじめてのカテキズム」の最初に掲げられたのが、「あなたは誰ですか」という問いでした。
子ども向けのカテキズム、信仰問答書という枠組みにおいて、「あなたは誰ですか」という問いが立てられたとき、皆さんは、どんな答えを期待されるでしょうか。実際のやり取りをご紹介します。問い1「あなたは誰ですか」。答え「わたしは神さまの子どもです」。信仰問答の問いに対する答えというのは、決して、信仰者の実感に基づいて生まれた言葉ではありません。私たちが、自分自身で、ああ、私は神さまの子どもだ、と実感して、胸を張って答えるわけではないのです。そうではなくて、「あなたは誰ですか」「わたしは神さまの子どもです」という問いと答えの言葉を通して、自分自身が本当は何者であるのか、何者とされているのか、ということを学ぶことになります。知らなかった真実に触れるのです。自分から自発的に、「わたしは神さまの子どもです」などとは到底口にできない者であっても、信仰の応答としての言葉をなぞるようにして読み上げながら、正しい信仰告白の言葉を身につけて行きます。神の子とされている、その驚くべき恵みを味わい知るのです。
カテキズムは続けて、問いと答えを重ねていきます。問い2「神さまの子どもであるとはどういうことですか」。答え「わたしが、わたしを愛してくださる神さまのものだということです」。問い3「あなたは何によって神さまの子どもになりましたか」。答え「恵みという『神さまの自由な愛の贈り物』によってです。わたしはそれにふさわしくありませんし、自分の努力で勝ち取ることができません」。問い4「神さまに愛されるためには『良い子』にならないといけないのですか」。答え「いいえ、わたしがどんな子であっても、神さまは愛してくださっています」。問い5「この愛の贈り物に対してどのように神さまに感謝するのですか」。答え「わたしが心から神さまを愛し、神さまに信頼することを約束することによってです」。まだまだ続きます。子どもにも分かる言葉で、恵みによって神さまのものとされたこと、そして、この恵みに応えて生きる道が、はっきりと示されているのです。
ペトロの手紙一もまた、同じような語り口をもっていると言って良いと思います。この手紙は、洗礼を受けて間もない信徒たちに対して、厳しい迫害にさらされる中で信仰が萎えてしまわないように、教会の信仰を確かなものとするために書かれたと言われます。その意味では、旧約聖書の預言と主イエスによる救いの出来事に基づいて書かれた「はじめてのカテキズム」と呼んでもよいのではないかと思います。洗礼を受けて、教会の仲間に加えられた信徒たちに向かって、信仰者の群れである教会は、どのようなものなのか、何者とされているのか、教会のアイデンティティをくっきり描き出します。そして、神のものとされた教会は何をするのか、ということを示そうとするのです。
第2章9節で告げられます。「しかし、あなたがたは、選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、あなたがたを闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある顕現を、あなたがたが広く伝えるためです」。教会とは何であるかを記している四つの言葉については、すでに、夏期修養会に向けての学びの中で、何度も触れてきました。エジプトにおいて奴隷とされていたイスラエルは、そこから救い出されて、荒れ野へと導かれる中、シナイ半島の中央、シナイ山のふもとで神と契約を結んで、神の民となりました。そこで主なる神が告げられたのは、こういう言葉でした。「私がエジプト人にしたことと、あなたがたを鷲の翼の上に乗せ、私のもとに連れて来たことをあなたがたは見た。それゆえ、今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたがたはあらゆる民にまさって私の宝となる。全地は私のものだからである。そしてあなたがたは、私にとって祭司の王国、聖なる国民となる」(出エジプト19章4~6節)。
イスラエルは、神と契約を結び、神の言葉に従い、掟の言葉を守ることで神の宝の民とされました。そこで、イスラエルに告げられた言葉、神に選ばれ神のものとなった「宝の民」、「祭司の王国」、「聖なる国民」。これらの言葉を基にしながら、新しい神の民である教会に対しても、「選ばれた民」、「王の祭司」、「聖なる国民」、「神のものとなった民」と告げられるのです。この四つの言葉で、新しい神の民とされた、私たち教会のアイデンティティを描き出そうとしているのです。
まず初めに告げられるのは、教会とは神によって「選ばれた民」であるということです。私たちが、神の民となったのは、私たちの願いや決断によるのではありません。神さまの大いなる救いのご計画の中で、私たちが救いへと選ばれたからです。その救いは今に始まったことではなく、永遠の昔から、この世界が造られる前から、神の御心の中で愛をもって定められていました。神のご計画を記した巻物が、この地上で少しずつ開かれていくようにして、世界の歴史が導かれてきました。その中で、神の器として選び分かたれた聖なるものとして、神の業のため用いられるがゆえに、教会もまた「聖なる国民」と呼ばれます。私たち教会は、争いと混乱に満ちたこの世界のただ中で、神ご自身がまことの支配者であり王である、神の国の民として召し出されているのです。
しかしながら、最初に御国の民として、神の宝の民として選ばれたのはイスラエルでした。アブラハムの選びから始まり、シナイ山の麓での契約締結を経て神の民となったイスラエルこそが、神の民の使命を果たすべく召され、遣わされていたのです。それは、「祭司の王国」としての務めでした。神はアブラハムを祝福の基とすることによって、罪による呪いを受けて全地に散らされたすべての民を再び祝福に招き入れようと計画しておられました。イスラエルの民は、神と世界の間に立って、祭司の務め、すなわち、執り成しの務めを担うようにと期待されていたのです。ところが、イスラエルの民が、地上の歴史の中で、神に背いて散らされ、祭司としての務めを担うことができなくなりました。それゆえ、神は、ご自身の独り子である御子イエスをユダヤ人の一人として生まれさせ、御子において、祭司の務めを立てようとされました。同じペトロの手紙一第2章の7節で言われていたように、「家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった」、あの十字架の出来事によって、完全な罪の贖いを成し遂げてくださいました。動物の犠牲による血をもってではなく、御子イエス・キリストの血によって罪からの救いの道を開いてくださったのです。御子を「隅の親石」、すなわち、かしら石、かなめ石として、主の復活の体である霊の家を建ててくださったのです。
何のためでしょうか。この世界を神の前に執り成すまことの祭司としての務めを貫くため。この世界を、神のものとして治めるまことの王の務めを貫くため。そして、この世界に、驚くべき救いの出来事を宣べ伝え、証しするまことの預言者としての務めを貫くためです。ペトロは言います。「それは、あなたがたを闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある顕現を、あなたがたが広く伝えるためです」。世界は今も、深い闇を抱えています。なおも罪の闇が支配しており、死の苦しみと傷みに満ちています。けれども、初めに、神が「光あれ」と言って光を創造し、闇を退けられたように、この世界にはキリストの復活の光が輝いたのです。神の独り子が十字架にかけられ殺されるというありうべからざることが起こりました。世界が罪の力に呑み込まれてしまったかのような深い闇を引き裂くようにして、復活の栄光が輝いたのです。主イエスを墓の中に閉じ込めた入口の大きな石が転がされたように、死が転がされて、命の光が輝いたのです。
私たちは、自分自身の中を覗き込めば、闇しか見えないかも知れません。死の恐れに捕らわれそうになります。けれども、主イエス・キリストを仰ぎ見るならば、死の闇を引き裂いた驚くべき光の中に招き入れられていることを知るのです。闇の中から光の中に移されている。罪と死の支配のもとから命の支配へと移されている。聖なる御国の民として召し出されている。主イエス・キリストを仰ぐとき、十字架と復活の主を仰ぎ見るとき、私たちはすでに、神の憐れみと赦しの中に生かされており、恵みと命に移されていることを信じることができるのです。主イエス・キリストの顕現にあずかるとき、主が今も生きておられ、私たちと共にいてくださる恵みを味わい知るのです。
闇の中から驚くべき光の中に招き入れられた。その恵みを具体的に現わすために、ペトロは、旧約聖書ホセア書の言葉を引用して、印象深く歌います。「あなたがたは、『かつては神の民ではなかったが 今は神の民であり 憐れみを受けなかったが 今は憐れみを受けている』のです」。引用されているのは、ホセア書2章の言葉です。そのホセア書1章から読んでいくと、預言者ホセアが味わった過酷な人生、不幸な結婚生活に言葉を失います。ホセアの妻であるゴメルは、夫を裏切って罪を犯し、他の男性との間に3人の子どもを設けます。しかし、神はホセアに対して、夫である自分の愛を裏切ったゴメルをなおも赦し、子どもたちと共に迎え入れるようにと命じられます。その過酷な体験を通して、神に背いて偶像の神々に惹かれていくイスラエルの民を、なおも赦し受け入れようとされる神の愛を深く知ることになるのです。ホセアは愛の預言者と呼ばれます。決して変わることのない神の愛を説いたのです。
その中で、主なる神は、ホセアに、2番目の女の子を「ロ・ルハマ」と名付けさせ、3番目の男の子を「ロ・アンミ」と呼ばせられます。最初の「ロ」は、否定を意味します。「ロ・ルハマ」は「憐れまれない者」という意味です。「ロ・アンミ」は「私の民でない者」を意味します。2人目の子が生まれたとき、主はホセアに言われたのです。「その子の名をロ・ルハマと呼べ。なぜなら、私はもはやイスラエルの家を憐れまず 彼らを決して赦さないからである」(ホセア1章6節)。そして、3人目の子が生まれたとき、主は言われます。「その子の名をロ・アンミと呼べ。あなたがたは私の民ではなく 私もまた、あなたがたのものではないからだ」(1章9節)。しかし、神は、その呪われた子どもの名前から、否定の「ロ」を取って、祝福に変えてくださいます。「憐れまれない者」という意味であった「ロ・ルハマ」は、「ルハマ」、すなわち、「憐れまれる者」と変えられます。「私の民でない者」を意味した「ロ・アンミ」は、「アンミ」、すなわち、「わが民」へと変えられるのです。それは、神に背いたがゆえに、神の愛と憐れみを失っても仕方のない者が、なおも神の憐れみを受け、神に愛されているということです。神に背を向けて、もはや神の民とは呼べない者が、なおも神の民とされているという、驚くべき赦しの恵みを証ししているのです。
ホセアの預言は、イスラエルの民について言われた言葉でした。しかし、それは、異邦人である私たちにとっては、そのまま、神の恵みによる「ビフォー/アフター」を告げていると言ってもよいのだと思います。かつてある神学者は、罪と死の力は、括弧の前についたマイナスのようなものだと言いました。私たちが自分の人生において、どんなのその中身を充実させて大きくしたとしても、括弧でくくってマイナスをつければ、結局全体はマイナスの値になります。罪と死は、まさに人生の呪いであり、すべてをマイナスに変えてしまう否定の力です。けれども、そこに、イエス・キリストの十字架の死という大きなマイナスをかけるとき、マイナスとマイナスをかければプラスになる。それが、主イエス・キリスト出会った私たちの人生なのです。主イエスは、ご自身の十字架の死によって、私たちの人生を縛り付けていた否定の力、罪と死によるマイナスをプラスに変えてくださったのです。
異邦人である私たちは、「『かつては神の民ではなかったが 今は神の民であり 憐れみを受けなかったが 今は憐れみを受けている』のです」(1ペトロ2章10節)。マイナスがプラスに変えられ、否定は大きな肯定に変えられた。私たちは、この驚くべき恵みを証しし、伝えます。かつては神の民でなく、神の憐れみを受けていなかった私たちが、今は神の民とされ、憐れみを受けています。だからこそ、闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある顕現を、広く伝えていくのです。
本日の説教題は、「何のために生まれ、何をして生きるのか」とつけました。聖書の中の言葉ではありません。どこから取った言葉か、よくお分かりの方が多いと思います。今話題の朝ドラのテーマの一つにもなりました。「アンパンマンのマーチ」の中の一節です。「なんのために 生まれて なにをして生きるのか こたえられない なんて そんなのは いやだ!」と歌います。「何のために生まれ、何をして生きるのか」。私たちも、かつては答えられませんでした。答えを求めながらも迷い続けていました。けれども、命の造り主であり、命の贖い主であるお方と出会って、私たちは確かな答えを見いだしたのです。自分のために、自分のしたいことをして生きようとしていると、先は見えません。闇の中です。けれども、主イエス・キリストの十字架と復活の光に照らされて、私たちの命の意味、私たちのなすべきこと、行くべき道が示されます。「神の民」、「神の子」とされた命を、喜んで、主のために献げて生きることができるのです。