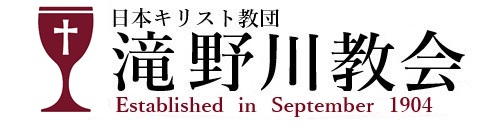2025年8月31日 主日礼拝説教「主の恵み深さを味わい知る」 東野尚志牧師
詩編 第34編6~11節
ペトロの手紙一 第2章1~3節
先週の月曜日から水曜日まで、私は夏期休暇の3日間を、京都で過ごしました。高校時代に寮生活を送った懐かしい京都市内で、のんびり休暇を楽しんだというわけではありません。日本基督教団の教師委員会が主催する「教師継続教育研修会」に参加しました。「教師継続教育研修会」、初めて耳にする方も多いと思います。今回で第6回というまだ歴史の浅い研修会です。教団の教師になって、3年から10年くらいまでの教師を対象とする研修会で、いわば「伝道者リトリート」、「牧師リトリート」と呼んでも良いと思います。
私自身は、伝道者になって今年で36年になります。今回の研修会の対象者ではありません。同じ教団の教師養成制度検討委員会からの派遣という形での参加でした。もうかれこれ14年近く、教団の教師養成制度の検討に携わっています。教師養成制度検討委員会というのは、神学校における教師養成、教団による検定試験の実施、そして、教師の継続教育、このシステム全体を見直しながら、より良い教師制度を整えるための検討をする委員会です。そういう意味で、今回は、教団の継続教育の実態に触れるため、ゲストとしての参加でした。けれども、一参加者としても、大きな祝福を味わうことができました。
「説教・牧会」というテーマで、2人の講師が立てられ、主題講演を聴いて分団協議をするという通常の研修会の形式でした。その中で、6回の礼拝が行われ、教師委員たちが分担して、司式・説教を担われました。開会礼拝で御言葉を聴き、1日目の夕礼拝で御言葉を聴き、2日目の朝礼拝で御言葉を聴き、また夕礼拝でも御言葉を聴く。3日目の朝礼拝で御言葉を聴き、最後、閉会礼拝でも御言葉を聴く。伝道者である委員が、同じく伝道者に向かって語る説教。その御言葉によって、深く慰められ、また励まされました。自分で御言葉を読み、御言葉を語るという普段の生活から離れて、同労者たちの語る御言葉の説教を聴き続ける、そういう3日間を過ごしたのです。そして、改めて思いました。伝道者だけではありません。私たち信仰者すべてにとって、御言葉を聴く、御言葉の説教を聴く、ということがどんなに大切であるかということ。御言葉にどっぷり浸かる、ということがどんなに幸いな経験であるかということです。
3日間、朝、昼、晩と食事も美味しくいただきました。肉体の命が健やかに養われるためには、食事が欠かせません。それと同じように、私たちの霊的な命が健やかに養われるためには、霊の食事が欠かせないのだと思います。生まれたばかりの幼子は、必要なすべての栄養を含んだ母乳によって養われます。やがては、離乳食を経て、柔らかいものだけではなく、硬いものも食べながら、体の健康を維持します。栄養のあるものを食べることで、体は大きく成長していきます。しかしながら、ある年齢を過ぎると、体の健康を守るために、食べるものに制限を受けることが始まります。私もこの歳になって、医者から脂質をあまりとらないように、塩分を控えるようにと指導される立場になりました。自分の好きなものを好きなだけ食べていたのでは、体の健康を維持することができないのです。
毎日の食事によって、私たちの体はつくられています。だからこそ、何を食べているか、ということによって、私たちの体も変わります。体の健康を維持するために、食べるものに気をつけなければならないのです。それは、肉体のことだけではなくて、私たちの魂、霊の命についても言えるのだと思います。魂の糧となるものをしっかり食べていないと、私たちの心は貧しくなり、弱くなります。霊の食事をきちんと摂っていないと、霊の命は痩せ細っていきます。枯れていきます。そして、ついには死んでしまうのです。心が痩せ細っても、目には見えません。霊の命が弱っても、自分ではそれに気づくことができません。果たして、今、私たちの霊の命は、健康な状態に守られているでしょうか。それは、何によって確かめることができるのでしょうか。
ペトロの手紙は告げています。「生まれたばかりの乳飲み子のように、理に適った、混じりけのない乳を慕い求めなさい。これによって成長し、救われるようになるためです」(2章2節)。この手紙は、洗礼を受けて、キリスト者としての生活を新しく始めた人たちに向けて書かれたとも言われます。直前の第1章の終わりのところ、23節では次のように言われていました。「あなたがたは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生ける言葉によって新たに生まれたのです」(1章23節)。洗礼を受けて、神の子としての新しい命をいただいた者は、生まれたばかりの乳飲み子のようなものだと言います。乳飲み子のようなキリスト者にとって必要なのは、ただひとつ「理に適った、混じりけのない乳」だと言うのです。これを慕い求め、これによって養われて、信仰者として成長するようにと言われます。
いったい、私たち信仰者を養い育て、救いへと導く「理に適った、混じりけのない乳」とは何のことでしょうか。私たちの聖書で「理に適った」と訳されているのは、ヨハネの福音書の冒頭の賛歌において、神の言葉、「言」と訳される「ロゴス」というギリシア語から出来た言葉です。「理に適った」とか「筋の通った」という意味があります。「霊的」と訳されたこともあります。かつての口語訳や新共同訳の聖書では、「霊の乳」と訳されていました。もとが「ロゴス」ですから、「御言葉の乳」と言い換えてもよいと思います。筋の通った、混ぜ物のない、純粋な神の言葉を慕い求めよ、と言うのです。
私たちが、純粋な神の言葉によって養われ、生きるために、捨てるべき物があります。私たちがキリスト者として生きるために、何を求めるべきかが2節で述べられ、そのために何を捨てたらよいかを1節で語っているのです。「だから、一切の悪意、一切の偽り、偽善、妬み、一切の悪口を捨て去って」。「捨て去って」と訳されているのは、「脱ぎ捨てる」という意味の言葉です。着物を脱ぐようにすべて脱ぎ捨てなさい、というのです。着ているものを脱ぎ捨てたら裸になります。新しく生まれて、乳飲み子になるということは、まさに、それまで身に着けていたものを一切脱ぎ捨てて、乳飲み子のように、裸になるということです。無防備になるということです。いったい、私たちが自分で自分の身を守ろうとして、それまで後生大事に身にまとっていたのは何でしょうか。「悪意、偽り、偽善、妬み、悪口」と列挙されます。私たちの心のうちにあるものが、外に現れ出てくる様子をよく現わしていると思います。
すべては私たちの心の内に宿った「悪意」から始まります。神に背を向けてしまったために、ねじけて歪んだ心から、「偽り」が生まれます。ここに、神と人との関係を損ない、人と人との関係を引き裂いてしまう悪しきものの根源があります。すべては、悪意と偽りから出てくると言ってもよいのです。だからこそ、最初に、「一切の悪意、一切の偽り」というように、強調して語るのです。この悪意と偽りが形をとって現れたものの第一が「偽善」です。舞台の役者が仮面をつけて演じることから生まれた言葉です。裸のままの自分、自分の本心を隠して、相手から見える面だけを装い、ごまかすことを意味します。本当は弱いのに、強そうな顔をする。本当は愛がないのに、いかにも愛に溢れているかのように見せかける。信じていないのに、信じているふりをする。そうやって、人の目に、自分を良く見せようとするのです。
次に現れるのは「妬み」です。どのような団体でも、またグループでも、人が集まるところでは、必ず、「妬み」の思いがうごめきます。それが罪ある人間の現実です。教会も例外ではありません。優れた働きをしている人のことを純粋に称賛するのではなくて、そこに、妬みの思いが忍び込みます。自分と比べてしまうからです。相手の方が自分よりも優れているということを認めるのが悔しくて、妬んでしまう。いったい、他人のことを妬んだことのない人がいるでしょうか。人から認められたい、人から褒められたい、という思いが強いほど、その反面として、認められ、褒められている人に対する妬みが渦巻きます。妬みは、人間関係をねじ曲げてしまいます。そして、この妬みの思いが外に現れるとき、「悪口」となるのです。
だれかと仲良くなろうと思ったら、その場にいない人の悪口を言えばよい、そんなことさえ言われます。私たちは、とかく、人の噂話が好きなのです。主イエスは、言われました。「二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである」(マタイ18章20節)。主イエスは、2人、3人が集まって、兄弟の救いのために祈りを合わせることを願われました。主の名によって祈る者たちのただ中に、主ご自身が共にいると約束してくださったのです。しかしながら、私たちの現実はどうでしょうか。2人、3人が集まれば、誰かの悪口を言い、それで盛り上がる。誰かの悪口を言うことで結びつくような交わりというのは何でしょうか。そこに、主イエスはおられるでしょうか。いや、主イエスがおられたら、とても恥ずかしくてそんな話はできないはずです。主はおられない、主は聴いておられない、そう思っているからこそ、安心して、人の悪口を言うのです。ある人は、人の悪口は、殺人よりも罪が重い、と言いました。殺人は、1人の人の命を奪うだけである。しかし、人の悪口は、それを言われている人の命を奪い、聴いて同調している人の命を奪い、言っている本人の命を奪う。確実に、3人の命を奪うことになる、と言うのです。人の悪口を言うことで、憂さ晴らしをしているつもりが、実は、自分自身の霊の命をも深く傷つけることになっている。そのことに気づかないのは、まことに不幸なことだと言わざるを得ません。
キリストの救いを知らなかった時には、自分で自分を守るために、「悪意、偽り、偽善、妬み、悪口」を身にまとっていました。けれども、キリストと出会ったら、すべて脱ぎ捨てて生まれ変わり、無防備な乳飲み子のようになる。無防備と言いましたけれど、神の子とされて、神さまご自身が守ってくださるのですから、これほど確かな守りはありません。だから、自分で幾重にも重ね着をして自分を守ろうとするのではなくて、「一切の悪意、一切の偽り、偽善、妬み、一切の悪口を捨て去って、生まれたばかりの乳飲み子のように、理に適った、混じりけのない乳を慕い求めなさい。これによって成長し、救われるようになるためです」。御言葉はそのように告げるのです。私たちがこの世で生きるときには、いろんなものを身に着けながら、成長していきます。残念ながら、その過程で、さまざまな不純物や悪しき習慣まで身につけてしまいます。この世の習わしに染まっていくのです。しかし、主イエス・キリストと出会ったとき、そのすべてを断ち切り、脱ぎ捨てて、筋の通った、混ぜ物のない、純粋な神の言葉によって養われるように、変えられるのです。
「成長し、救われるようになるため」とありました。誤解をしてはならないと思います。私たちは、すでに、主イエスの十字架によって罪赦され、復活によって新たな命に生かされているはずです。私たちは、すでに救われているのです。しかし、いまだ救いは私たちにおいては完成されていません。私たちは、救いの完成に向かって、成長していくのです。私たちが、混じりけのない、真実な神の言葉によって養われ、成長していくとき、教会の交わりもまた、清められ、成長していくのではないでしょうか。妬みや人の悪口によって結びつくのではなくて、霊の糧である御言葉によって結び合わされた命の交わりを喜ぶようになるのです。
2人、3人が主の名によって集まり、主の名によって祈りを合わせる。そこに、主が共にいてくださいます。そこでこそ、私たちは、主の恵みを味わいます。ペトロは言います。「あなたがたは、主が恵み深い方だということを味わったはずです」(2章3節)。ここで「恵み深い」と訳されているのは、普通に恵みを言い表す言葉とは違います。ぶどう酒がうまい、美味しいという意味でも使われる「クレーストス」という言葉です。キリストを現わす「クリーストス」と良く似ています。私たちの主である「クリーストスはクレーストス」、そういう掛詞になっているのです。
ある人は、この「クレーストス」という言葉は、恵み深いというのを通り越して、極端に親切な人、お人好し、そんな意味に近いと説明しています。神は底抜けに善良であってお人好しであられる、というのです。確かに、幾たび裏切られても見捨てることなく信じ抜いてくださいます。どんなに背かれても、愛し抜いてくださいます。そして、罪深く、少しも真実でないものを、どこまでも赦そうとしてくださいます。私たち人間は、このような底抜けのお人好しで恵み深いお方に出会わないと、いつまでたっても、つまらない偽りによって自分の身を守ろうとすることから抜け出ることができないのだと思います。私たちを無条件で受け入れてくださる十字架の主キリストにおいて、私たちは本当のクレーストス、恵みの美味しさを味わい知るのです。そこから、新たな歩みが始まります。すべての偽善や妬み、悪口を脱ぎ捨てて、この恵み深いお方の命の言葉を本気で聴こうとする歩みが始まります。このクレーストスなお方の前では、自分を偽る必要はなく、人を妬む必要もない。ありのままの自分をさらけ出して、恵みにあずかることができるのです。何度もつまずき、挫折を味わったペトロが、キリストのクレーストスによって立ち直り生かされて来た恵みの証し人として語ります。「あなたがたは、主が恵み深い方だということを味わったはずです。主のもとに来なさい」。備えられ、差し出された恵みに、感謝をもってあずかりましょう。