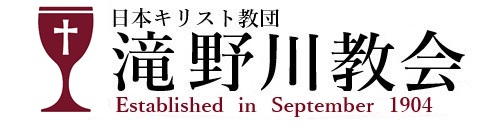2025年8月10日 主日礼拝説教「キリストを知る以前と以後」 東野尚志牧師
レビ記第11章44~45節
ペトロの手紙一第1章13~21節
今日は、この礼拝を終えた後、軽井沢へと移動して、夏の修養会を行います。40 年前、私が滝野川教会の神学生であった頃は、大人と子どもを合わせると 100 人を超える人たちが、軽井沢の女子聖学院セミナーハウスへと大移動しました。40 年というと、聖書的には、世代交替が起こる歳月ということになります。もはや軽井沢のセミナーハウスもありません。東洋英和女学院の寮を借りて、20 人ほどの参加者による修養会となります。泊まりがけの参加が、年々、難しくなっているのかもしれません。ノスタルジーに浸るのではなく、これからの修養会のあり方を前向きに考えていきたいと思います。今、ご一緒に礼拝をしている方たちの多くは、礼拝が終わると、それぞれの家に帰って行かれることと思います。しかし、ぜひとも、軽井沢の地で行われる教会の修養会を皆さんの祈りのうちに覚えていただきたいと願っています。
今年の夏期修養会は、今年度の年間聖句であるペトロの手紙一、第2章9節の言葉を中心にして、2章の1節から10節までを取り上げています。「新しい神の民―恵みと祝福のうちに生きる―」という主題を掲げました。旧約聖書に描かれた「神の民イスラエル」の歴史を踏まえながら、私たち教会は、イエス・キリストによって「新しい神の民」として招集されています。神の民に約束された祝福と、使命を受け継いでいるといってよいのです。第 2 章の10節には、私たちについて、興味深い言葉が記されています。「かつては神の民ではなかったが 今は神の民であり 憐れみを受けなかったが 今はあわれみを受けている」というのです。
聖書を読んでおりますと、しばしば、私たち信仰者の「かつて」と「今」がくっきりと描き分けられていることに気づきます。「かつては神の民ではなかったが 今は神の民」である、と言われました。実は、今日の箇所、1 章の13節から21節までの間にも、「かつて」と「今」が対比するように描かれています。ペトロは容赦なく、私たちの「かつて」、私たちの過去について記します。かつては無知であり、自分の欲望に引きずられ、罪を重ねていた。そういう生き方をひっくるめて、「先祖伝来の空しい生活」と呼んでいます。かつての生き方をネガティブな響きの言葉でえぐり出すのです。
そして、それとくっきり対比するように、キリストに結ばれた「今」をポジティブに描いていきます。今では、かつてのむなしい生活の中から贖い出され、召し出されて、神の子とされている。神を「父」と呼ぶ幸いな交わりの中に召されている。そのように語るのです。私たち一人ひとりにも、「かつて」と「今」があるのではないでしょうか。イエス・キリストを知らなかった「かつて」の生活があります。神を信じていなかった「かつて」の人生があります。しかし、今では、神を知っている、いや、神に知られていることを知った。今では、イエス・キリストを主と仰ぎ、神を父と呼ぶ幸いを知っている。そして、聖餐の恵みを深く味わう、幸いな交わりの中へと招かれているのです。
私たちの「かつて」と「今」を分ける、その中心に、イエス・キリストがおられます。ペトロは語ります。「キリストは、天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時に、あなたがたのために現れてくださいました」(1章20節)。私たちの「かつて」と「今」を切り分ける中心に、十字架と復活の主が立っておられます。私たちは、キリストの十字架の死に合わせられて、古い罪の自分に死にました。そして、キリストのよみがえりに合わせられて、神に生きる者、神の子とされました。キリストのものとして、キリスト者として生きる新しい命を与えられたのです。このキリストの復活に連なる命が無駄になってしまうようなことがあってはなりません。それはキリストの死を無駄にすることになります。キリストの復活を空しいことにしてしまいます。だからこそ、ペトロは、私たちに語りかけるのです。恵みをしっかりと指し示しながら、勧めるのです。
「それゆえ、あなたがたは心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みを、ひたすら待ち望みなさい」(1章13節)。イエス・キリストは、今から二千年前、ひとたび、この地上に現れてくださいました。そして、終わりの時に、再び現れてくださいます。私たちの死ぬべき体が贖われ、復活の体が与えられ、私たちのうちに既に始められている救いの御業を完成するために、主は再び来てくださいます。主の再臨の約束を信じ、待ち望みながら、心を引き締め、身を慎んで生きるように、と使徒は教えるのです。
「心を引き締め」るというのは、おもしろい表現が用いられています。かつての口語訳聖書においては、「心の腰に帯を締め」と訳されていました。それが直訳です。当時の人たちは、上から下までずどんと垂れた衣を着ていました。何か仕事をするためには、そのままでは具合が悪いのです。だから、腰に帯を締めて、着物の裾をその帯に挟み込みました。足元にまつわりつく邪魔な裾をたくし上げて、足が自由になるようにしたのです。日本で言えば、和服にたすきを掛けて、腕の動きを自由にするのと似ているかもしれません。ちょうどそのように、心の腰に帯を締めて、心が自由に動くようにする。ここで言う心は、感情よりも、判断を司る場所です。「心を引き締める」「心の腰に帯を締める」というのは、さまざまな囚われや束縛から心が自由になって、自由な判断ができるようにするのです。
考えてみれば、私たちの心は、日々、いろいろなことに囚われています。主イエスは言われました。「自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで何を着ようかと思い煩うな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか」(マタイ 6 章 25 節)。そして言われます。「空の鳥を見なさい」「野の花がどのように育つのか、よく学びなさい」。父なる神が、私たちのことを心にかけていてくださり、養い導いてくださる。本当に必要なものは、神が備えてくださる。だから、思い煩うな、と言われました。あの良く知られた言葉で結ばれます。「だから、明日のことを思い煩ってはならない。明日のことは明日自らが思い煩う。その日の苦労は、その日だけで十分である」(6章34節)。
けれども、決して、自分の生活の思い煩いだけではないと思います。皆さんは、この数日の報道をどのようにご覧になってきたでしょうか。今、この世界で起こっていること、戦後80年を経ても、なおこの世界から戦争がなくならない現実。テレビの特集番組を見て、改めて、80 年前の原爆の被害のすさまじさを思うと、心が凍ります。猛暑続きで環境や作物に被害が出ているかと思えば、降れば土砂降り、洪水で車や家が流されていく。心が痛みます。戦争や災害を、他人事ではなく、自分事として受けとめていくとき、私たちの心はいろんな心配事や悩みに囚われてしまいます。そうなると、本当の意味で、自由な判断ができなくなるというのです。
いったい、どうすればよいのでしょうか。ペトロは、「心を引き締め」という言葉に続けて「身を慎み」と語ります。「身を慎」むという言葉は、文字通りに言うと、酒に酔わないということを意味します。しらふでいる。何か酔っぱらっていい気持ちで夢や幻を見るというのではなくて、きちんと目覚めているということです。目を覚まして現実を見るということです。
かつて、「宗教は阿片だ」と言った人がいました。宗教は、人間の現実から目をそらして、夢物語のような救いの話をするという考え方があります。だから、現実的な人間は、宗教などに惑わされないと言われるのです。宗教なんて「はしか」のようなものだという言い方もあります。しばらく熱に浮かされているが、夢は過ぎ去ってしまう。熱が冷めると、厳しい現実に引き戻されるのです。私も昔は教会の礼拝に出ていました。聖書を読んだことがあります。そんな思い出話を聞かされると、複雑な思いがします。
けれども、聖書の言い方は、真逆です。イエス・キリストを信じることによって、現実離れした夢見る人になるというのではありません。むしろ、イエス・キリストを信じることによって、私たちは本当に目覚めていることができる、と言うのです。恐れず、勇気を持って、現実と向かい合い、真実を見ることができるというのです。世界の造り主である神を否定して、人間が万能の力を持っているかのような幻想から解き放たれて、本当に目覚めた自由な心で、この世界の真実を見抜くことができるようになるというのです。
「現実を見る」というのは、実際には、とても厳しいことだと思います。むしろ、私たちは、自分の現実を受け入れることができずに、自分からも、世界からも目を逸らし、逃げ出したくなることがあるのではないでしょうか。酒に酔うというのは、まさにその一つです。酒を飲んでいる間だけは、煩わしい人間関係や、自分が置かれている厳しい現実から逃れて、すべてを忘れることができる。しかし、酔いが醒めたときに待っているのは、より深い絶望ではないでしょうか。私たちにも逃げ出したい、投げ出してしまいたい現実があります。次第に年老いていくという現実、重い病を身に負うという現実。家族の病、家族の死。そのままでは受け止めきれないような厳しい現実です。けれども、私たちの中に、キリストの福音というくさびが打ち込まれたとき、私たちは、イエス・キリストにある恵みの現実を知りました。イエス・キリストにおいて、現実と向かい合います。
私たちには受けとめきれないような厳しい現実を、イエス・キリストが受けとめていてくださるのです。罪によって引き裂かれ、愛に破れてしまっている現実、死の力に脅かされる私たちの現実のただ中に、キリストが来てくださいました。私たちの破れのただ中に立って、そのすべてを、十字架の傷を刻んだ御手で受けとめてくださいます。キリストが、私たちをしっかりと捕らえてくださり、私たちの現実を受けとめてくださいました。そのとき、私たちは、自分の現実と向かい合う勇気を持つことができたのです。イエス・キリストによってしっかりと捕らえられて、私たちの心の腰が安定したとき、恐れることなく見つめることができる。この世の現実のただ中にあって、キリストに結ばれた「聖なる者」として生きる道を見いだすのです。
ペトロは言います。「あなたがたを召し出してくださった聖なる方に倣って、あなたがた自身も生活のあらゆる面で聖なる者となりなさい。『聖なる者となりなさい。私が聖なる者だからである』と書いてあるからです」(1 章 15~16 節)。聖書の言う「聖なる者」というのは、道徳的に立派な聖人君子ということではありません。聖なる方によって捕らえられた者、神のものとして選び分かたれた者のことです。私たちも今、この世の現実のただ中にあって、それぞれに厳しい現実を抱えながら、神によって選び出され、礼拝の中に導き入れられ、聖なる者とされています。そして、聖餐を分かち合うことによって、まさに聖なるものにあずかるのです。キリストの生命にあずかる。そのために、どのような大きな犠牲が払われたのかを思い起こさせようとして、ペトロは語ります。「あなたがたが先祖伝来の空しい生活から贖われたのは、銀や金のような朽ち果てるものによらず、傷も染みもない小羊のようなキリストの尊い血によるのです」(1章18節)。あなたがたは、そのことを知っているはずだ、「知ってのとおり」と語るのです。
ここに私たちの救いの現実があります。これは、決して、幻想ではありません。ひとときだけの慰みではありません。主の再臨によって完成される、確かな望みとしての救いの現実がここにあります。私たちの地上の生活を仮住まい、寄留する間、と呼ばせるほどの、天の祝福の確かさが、今私たちの前に差し出されているのです。
今日の箇所の結びの言葉を、しっかりと心に刻みたいと思います。「あなたがたは、キリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神を、キリストによって信じています。したがって、あなたがたの信仰と希望とは、神にかかっているのです」(1章21節)。私たちの信仰と希望は、神にかかっている、と言われます。「神にかかっている」。これ以上、確かなことがほかにあるでしょうか。人に対する信頼や希望は、しばしば裏切られます。そもそも自分自身のことを考えれば、何とも心もとない存在であることを認めざるを得ません。しかし、神に対する信頼と希望は、決して裏切られることはありません。
なぜなら、この方は、私たちの罪を赦すために、大切な独り子キリストを十字架に引き渡されました。そして、キリストを死者の中から復活させて、罪と死の力に打ち勝ってくださいました。さらには、キリストに栄光を与えて、キリストによる救いが確かなものであることを現わしてくださいます。私たちは、この礼拝において、神の右におられる栄光のキリストを仰ぎ見ることができるのです。私たちの信仰と希望が、決して空しくなることはないと、神が保証してくださいます。私たちは、主イエス・キリストを通して、このお方を「父」と呼んでいます。神の子とされた恵みの中で、新しい神の民である教会のひと肢として、心から神をほめたたえる。この礼拝から、すでに、新しい神の民としての学びと祝福が始まっているのです。