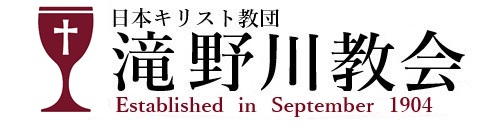2025年7月20日 主日礼拝説教「死に勝つ望みに生きる」 東野尚志牧師
エレミヤ書 第17章 5~8節
ペトロの手紙一 第1章 3~9節
先週は、台風の影響を受けて、久しぶりにまとまった雨が降りました。雨雲が晴れた金曜日には、関東地方でも梅雨明けとなったようです。6 月から 7 月にかけて、梅雨であることを忘れさせるような猛暑が続きました。これで梅雨が明けて、いよいよ本格的な夏の到来となります。
朝から 30 度を超える中、主の日の礼拝をささげるため、教会堂に集われた皆さまお一人びとりの上に、父・子・聖霊なる神の祝福と平安を祈ります。健康の不安を抱えながら、また遠方から、オンラインの礼拝に連なる方たちの上にも、主の祝福を祈ります。教会に連なるすべての方たちの上に、そして、神が愛しておられる、造られたすべての命の上に、天地万物の造り主であり、命の贖い主である神の守りと祝福を祈ります。
すでに役員会の協議を経て、ご案内をして参りましたように、来週の日曜日から、教会は一部、サマー・タイムを導入します。通常の主日礼拝の時間は、10 時 15 分から 11 時 45 分までとして案内しています。けれども、次週の主日から 8 月いっぱいと 9 月第1主日まで、礼拝開始時刻を 15 分早めます。そして、礼拝終了時刻を 30 分早める予定です。主日礼拝は、午前 10 時から開始して、11 時 15 分終了を目指します。礼拝開始を早めるだけではなくて、礼拝全体の時間も 15 分短縮することになります。そうやって、日曜日の朝、礼拝に集われた皆さまが、暑さのピークを迎える前に、帰途に就くことができるようにします。
礼拝時間を短くするというとき、真っ先にやり玉に挙がるのは、説教の時間です。誰もが、説教を短くするということを考えます。それは簡単なようで、実は一番難しいことでもあります。プロテスタント教会は、御言葉が読まれ、説かれることによって礼拝が成り立つことを大事にしてきました。主の日の公同礼拝を成り立たせるために必要な説教を、語る者も聴く者も一緒に求めて行かなければなりません。そのことを疎かにしないようにしながら、時間を短くするように、準備を整えたいと思います。
役員会の協議の中では、毎週の礼拝で祝う聖餐式の式文を短くするとか、讃美歌を減らすという案も出ました。かつてコロナ禍のもとで、讃美歌の数を減らしたり、歌う節の数を減らしたり、交読文を省略したりしたことがありました。これは、確かに、礼拝時間を短くするという意図もありましたけれど、むしろ、感染予防のために、礼拝者が声を出す、発話の機会を減らすという狙いが大きかったと思います。プロテスタント教会の信仰では、御言葉の説教がなければ礼拝そのものが成立しません。しかしまた、賛美と祈りも、礼拝の欠かせない要素です。これは安易に削ってよいものではないと私は思います。
詩編の中には、「主を賛美するために民は創造された」という言葉があります(詩編 102 編 19 節、新共同訳)。あるいはまた、17 世紀に英国の神学者会議が生み出した「ウェストミンスター教理問答」は、その第一の問いとして、「人間の主要な目的は何ですか」という問いを立てて答えます。「人間の主要な目的は、神の栄光をたたえ、永遠に神を喜ぶことです」。人生の目的とか、生きる意味について考えるとき、私たちはしばしば、生きがいという言葉に引きずられて、自分自身の必要や願いが満たされることを考えます。けれども、聖書の信仰から導き出される答えは、違います。私たちが、神の栄光をたたえ、永遠に神を喜ぶこと、つまり、私たちの命の造り主であり、贖い主である神を正しく知ることを通して、神をほめたたえ、神との交わりの中に生かされていることを喜び祝うことだというのです。礼拝は、御言葉の説教なしには成立しません。しかし、御言葉の説教を通して、神がどのようなお方であり、神が私たちのために何をしてくださったかが告げられるとき、私たちは共々に、心から神をほめたたえ、感謝と賛美の歌を歌う。それが礼拝です。礼拝は、賛美に始まり賛美に終わると言ってもよいのです。
私たちは、主の日の礼拝において、ペトロの手紙一を読み始めました。前回は、手紙の差出人と受取人、そして挨拶を記した冒頭部分を読みました。それを受けて、先ほど朗読した第 1 章 3 節から手紙の本文が始まることになります。ペトロの手紙が、その本文の最初に記したのは何でしょうか。ペトロは語ります。「私たちの主イエス・キリストの父なる神が、ほめたたえられますように」。これは賛美の言葉です。もちろん、ペトロが教会に対して、伝えたいことはたくさんあったはずです。しかし、まず初めに、神を賛美する言葉を記しました。挨拶に続く本文の冒頭に、神への賛美を記したのです。
「私たちの主イエス・キリストの父なる神が、ほめたたえられますように」。聖書の原文の順序では、「ほめたたえられますように」という言葉が最初に記されています。その思いをよく映し出したのは、口語訳聖書でした。「ほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神」。私たちの主イエス・キリストの父なる神こそは、ほめたたえられるべきお方、賛美を受けるにふさわしいお方、そう言って、神を賛美することから始めたのです。確かに、礼拝を成り立たせるのは、神の言葉であり、神の言葉の説教です。けれども、その礼拝において、私たちが最初になすべきことは、神を賛美することです。一週間の歩みを終えて、新たな週の初めを迎えたとき、もちろん、神さまにお願いしたいことがたくさんあります。神さまの赦しと憐れみを求めなければなりません。そして、新しく赦しの言葉を聞くのです。けれども、そのすべてに先立って、神の御前で私たちがなすべきことは、神を賛美し、神をほめたたえることなのです。
「ほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神」。そのように歌った後、私たちが神を賛美する理由が述べられていくことになります。父なる神が、主イエス・キリストにおいて、私たちのために備えてくださった救いを描いていきます。そして、その救いにあずかっている私たち自身の喜びについて語るのです。第 1 章の 8 節と 9 節をご覧ください。「あなたがたは、キリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせないすばらしい喜びに溢れています。それは、あなたがたが信仰の目標である魂の救いを得ているからです」(1 章 8~9 節)。短い言葉の中に、イエス・キリストに結ばれて生きる私たちの、愛と信仰と希望が、見事に言い表されています。キリストを見たことはないのに、この方を信じている。信じているがゆえに愛している。そしてキリストによって約束された救いを望みながら、今既に、その救いに生かされている喜びを深く味わっているというのです。私たちがイエス・キリストに対する愛と信仰と望みに生きるとき、そこには、素晴らしい喜びが満ちあふれてくる。聖書は、そのような信仰者の喜びを証ししているのです。
聖書は、繰り返して、私たち信仰者に与えられている「喜び」について語ります。「ウェストミンスター教理問答」も、その冒頭に喜びを掲げました。「人間の主要な目的は、神の栄光をたたえ、永遠に神を喜ぶことです」。しかし、考えてみると、喜びについて語るということは、案外、難しいことなのではないかと思います。どれほど真剣に、一所懸命になって喜びを語ったとしても、聞いている者にその喜びが伝わらなければ、何の意味もありません。しばしば、喜んでいるのは本人だけで、聞いている者はかえって白けてしまうということが起こります。体の痛みに苦しみながらも喜ぶことができる。徐々に体の力が失われていく不安に直面しながらも喜ぶことができる。その言葉が、決して、やせ我慢でもなく、また自己満足でもなくて、本当の喜びであるためには、その喜びの源としっかりつながっているということがなければならないのだと思います。教理問答が告げるように、信仰の喜びの究極は、「神を喜ぶ」ということになります。喜びを語る者は、その喜びの根拠をしっかりと見つめ、また指し示しながら、聞く者たちを喜びへと招いていくのです。
今、この手紙を書いているペトロ自身が見つめている喜びの源は何でしょうか。ペトロは語ります。「あなたがたは、終わりの時に現されるように準備されている救いを受けるために、神の力により、信仰によって守られています。それゆえ、あなたがたは大いに喜んでいます」(5~6a 節)。私たち信仰者に与えられている喜びは、終わりの時と結びついているのです。その直前には、こう書かれています。「また、あなたがたのために天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、消えることのないものを受け継ぐ者としてくださいました」(4節)。私たちが受け継ぐべき財産は、天に蓄えられています。それは、今、この地上で目にすることはできません。しかし、その一切は、終わりの時に現されることが約束されているのです。「終わりの時」という言葉は、さらに、「イエス・キリストが現れるとき」と言い換えられていきます(7 節)。終わりの日を待ち望む信仰は、イエス・キリストが来られるのを待ち望む信仰と結びついています。そして、私たちの信仰は、「イエス・キリストが現れるときに、称賛と栄光と誉れとをもたらす」と約束されているのです。信仰者の喜びは、単純に今を生きる喜びではありません。終わりの日に約束された救いの恵み、その栄光と誉れから捉え返された今を生きるとき、そこに溢れてくる喜びです。終末論的な喜びと呼んでも良いと思います。
私たちは、終わりの日の約束を目指して生きています。イエス・キリストの現れる時を目指して歩んでいます。そうであればこそ、私たちが生かされている今の時を、「今しばらくの間」と捕らえることができます。ペトロは言います。「今しばらくの間、さまざまな試練に悩まなければならないかもしれませんが」(6 節)。この手紙が書かれた時代は、既に、キリスト教信仰に対する迫害が激しくなってきた頃だと言われます。信仰のゆえに捕らえられ、むち打たれ、殺されるということが起こるのです。しかし、その試練も、「今しばらくの間」のことだと言い切るのです。永遠に続くわけではありません。終わりが来るのです。そして、その区切られた、今しばらくの間だけ悩まされる試練によって、信仰が本物であると証明され、その信仰が鍛えられていく。イエス・キリストが現れる時に、称賛と栄光と誉れをもたらすような信仰へと、練り清められていくと言うのです。
私たちは、いつも自分の信仰がもっと強くなるようにと願っているのではないでしょうか。簡単にくじけてしまうことがないように、もっと強い信仰に生きたいと願っています。体だって、強くするためには鍛えなければなりません。心もまた、鍛えることを怠ると、甘えたわがままなものになります。ましてや信仰も、本当に強い信仰を得たいと願うならば、それが鍛えられるということを避けるわけにはいきません。ある人が、信仰が強くなるというのはどういうことかと問いながら、書いています。それは、私たちの信仰が、さらに純粋な、混じりけのない信仰になることである、と言うのです。そして、そのことを具体的に言えば、甘ったれていない、まことの神に対する正しい態度をもった信仰、また、どんな困難があっても、祈ることができる信仰、あるいは、いつでも、何事もないときでも、祈ることができるような信仰。また、人から嫌なことを言われても、されても、その人を赦し、その人のために尽くすことのできる信仰、さらに、多くの誘惑の中にあっても、まちがった生活をしない信仰。つまり、清い心を持ち、何よりも、神に従うことを喜びとする信仰だと言うのです。そのような信仰が、今しばらくの間の試練の中で鍛えられていくのです。
では、何のために、信仰が鍛えられ、信仰が強くなることを求めるのでしょうか。もしもただ自分が立派な信仰生活をするためであるとするなら、それも自己満足のためになるのではないでしょうか。信仰は、それ自体、神への献げ物とするのでなければ、本当に純粋なものとはなりません。私たちは、試練の中で信仰を鍛えられながら、終わりの時、主イエス・キリストの来られる時を待ち望むのです。イエス・キリストの現れるとき、私たちの信仰の試練が、称賛と栄光と誉れとをもたらす、とペトロは言いました。しかし、間違えてはなりません。私たちの信仰が称賛され、私たちが栄光と誉れに満たされるということが、大事なのではありません。イエス・キリストが現れるとき、私たちはその御前にひざまずいて、主を礼拝する。その時、私たちの信仰は、神への称賛、栄光、誉れに変えられるのです。神が喜ばれる献げ物になるのです。
信仰は苦しいときにも支えになると言います。病の痛みの中でも、信仰があるから大丈夫だと言います。それは決して間違っていないと思います。しかし、私たちの信仰は、私たちにとって役立つだけではないのです。むしろ、信仰もまた、神への献げ物として役立てられるのです。主イエス・キリストが来られるとき、私たちが主にお献げすることができるのは、信仰以外にありません。そして、私たちが信仰をもって神の御前に立つとき、そのような私たちの信仰によって、神が賛美と栄光と誉れを受けてくださる。神に一切の栄光を帰することによって、私たちもその神の栄光に照らされて、神の栄光を映し出すものとされるのです。
終わりの日について語るとき、聖書は決して、空想的な話をしているのではありません。終わりの日の栄光は、今既に、望みとして私たちに与えられているからです。そうであればこそ、今、私たちに喜びをもたらすのです。ペトロは言います。「神は、豊かな憐れみにより、死者の中からのイエス・キリストの復活を通して、私たちを新たに生まれさせ、生ける希望を与えてくださいました」(3 節)。私たちに与えられているのは、「生ける希望」です。「生きる希望」ではありません。私たちが生きていくための望みではないのです。そうではなくて、この希望が生きているのです。生きている希望です。死んだ望みではありません。私たちが生きているときだけではなくて、死ぬときにも、私たちが息をしなくなるときにも、私たちを支える望みなのです。神は豊かな憐れみをもって、私たちをこの望みへと招いてくださいました。終わりの日の称賛と栄光と誉れを目指して、この生きた望みに支えられ、喜びをもって、愛と信仰の歩みを続けるようにと招いておられます。私たちを支える望み。それは決してむなしい望みではありません。イエス・キリストの死とよみがえりによって、確かな保証が与えられています。主とひとつに結ばれる洗礼を受けて、新たに生まれた者たちが、聖餐の食卓を囲んで、この確かな救いの約束に連なり、喜びを分かち合うのです。
英国に留学していたとき、学期中の金曜日の朝早く、コレッジのチャペルに神学生たちが集まって、短い聖餐礼拝を行っていました。「ユーカリスト」と呼ばれていました。聖餐式の式文が読まれていく中で、集った者たちが一緒に唱える言葉がありました。Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. 「キリストは死なれた。キリストはよみがえられた。キリストは再び来られる」。ここに、私たちの信仰の根拠があり、救いのすべてがかかっています。キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、私たちの罪はすべて贖われ、赦されました。キリストが復活してくださり、今も生きておられることによって、私たちが神の子として新しく生まれる命の道が開かれました。そして、キリストが再び来てくださる終わりの日、私たちは、よみがえりの体を与えられて、約束された永遠の命を受け継ぐのです。称賛と栄光と誉れがもたらされ、私たちは永遠に、主をほめたたえ、神を喜ぶ者として、祝宴に連なる者とされる。その時を信じ望みながら、今しばらくの試練のとき、互いに支え合い、励まし合い、執り成し合いながら、礼拝から礼拝へと、共に主をほめたたえて生きるのです。