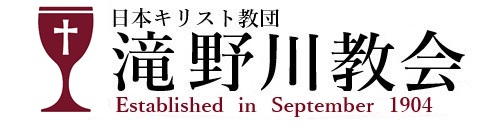2025年7月13日 主日礼拝説教「主イエスに祈られて」 東野ひかり牧師
ルカによる福音書 第6章12~16節
イザヤ書 第55章6~7節
**********
ルカによる福音書 第6章12~16節
12 その頃、イエスは祈るために山に行き、夜を徹して神に祈られた。13朝になると弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選んで使徒と名付けられた。14それは、イエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そして、ヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、15マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、16ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。
**********
讃美歌307番を共に歌いました。あまり歌ったことのない讃美歌だったかもしれません。「祈祷」という表題がつけられています。4番の歌詞は、祈って野に夜を明かした主イエスのお姿を思う歌詞です。今朝私たちに与えられました聖書のみ言葉は、主イエスが山で夜を徹して祈られた、ということを伝えるみ言葉です。それで、この讃美歌を選びました。また5番の歌詞は、主イエスが今もなお、天にあって私たちのためにとりなし祈っていてくださる、そのような主イエスの祈りのお姿を、私たちの心に映し出してくれるような歌詞です。この讃美歌を歌って、今日のみ言葉へと導かれたいと思いました。
ルカによる福音書第6章12~16節は、短い箇所ですけれども、主イエスが徹夜の祈りをなさったという、大変重々しい雰囲気を感じさせる場面です。今朝は、この主イエスの祈りのお姿に心を集めながら、共にみ言葉に聴いて参りたいと思います。
ルカによる福音書は、他の福音書よりも多く、「祈る主イエス」のお姿を私たちに伝えてくれます。ご一緒に聖書を開きながら、ルカ福音書が伝える「祈る主イエス」のお姿が記される箇所を丁寧にたどるなら、とても豊かなみ言葉の経験をすることができるかと思いますが、まず、いくつかの箇所を見てみたいと思います。
第3章21,22節には、主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったということが記されます。そのとき、主イエスが「祈っておられると」、天が開け、聖霊が鳩のような姿で主イエスの上に降った、そして「あなたは私の愛する子、私の心に適う者」との声が天から聞こえた、というように記されております。ルカは、洗礼を受けられた主が祈っておられたときに、聖霊が降り、天からの声をお聞きになったと、そのようにこの場面を描いております。第9章には、いわゆる「山上の変貌」の場面が描かれますが、ここでも、ルカは祈る主イエスのお姿を伝えます。主イエスが「祈っておられるうちに」、そのお姿が光り輝く栄光のお姿に変わった、というように記されております。第3章も第9章も、主イエスとはどのようなお方か、「イエスとは誰か」ということが啓き示される場面を描いています。ルカは、主イエスについての真実が啓き示されたのは、祈りのなかにおいてであったと、そのように描くのです。
そして最後の晩餐の席でのことです。主イエスは、ペトロが三度主イエスを知らないと言ってしまうことを予告されました。そのときに主イエスはペトロに言われました。「しかし私は、信仰がなくならないように、あなたのために祈った。」(22:32)ルカだけが、この場面でペトロのために祈る主イエスを伝えます。そして第23章、十字架の上で、主は苦しい息の中から、ご自分を十字架につけた者たちのために祈られました。「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか分からないのです。」(23:34) そして主の最期の言葉は、天の父に向かう祈りでした。46節「父よ、私の霊を御手に委ねます。」
ルカ福音書は、ここでもここにも、というように、主イエスの祈るお姿を描きます。主イエスは、本当にいつも父なる神に祈っておられた、父なる神を呼び、父なる神との親しい交わりに生きておられたのです。先ほどは、詩編交読で、詩編116編の全部を読み交わしました。この詩編は繰り返し「主を呼ぼう、主の名を呼ぼう」と歌います。苦しみ嘆きの中から、私は主を呼び求める、主を愛する、主を信じると、主を呼んで歌い、祈ります。祈りとは、まず神さまを呼ぶことです。主イエスも、親しく父なる神さまを呼び続ける祈りに生きておられました。父なる神さまとの深く親しい交わりの中で、主イエスの地上の歩みは進められて行ったのです。最期の息を引き取るその時まで、主イエスは祈っておられました。その地上の歩みの始まりから、その終わりのときまで、主イエスは父を呼び続け、そして弟子たちのために、私たちのために祈っておられたのです。私たちの祈りが絶えてしまわないように、私たちの信仰がなくならないように、そして、私たちの罪が赦されるように。私たちのために、最期の最期まで、祈っておられました。主イエスの地上の歩みは、父なる神に向かい、父を呼び続け、私たちのために祈る祈りに貫かれたご生涯だったということを、ルカによる福音書は伝えるのです。
けれども、もしかすると皆さまの中にはこんなふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。「イエスさまは神の御子、神の独り子であられるのだから、神さまのことは何だってよく分かっておられたはずなのに、神さまのお心だってよく分かっておられたはずなのに、どうしてこんなに神さまにお祈りする必要があったのか」と、そんなふうに思われる方もあるかもしれないと思います。実は私も昔そう思ったのです。「イエスさまはいつも祈っておられたんだよ」と、教会で教わりましたとき、「イエスさまは神さまの御子なのだから、お祈りする必要なんてないのではないか」と思いまして、イエスさまが祈っておられたということを、とても意外に思いました。けれども、神の御子であったからこそ、神のみ心を誰よりもよく知るお方だったからこそ、主イエスは、父である神と語らい、父なる神と親しく交わる祈りのときをこのうえなく大切になさったのです。父なる神との親しい交わり・祈りこそ、主イエスのお働きの原動力であったのです。
そして、主イエスは私たちと同じ人間の一人として、この地上を共に歩んでくださいました。私たちが大地を踏みしめて歩くように、主イエスもその御足を土に汚しながらガリラヤの町々をめぐり歩き、病む人々、苦しみ悩み悲しむ人々のもとを訪れて、癒やし、慰め、励まし、平安を告げて歩まれました。癒やしを求め、救いを求めて、みもとに集まってくる人々を深く憐れまれました。主は、私たちすべての者の、苦しみ悩み、痛み悲しみを知ってくださったお方です。だからこそ、祈らないわけにはいかなかったのです。罪にとらわれ、死の恐れに取り囲まれ、悪霊の支配に苦しみ悩む私たちのために。私たちがその苦しみや恐れや捕らわれから解放され、解き放たれて救われるために、主イエスは絶えず祈らないわけにはいかなかった、そして最期の息を引き取るその時まで、私たちのために祈られたのです。
16世紀のスペインに生きたアビラの聖テレジア(1515~1582)というカトリックの聖人の言葉に、こういう言葉があるそうです。「祈りとは、多く考えることにあるのではなくて、多く愛することにある」。聖テレジアのこの短い言葉は、祈りの本質は愛にあるということを教えます。祈りは、神について多く考えることではなくて、神に身も心も向けて神を愛すること、そして、隣人についてあれこれ考えることではなくて、身も心も隣人に向けて隣人を愛すること。祈りとは、そのようなものだと言うのです。聖テレジアのこの言葉が紹介されていたのは、もう亡くなった方ですが、奥村一郎というカトリックの神父さんが書かれたエッセイ集でした。奥村神父は、祈りとは、自己の立場から離れて「他に向かう」ことだとも言います。「どこどこに向かう」と言えば、自分が今いるところを離れ、そこから出て、目的の場所に向かうことを言います。祈りとは、そのように、自己の立場を離れて、神へと、そして他者へと、「向かう」行為だと言うのです。そして、それは「愛する」ということに他ならないと言うのです。
主イエスの祈りは、まさにそのような愛の行為そのものだったのではないかと思わされます。身を投げ出すように神へと向かい、そして身を投げ出すように自らをささげて私たち一人ひとりへと向かう愛の祈り。主イエスの祈りは愛そのものだと思わされます。主イエスが、神に向かって私たちのために祈ってくださる、それは、ご自身の全存在を父なる神に向けてそのみ旨に服従させ、そしてご自身のいのちを注ぎ出して私たちすべての者を愛し抜いてくださった、ということに他なりません。
今朝の御言葉は、イエスが徹夜で祈られたと伝えています。「イエスは祈るために山に行き、夜を徹して神に祈られた。」いつも祈っておられた主イエスのお姿をたどりましても、主が「徹夜で」祈られたと書かれていますのは、実はここだけです。それだけにここでの主イエスの祈りには尋常でない厳粛さ、重々しさがあります。主イエスのご生涯の中で主が徹夜で祈られたのは、このときと、そして主イエスが十字架につけられる前の晩、いわゆるゲツセマネの祈りのとき、この二回だけなのです。ゲツセマネの祈りの記事の中には「夜を徹して」という言葉は出てまいりませんけれど、その祈りは、夜を徹しての寝ずの祈りでありました。ルカは、主イエスのゲツセマネの祈りの様子をこのように伝えます。「天使が天から現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。」(22:43-44) ゲツセマネでの主イエスの祈りは、天使に励まされなければ祈り続けられないほどの苦しい祈りだったというのです。汗が滴り、それは血のように、地面にぽたぽた滴り落ちたというのです。
その夜と同じように、今日のところでも、主イエスは徹夜で祈られました。夜通し祈らねばならないほどの祈りが必要だったのです。ゲツセマネの祈りと同じ厳しい祈りを、ここで主はしなければならなかった。14~16節に名前が挙げられている十二人を選ぶために。「ペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そして、ヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダ」。ペトロに始まりユダで終わる、この十二人を選ぶために、主イエスは徹夜の祈りを必要とされました。主イエスのもとにはすでに大勢の弟子たちが集まっていたようです。大勢の弟子たちの中からこの十二人を選び出し、主は彼らを「使徒」と名付けられました。使徒として任命されました。そのために、主は徹夜になってしまうほどの難しい、厳しい祈りの闘いをしなければなりませんでした。そこに、「後に裏切り者となったイスカリオテのユダ」が含まれたからです。
裏切り者となるユダを選ぶ。それは、主イエスがこのユダに裏切られて殺されることになる、その十字架の死を引き受けるということを意味しました。ユダの罪をご自身の身に負うということを意味しました。罪のない神の御子主イエスが、このユダに代表される全人類の罪、神に逆らい、神に反逆し、神など要らないと神を捨てる、そのすべての罪を負い、罪人たちの身代わりとなって十字架に死ぬ、その道へと確かに歩み始める、その第一歩がこの十二人の選任であったのです。ユダを含む十二人を選ぶための徹夜の祈り、それは、最期の夜にゲツセマネで、十字架の死という苦い杯を決定的に受け取るために祈った、あの血の汗をしたたらせて祈った祈りと、同じ意味を持つ徹夜の祈りでありました。この十二人を選び出すために、主は夜を徹して祈らねばならなかった、ゲツセマネの祈りと同じ、厳しい祈りの闘いを強いられました。
この主イエスの徹夜の祈りは、父なる神への服従と、そしてユダと十一人の弟子たちへの愛を貫かれた、そういう祈りであったと言ってよいのではないかと思います。裏切者はユダだけではありませんでした。十二人の筆頭に名前が挙げられたペトロも主イエスを三度「知らない」と言って主を裏切りました。他の弟子たちも皆、主を見捨てて主から離れてしまいます。しかし、主イエスは、徹夜の祈りの闘いを経て、父なる神への服従を貫き、十二人への愛を貫かれて、この十二人を選び立てたのです。この十二人を最期まで愛し抜く歩みへと、十字架への道を踏み出されたのです。主イエスの祈りは、主イエスの愛は、この裏切り者のユダにまで向かいました。裏切りのユダをも包み込みました。主イエスの徹夜の祈りは、ペトロを包み、そしてユダをも包み込む愛の祈り、赦しの祈り、贖いの祈りであったのです。
主はこの十二人を使徒とされました。「十二人」という数は、偶然の数ではありません。イスラエルの十二部族と同じ十二です。主が「十二人」を選ばれた、それは、主がここに新しいイスラエル十二部族をお立てになったということを意味します。すなわち新しいイスラエル、新しい神の民を、ここに選び立てられた、ということです。そして彼らを「使徒」と名付けられた。それは、この十二人において、教会の礎、土台を据えられた、ということです。主イエスはここに、新しいイスラエル・新しい神の民・教会の礎を据えられたのです。
この十二人、その面々は、優秀な精鋭たちというのではありません。裏切る者がおり、主を捨てる者たちがおります。またトマスのような疑い深い者がおり、熱心党という過激派のような者もおりました。名前だけしか分からない、名前さえ確かかどうか分からない、言ってみれば、「とるに足りない」というような人もおります。この十二人は、そういう者たちの集まりです。主イエスは、徹夜の祈りの果てに、そのような者たちによって新しい神の民の土台を据えられたのです。ペトロも、そしてユダをも、主は排除なさいませんでした。主のもとには大勢の弟子たちが集まっていたのですから、その中には、もっと誠実で忠実で、強い信仰と豊かな知識を持つ優れた人たちもいたでしょう。しかし主はそのような人たちではなく、てんでばらばらな、ある意味どうしようもないような十二人、罪人の頭たちの集団のようなこの十二人をお選びになり、彼らにおいて、新しいイスラエル、新しい神の民・教会の礎、土台を据えられたのです。この十二人をご自分の使徒として、ご自分の手足として用いていく、全世界に遣わしていく、その決意をなさったのです。裏切り者となるユダは欠けてしまいます。悲惨な死を遂げることになります。それでも、そのユダをも含む十二人を、ここで使徒とされました。教会の礎とされました。主は、この十二人のために十字架に命を捨てる、そのようにしてこの十二人を愛し抜く、そのご決意、父なる神のみ旨に従い抜く祈りとご決意をもって、この十二人をお選びになったのです。そのために、徹夜で祈らなければならなかったのです。ルカ福音書は、教会とは、主イエスの血の汗を滴らせる徹夜の祈りに祈られて、主イエスの徹夜の祈りのうちに、その礎を据えられたのだと、そう伝えるのです。
ルカは後に、この福音書の第二巻となる使徒言行録を書き著します。その第20章で、ここに据えられた十二使徒から始まった新しいイスラエル、新しい神の民である教会のことをこう呼びます。「神が御子の血によって御自分のものとなさった神の教会」(使徒20:19,新共同訳)。新しい神の民、新しいイスラエルである教会の礎、その土台には、主イエス・キリストの血が注がれているのです。神の小羊として十字架の上に屠られた、十字架の上に殺された、御子主イエスの血が、教会の礎である十二人に、注がれたのです。
裏切りの代償として悲惨な死を遂げたユダにも、犠牲の小羊の血は注がれたと言ってよいと思います。主を裏切ったユダは自殺します。その死がどんなに悲惨であったかを、ルカは使徒言行録の冒頭に記しています。しかし、主を売り渡した報酬で得た土地に真っ逆さまに落ちたユダ、陰府の暗闇の底に落ちて行ったかの如くのユダを、陰府にまで降り給うた十字架の主は、その暗闇の底で受けとめられたのではないでしょうか。主イエスの徹夜の祈りは、陰府の暗闇にまで届く祈りであったのではないでしょうか。愛の祈り、赦しの祈り、贖いの祈りであったのです。
私たちは今、新しいイスラエル、新しい神の民である教会に共に集められ、生かされています。ペトロに、そしてユダにまで向かい、ユダをも包み込んだ主イエスの徹夜の祈り、愛の祈りが、私たちにまで及ばないことがあるでしょうか。私たちが今ここにこうして教会に集められているのは、私たちのための主イエスの徹夜の祈りがあったからです。私たちのためにも、私たち一人ひとりのためにも、主イエスは夜を徹して祈り、私たちをご自分の血によって、神の教会のひとえだとして贖いとってくださったのです。
私たちも、十二人の使徒たち同様、てんでばらばらな者たちです。信仰弱く、すぐにつぶやき、主から離れてしまいそうになる、誘惑に負けてしまう、そういう者たちです。けれども、こういう私たちを、ご自身の血を注いで贖いとった神の教会の一員、一部分とするために、主は、徹夜で祈られたのです。そして今も天にあって祈っていてくださるのです。まどろむことなく眠ることなく、寝ずの番をするようにして祈っていてくださる。私たちが迷い出て行かないように。私たちの信仰がなくならないように、祈っていてくださる。私たちに向かう愛の祈りを、父なる神にささげていてくださるのです。
主イエスは私たちのために、今も天にあって祈っていてくださいます。私たちがまだ出会っていない、将来の教会の仲間たちのためにも、主は祈っておられます。そして、教会から離れて行った人たちのためにも主は祈っておられる。徹夜の祈りをしておられるのです。私たちも祈りたいと思います。主イエスの祈りに合わせて祈りたい。父なる神に身を向けつつ、私たちの隣り人に向かう愛の祈りを祈りたいと願うものです。