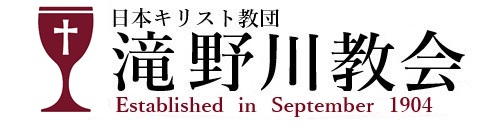2025年6月8日 聖霊降臨主日礼拝説教「神の偉大な業を語る」 東野尚志牧師
ヨエル書 第 3 章 1~5 節
使徒言行録 第 2 章 1~13 節
今日は、聖霊降臨記念主日です。今から二千年前、復活された主イエスの約束を信じて、エルサレムに留まり、祈りつつ待っていた弟子たちの上に、天から聖霊が降りました。聖霊に満たされた弟子たちは、力強く福音を宣べ伝え始めたのです。ペンテコステとも呼ばれます。ペンテコステ礼拝です。二千年前のペンテコステの日、いったい何が起こったのか、その出来事を描いているのが、先ほど朗読した使徒言行録第 2 章の記事です。長く教会に来ておられる方たちは、何度も読み、また聞いてきた話であるはずです。今日、この礼拝に先立って行われた教会学校の礼拝においても、同じ使徒言行録第 2 章の物語が読まれました。教会学校で育った人たちは、それこそ、子どもの頃から聞き続けてきた話ということになります。私たちはそれを、毎年毎年、ただ二千年前の昔話として読むのではありません。そうではなくて、今、私たちの上に起こる出来事として味わいます。聖霊が降るとき、聖書に記された二千年前の出来事が、私たちの上にも起こるのです。主イエス・キリストが、二千年前の過去の人ではなくて、今日、私たちと共にいてくださるお方として、私たちに現れてくださるのです。
使徒言行録第 2 章の記事は、「五旬祭の日が来て」と始まります。ここで、「五旬祭」と訳されている聖書のもとの言葉が、「ペンテーコステー」というギリシア語です。五十番目、五十日目という意味の言葉です。それを日本語に訳した「五旬祭」というのも、「五十日目のお祭り」という意味を持っています。一か月を三つに分けて、上旬、中旬、下旬、と呼ぶように、「旬」という言葉は 10 日間を意味するのです。「五旬祭」は「五十日祭」と言ってもよいわけです。問題は、どこから数えて、何から数えて五十日目なのかということになります。
私たちはすぐに、主イエスが復活された週の初めの日から七週間を経て五十日目、というふうに考えるかもしれません。けれども、「五旬祭」というのは、主イエスが地上にお生まれになる前から、ユダヤ人の間で大切に祝われていたユダヤ教のお祭りでした。ユダヤ人にとって、最も大切なお祭りであった「過越祭」から数
えて 50 日目のお祭りだったのです。
二千年前の新約聖書の時代から、さらに千二百年ほど遡ることになります。主なる神は、エジプトで奴隷として苦しめられていたイスラエルの民を憐れんで、奴隷の軛から解放するためにモーセを召し出して、お遣わしになりました。このあたりは、今ちょうど、木曜日の聖書研究・祈祷会で丁寧に読んでいるところです。エジプトの王ファラオは、心をかたくなにして、イスラエルを解放しようとしません。それで、エジプト中にさまざまな災いが下されることになります。その最後、10 番目の災いとして下されたのが、「初子撃ち」でした。人間と動物を問わず、エジプト中で最初に生まれた初子、人間であれば、長男がすべて撃たれて死ぬ、という恐るべき災いです。けれども、その裁きの夜、予めモーセを通して神から告げられた命令に従って、小羊を屠り、その血を入口の柱と鴨居に塗ってしるしを付けていたユダヤ人の家は、死をもたらす滅びの天使が過ぎ越していったというのです。この救いの出来事を記念して、イスラエルでは毎年「過越祭」を祝うことが定められました。現代の暦に移すと、3 月の終わりから 4 月の終わりにかけての時期ということになります。
この「過越祭」から七週を経て祝われたのが「五旬祭」でした。元来は、小麦の収穫を祝う春の祭りであったようです。「刈り入れの祭り」と呼ばれていました。厳しい荒れ野の旅を経て、約束の地カナンに定住するようになった後、小麦の最初の収穫である初穂を献げるお祭りとして始まったのです。しかし後には、そこに新たな意味づけがなされました。エジプトを脱出して、海の中に開かれた道を通って追っ手のエジプト軍から逃れ、シナイ半島の荒れ野を進んで行ったユダヤの民は、シナイ山において、神から律法を与えられます。この律法授与を記念する日として祝われるようになったといわれます。神とイスラエルの民はシナイ山で契約を結んで、神はイスラエルの神となられ、イスラエルは神の民となりました。神の民となったイスラエルに、契2約のしるしとして与えられたのが、十の戒めからなる「十戒」です。ここから、神の掟によって生きる神の民イスラエルが生まれた、と言ってよいのです。神の民イスラエルの新たな誕生日として祝われた、それが「五旬祭」の祝いとなりました。この日は、「過越祭」と並んで、大切な巡礼の日として定められました。ユダヤ全土からはもちろん、周辺の国々に離散していたユダヤ人たちも、エルサレムの都に集まって、祭りに参加したのです。普段はヘブライ語を用いずに、離散した国々の言葉を話していたユダヤ人たちが大勢、エルサレムの都に集まっていたのです。
その年の過越祭は特別でした。エルサレムが多くの巡礼者であふれかえり、過越祭に備える中で、主イエス・キリストが捕らえられ、裁かれ、十字架にかけられて殺されたからです。ヨハネの福音書によれば、ちょうど、過越の小羊が屠られる時間に、主イエスは十字架にかけられ殺されたのです。主イエス・キリストは、ご自身を過越の犠牲として屠られた小羊になぞらえるように、私たちの罪が赦されるための贖いの供え物として、十字架において肉を裂き、血を注いでくださいました。御子イエスの血が私たちの罪を洗い清め、私たちを滅びから救い出してくださるのです。十字架の上で死なれた主イエスは、墓に葬られ、3 日目に死人の中からよみがえらされました。使徒言行録の第 1 章によれば、復活された主は 40 日にわたって、たびたび弟子たちに現れて、神の国について教えられたといいます。そして、40 日目に、弟子たちの見ている前で天に昇られ、それから 10 日の後、復活のときから数えて 50 日目に、約束の聖霊を弟子たちに送ってくださったのです。イスラエルの民がエジプトの奴隷生活から解放されたことを記念する「過越祭」は、主イエス・キリストの十字架と復活による罪と死の支配からの解放を記念する復活祭、イースターの祝いによって塗り替えられました。それと同じように、五十日目、シナイ契約に基づいてイスラエルに律法が与えられ、神の民イスラエルが誕生したことを祝う「五旬祭」は、主の弟子たちに約束の聖霊が与えられ、新しい神の民としての教会が誕生したことを祝う聖霊降臨祭、ペンテコステの祝いによって塗り替えられたのです。新たな意味づけを与えられて、上書きされたと言ってよいかもしれません。救いの枠組みが新しくされたのです。
その日、すなわち、主イエス・キリストが復活されてから七週を経た、五旬祭の日、約束の聖霊が弟子たちの上に降りました。聖書は、その日の出来事を、劇的なしるしを用いて描いています。まず初めは、激しい風の音です。「突然、激しい風が吹いて来るような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた」(2節)。聖霊はしばしば、風というしるしによって描かれます。主イエスもかつて、霊の働きについて語りながら、「風は思いのままに吹く」と言われました(ヨハネ 3 章 8 節)。聖霊は、あたかも風のように、何ものにも束縛されず自由に働かれます。そのような風が激しく吹いてくる音が、天から聞こえたのです。続いて、「炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった」といいます(3 節)。炎は汚れを焼き尽くす神の力です。ここで「舌」と訳されているのは、「言葉」と訳すこともできます。聖霊は、言葉の賜物をともなって臨んだことを暗示しているのかもしれません。
ここで大事なのは、その炎のような舌が、分かれ分かれに現れて、一人ひとりの上にとどまった、ということです。16 世紀にギリシアで生まれてスペインで活躍したエル・グレコという画家がいます。このエル・グレコが描いた、有名な聖霊降臨の絵を思い浮かべると良いかもしれません。弟子たちが同じ場所に集まっていました。中央の人物は、手を合わせ祈りの姿勢をとっています。その一人ひとりの頭に、小さな炎のような舌がともっています。聖霊は、小さな炎のように、一人ひとりの上に分かれてとどまったのです。決して、一人ひとりの存在が塗りつぶされて一つになるというのではありません。一つの群れの中にいる一人ひとりに、賜物が分け与えられるのです。聖霊によって生かされる教会のあり方が、よく現されているのではないでしょうか。私たちも、共に一つの場所に集まり、心を一つにして祈りを合わせます。この群れの中に聖霊が働いてくださるとき、一人ひとりが、それぞれの賜物に応じて生かされ、用いられていくのです。
さていよいよ、聖霊降臨の出来事のクライマックスに差し掛かります。「すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他国の言葉で話しだした」(4 節)。一体、私たちは、この出来事をどのように受けとめればよいのでしょうか。聖霊を受けたとき、使徒たちは急に外国語が話せるようになったのでしょうか。そうだとしたら、うらやましい限りです。「他国の言葉」というのは、直訳すれば「別の舌」と書かれています。これを、「他国の言葉」と訳したのは、恐らく、この後の 5 節以下の記事を踏まえて意訳したということだと思います。
5 節以下を見ると、ちょうどイスラエルの三大祭りの一つで、巡礼の時期にあたっていたために、さまざまな地域に離散して暮らしていたユダヤ人たちが、エルサレムに集まってきていたことが分かります。国家の滅亡と捕囚の経験は、民族離散の大きなきっかけになったと考えられます。捕囚から解放されて、エルサレムに戻ることが許されたといっても、みんながみんな元の土地に帰ってきたわけではありませんでした。そのまま外国に留まる者も多かったようです。もう何世代にもわたって、離散した先で生活をしていたユダヤ人たちがいたのです。生まれたときから外国語を用いてきた人たちです。中には商売に没頭して信仰を捨ててしまった人たちもいたと思われます。けれども、信仰深いユダヤ人たちは、たとえ外国で生活してはいても、祭りのたびに、巡礼者として、エルサレムの都に集まって来ました。さまざまな他国の言葉を用いる巡礼者たちは、使徒たちの口を通して、自分たちの国の言葉が語られているのを聞いてびっくりしたのです。
しかし、使徒たちが語った「他国の言葉」について、別の解釈をする人たちもいます。天から聖霊が降り、聖霊に満たされた使徒たちが語りだしたのは、いわゆる「異言」であったというのです。確かに原語では「別の舌」と書いてありますから、「異言」と訳すこともできます。そして、特に、水による洗礼と聖霊による洗礼をはっきりと分けて考える聖霊派の人たちは、異言を語るということを、聖霊を受けたことのしるしとして重んじています。「異言」とは何か、ということについてここで詳しく語ることはできませんけれども、パウロによれば、人間が普通に聞いて理解できる言葉ではなくて、霊的な恍惚状態にある者の口から発せられる意味不明の言葉です。それは人に向かって語る言葉ではなくて、神に向かって語る言葉だとも言われています。
パウロ自身、異言を語ることができたといいます。霊の賜物として否定する必要はありません。しかし、そのパウロがまた、人が聞いても理解できない「異言」を語るよりも、聞いて分かる「預言」の言葉によって神の御業を宣べ伝えることの方が大事だと教えました。異言は語る本人の徳を建てるだけですが、預言は教会を建て上げるというのです。歴史的にみれば、聖霊降臨のときに弟子たちが語ったのは、異言であったのかもしれません。弟子たちが語る言葉を聞いて、新しいぶどう酒に酔っているのだ、と言ってあざけった人たちもいたとありますから、一種、恍惚とした状態であったのかもしれません。けれども、使徒言行録を記したルカは、このペンテコステの日に起こった出来事を、主イエスの十字架と復活による救いが、全世界に宣べ伝えられていく、世界伝道の始まりとして、伝道する教会の誕生として描いたのです。
私たちは、ペンテコステの日に起こった出来事の本質を、しっかりと捕らえなければならないと思います。聖霊を受けたとき、いろいろな外国の言葉が自由に話せるようになったということを言いたいのではありません。言葉が違っても心を通じ合わせることができる、異文化コミュニケーションの道が拓かれた、ということを言いたいのでもありません。その日、起こったことの本質は一つです。それは、聖霊に満たされた使徒たちが、聞いている者たちに通じる言葉で、「神の偉大な業」を語り始めたということです。使徒たちの語る言葉が、聞いている者たちの心に届いたのです。聞いて分かったのです。その日、使徒たちの語る言葉を聞いた人たちは、驚いて言いました。「見ろ、話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうして、それぞれが生まれ故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、リビアのキレネ側の地方に住む者もいる。また、滞在中のローマ人、ユダヤ人や改宗者、クレタ人やアラビア人もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な業を語っているのを聞こうとは」(7~11 節)。
大事なことは、ただ言葉が通じたということではありません。「神の偉大な業」を語る言葉が通じたのです。「神の偉大な業」とは何でしょうか。それは、主イエス・キリストにおいて成し遂げられた救いの御業です。神は、大切な独り子であるイエス・キリストを私たちの救い主としてこの世に遣わしてくださいました。主イエスは私たちと同じ人間の一人としてこの地上を歩まれ、ついには、私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。父なる神は、主イエスの十字架の死を、私たちの罪の赦しのための贖いの死として受け入れてくださり、私たちの罪を赦して神の子としてくださいました。そして、罪と死の力を打ち破って主イエスを死者の中から復活させてくださり、主イエスによる罪の赦しの恵みを受ける私たちにも、死に打ち勝つ復活の命、永遠の命を約束してくださったのです。主イエス・キリストにおいて成し遂げられた私たちのための救い、神の偉大な業を、聖霊を受けた使徒たちは、力強く語り始めました。それは、天に上げられる前、主イエスが与えてくださった約束の実現です。主は言われました。「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる」(1 章 8 節)。聖霊は、私たちを、主イエスの証人として立たせてくださいます。主イエスの救いを語る者としてくださいます。私たちに語る言葉を与えてくださるのです。
聖霊は、私たちを、神の偉大な業を語る者としてくださいます。しかし、それだけではありません。聖霊は、その語られた言葉を聞く者たちに、それが訳の分からない異言ではなく、人間の作り話やむなしい話でもなくて、神の偉大な業を告げる言葉であることを分からせてくださるのです。聖霊が働いてくださらなければ、たとえどんなに力強く福音が語られたとしても、それを信じて受け入れることはできません。事実、最初のペンテコステの日にも、使徒たちが神の偉大な業を語るのを聞いても、訳が分からず、あざける者たちがいたのです。私たちの耳もまた、罪に惑わされることがあります。十字架の言葉は、人の知恵に逆らうと言われるのです。
私たちは、人に通じる話をしようとして、人々の好みに合わせて福音を水増しして薄めてしまう誘惑があります。人々の気に入ることだけを語っているならば、教会は存在の意味を無くすでしょう。自分の頭で理解できることだけを受け入れて、福音のつまみ食いをしていたのでは、救いを受けることはできません。しかし、私たちが語り、また聞くのは、救いの理屈ではなくて、救いの出来事です。神は、その独り子をお与えになったほどに、私たちを愛してくださいました。私たちは、十字架において現わされた神の愛を仰ぐのです。私たちが語り、また聞くのは、神の愛そのものであり、愛の言葉そのものであるイエス・キリストです。この礼拝において、生けるキリストご自身が私たち一人ひとりと親しく出会ってくださることを信じて、キリストの言葉を味わう。そのとき聖霊は、今、ここに、救い主が生きて働いておられることを、私たちに証ししてくださるのです。
イエス・キリストは語られる御言葉を通して、霊において、今私たちと共におられます。そのお姿を目で見ることはできません。しかし、私たちのために、目に見える神の言葉が備えられました。私たちは、この日、聖霊によって導かれながら、主が備えてくださった食卓に連なります。パンとぶどう液。これは、信じて洗礼を受けた者にとっては、誰にでも通じる共通の言葉です。ある意味では、語られる言葉よりもさらに雄弁に、恵みを伝える言葉です。まだ洗礼を受けていない人たちにとっては、通じない言葉であるかもしれません。けれども、すべての人にペンテコステは起こります。聖霊によって証しされる真理の言葉に導かれ、自分の口で信仰を言い表して洗礼を受けるとき、主の聖餐として備えられたパンと杯が、確かに通じる救いの言葉になるのです。すべての人にその日が備えられていることを信じ、さらに多くの人たちがこの救いに招かれることを祈り願いながら、私たちも、聖霊が語らせるままに、私たちの全存在を通して、神の偉大な業を語りつづけていきたいと願います。