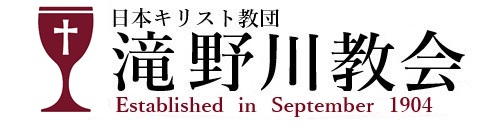2025年4月6日 受難節第五主日礼拝説教「涙が拭われるとき」 東野尚志牧師
イザヤ書 第25章6~10節
ヨハネによる福音書 第20章11~18節
新しい年度の歩みが始まりました。希望に燃えて、新たな学びや務めを始めた方もあると思います。しかしまた、不安や恐れの中で、あるいは悲しみや痛みを抱えながら、新しい年度を迎えた方もあると思います。世界に目を向ければ、今も、戦地にあって命の危機にさらされている人たちがあり、大きな地震に見舞われた地においては、犠牲者の数が増え続けています。自然災害は、思いがけない時に、容赦なく襲いかかってきます。日本もまた、南海トラフの地震は今後30年以内に80パーセントの確率で発生すると言われています。確率というのは、あまり役に立ちません。30年以内ということは、今日かもしれないし、明日かもしれないということです。
戦争や災害の中で、最も理不尽でやりきれないことは、突然、命が奪われてしまうことです。家や財産の被害も深刻ですけれども、命があれば、何とかやり直すことができます。どんなに厳しい状況であっても、まだ立ち直る望みはあります。けれども、命が奪われてしまったら、もうやり直すことはできません。この世界においては、愛する者の死という現実を動かすことはできません。たとえそれが、病のゆえに避けられないと覚悟していたとしても、死によって、地上の交わりが断ち切られることは、大きな痛みと喪失をもたらします。家族や親しい者にとっては、身を引き裂かれるような痛みをもたらすのです。
「マリアは墓の外に立って泣いていた」。今日、私たちに与えられた聖書の箇所は、そのように始まります。その日は、週の初めの日でした。私たちの暦で言えば、日曜日です。二日前の金曜日、主イエスは十字架にかけられ、十字架の上で息を引き取られました。そして、その日のうちに、アリマタヤのヨセフが用意した新しい墓の中に葬られた。ガリラヤからずっと主イエスに付き従ってきたマリアは、主が葬られるのを見届けた上で、掟に従って安息日を休んだのです。そして、安息日が終わって、夜が明けるのが待ち切れないように、まだ暗い中を墓へ急ぎました。横穴式の墓の入り口は、大きな石で閉じられていましたから、中に入ることはできません。それでも、主イエスが葬られた墓を訪ね、主イエスの側にいたいと願ったのです。ルカの福音書によれば、マリアは主イエスによって七つの悪霊を追い出していただいたと言います。主イエスによって解放され、救われたのです。その時以来、マリアは心から主イエスをお慕いして、喜んで一行のお世話をしてきたのだと思います。主イエスを深く尊敬し、愛していたのです。まだ薄暗い中、主が葬られた墓へと急ぎました。
ところが、マリアが墓に着くと、墓の入り口をふさいでいた石は取り除けられていました。しかも、墓の中には、主イエスの遺体が見当たりません。墓は空っぽになっていたのです。マリアは急いで引き返して、シモン・ペトロと主イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ出かけて、事の次第を告げました。ヨハネによる福音書第20章の2節に、その時のマリアの言葉が記されています。マリアは言いました。「誰かが主を墓から取り去りました。どこに置いたのか、分かりません」。主イエスの遺体は墓の中に置かれているはずでした。死んだ体が勝手に動くはずがありません。それでマリアは、誰かが主イエスのお体を墓の中から運び去って、どこかに置いたのだと考えました。あるべき場所から動かされて、どこに置かれているのか分からない、そう思ったのです。
マリアから、墓が空であったと知らされたペトロともう一人の弟子は、急いで墓に駆けつけました。墓の中を覗くと、主イエスの遺体を包んでいた亜麻布が、置いてあるのが見えました。しかも、主イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布から離れた別のところに丸めて置いてありました。誰かが、主イエスの遺体を持ち去ったということであるならば、そんな面倒くさいことはしないはずです。布で巻かれたままで運び去ったでしょう。墓の中に残された亜麻布は何を意味しているのか、死の力に捕らえられている者たちには、まだその意味が本当には分かりませんでした。
ペトロともう一人の弟子が家に帰ってしまった後も、マリアは墓の外に立ち続けていました。男性の弟子たちのように、簡単にはあきらめ切れません。なおも墓から立ち去りがたい思いで、泣き続けていたのです。マリアにとって、主イエスの存在がどれほど大切であったかということを物語っています。また同時に、大切な主イエスのために、何もできない自分の無力さを嘆き悲しんでいるのです。私たちも、この涙の意味を知っているはずです。人生には、泣く以外にどうすることもできないことがあります。愛する者の死に直面したとき、私たちもまた、涙をこぼすほかない悲しみと無力さを味わうのです。愛する者を失う悲しみの涙。しかも、死に向かう愛する者のために、何もできない無力さを思い知るとき、一体、泣くこと以外に何ができるのでしょうか。
マリアが泣きながら、身をかがめて墓の中をのぞくと、白い衣を着た二人の天使の姿が見えた、と言います。「一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのが見えた」と言うのです。頭の方、というのは、主イエスの頭を包んでいた覆いが置いてあった場所でしょう。足の方、というのは、主のお体に巻いてあった亜麻布が置いてあった場所だと思われます。二人の天使たちはマリアに言いました。「女よ、なぜ泣いているのか」。天使たちには、墓の中に置かれていた主イエスのお体が無くなっていることも、そのためにマリアが泣いていることも、よく分かっていたはずです。それなのにどうして「なぜ泣いているのか」と尋ねたのでしょうか。
天使の問いに対して、マリアは、先ほどペトロともう一人の弟子に告げたのと同じように答えました。「誰かが私の主を取り去りました。どこに置いたのか、分かりません」。こう言いながら、マリアは後ろに人の気配を感じたのだと思います。後ろを振り向きました。すると、そこに主イエスが立っておられるのが見えたと言います。ところが、マリアにはそれが主イエスだとは分からなかったというのです。振り向いて、主イエスのお姿が目に入ったはずなのに、どうして、あれほどに愛し、慕っていた主イエスのことが分からなかったのでしょうか。復活された主のお姿は、少し前とは違っていたのかもしれません。肉の体がそのまま生き返ったというのとは違うからです。あるいは、マリアの悲しみがあまりにも深くて、目が閉ざされていたということかもしれません。
なおも悲しみを深くしているマリアに、主イエスは背後から語りかけられました。「女よ、なぜ泣いているのか。誰を捜しているのか」。先ほどの天使の問いと同じです。主イエスもまた、「なぜ泣いているのか」とお尋ねになるのです。マリアは、主イエスだとは気づかず、園の番人だと思い違いをして言いました。「あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか、どうぞ、おっしゃってください。私が、あの方を引き取ります」。これで三度目です。マリアは一貫して、主イエスの体がどこに置かれたのか、どこに置いたのか、ということを問題にしているのです。
このやり取りを読みながら、この会話の中には大きなずれがあるということに気づきます。確かに、天使も、また主イエスも、「なぜ泣いているのか」と尋ねました。けれども、マリアが泣いている理由は既によく分かっているはずです。そうだとしたら、ただ泣いている理由を尋ねているのではなくて、むしろ、その意味を問うているのです。つまり、あなたはもう、泣いている必要はない、と告げておられるのです。それは、悲しんでいるマリアに対する優しい思いやりの言葉であり、また同時にマリアを激しく揺さぶる言葉なのです。
かつてマリアは、主イエスと出会いました。主イエスによって悪霊の支配としか言いようのない惨めな生活から解放されたことを喜び、その時以来、感謝をもって、主イエスにつき従ってきました。主イエスを心から尊敬し、また愛しています。そして、なおも主イエスを求め続け、主イエスを捜しているのです。けれども、マリアが今、墓の前に立って求めているのは、主イエスの命ではなくて、その死んだ体でした。マリアは、主イエスの体が取り去られて、どこかに「置かれている」と思っています。そして、それがどこかということが分かれば、自分で「引き取る」というのです。つまりマリアは、主イエスを、自分で取り扱うことのできる「もの」として考えていました。確かに、死体であれば、既に、ものです。しかし、その意識に縛られていたために、復活という出来事が受け止められずにいるのです。
マリアが、その死に捕らわれた思いから解き放たれて、主イエスの復活を受け止めるためには、もう一度、きちんと完全に「振り向く」ことが必要です。マリアは、一所懸命に墓の中を見つめていました。しかし、そこには主はおられない。主は正反対の方向、マリアの背後にお立ちになり、マリアが振り向くことを求めておられるのです。死の中を覗きこむのではなくて、復活者を仰ぎ見るように、死から命へ、絶望の涙の中から喜びの涙へと、主はマリアを招いておられます。「なぜ泣いているのか」。この呼びかけは、マリアの思いとまなざしの向きを変えさせるための呼びかけなのです。
マリアは、死の現実は動かないと思い込んでいました。どこまでも、主イエスの死んだ体を求めていました。しかし、主は死人の中にはおられない、墓の中にはおられない。主イエスは死人の中からよみがえって、生きて現臨されるお方として、マリアの背後にお立ちになったのです。主イエスは、背後から呼びかけられました。「マリア」。マリアは驚いて、主に向き直ります。そして、「ラボニ」と言いました。それは、当時、日常的に使われていた言葉で「先生」という意味の言葉です。もっと丁寧に言えば、「私の先生」という意味です。「女よ」と呼ばれたときには気がつきませんでした。しかし、「マリア」、自分の名を呼ばれたとき、初めて気づいたのです。恐らく、それまでに何度も繰り返されたやり取りであったに違いありません。「マリア」―「ラボニ」。生きた人格同士の交わりです。
主イエスは、死んだものとしてではなくて、よみがえった方、生きている方として、マリアの名を呼んでくださいます。だから、もう泣かなくてもよいのです。涙が拭われて笑顔が戻ります。もちろん、主イエスは、マリアの気づいていないときに、既にマリアと共におられました。私たちの方で気づいていないときに、愛する者の死に打ちのめされて、悲しみの涙に沈んでいるときに、既に主イエスは、死の力に勝利された復活者として、私たちと共におられるのです。そして私たちが気づかないときに、私たちを背後から支えていてくださいます。そして、死に捕らわれ続けるのではなく、復活の望みに向かって顔を上げるようにと、私たちの名を呼んでくださいます。私たちを振り向かせてくださるのです。
マリアは、主イエスから名を呼ばれ、振り向いて主イエスのお姿を見ました。信じがたい思いで、しかし、すぐに喜がにあふれてきたに違いありません。復活という出来事は理解できなくても、復活者にお会いしたなら、受け入れるしかありません。よみがえられた主が、マリアに現れてくださり、マリアの名を呼んでくださったのです。これで、前と同じように、いつも主イエスと一緒にいられると思ったのでしょう。もう二度と、主イエスと離れたくない。そんな思いで、主に近づいてすがりつこうとしたのかもしれません。しかし、主はマリアに言われました。「私に触れてはいけない。まだ父のもとへ上っていないのだから」。よみがえられた主イエスは、父なる神のもとに上られるのです。それをとどめるかのように、目に見える主のお姿にすがりついていてはいけないのです。主イエスのよみがえりは、単に、死んだ人が息を吹き返して生き返ったということではありません。復活された主イエスとの関わりは、それまでとは違ったものになるのです。主は天に昇られ、父なる神の右の座に着かれます。そして、御父のもとから、真理の霊であり、助け主、弁護者である聖霊を送ってくださいます。そして、この目に見えない霊において、主はいつも、私たちと共にいてくださるのです。
復活の物語を読むと、そこには、否定や、転換といった要素がたくさん含まれています。私たちは、地上の論理の延長線上で、自分たちの願いがそのまま実現するようにしてよみがえられた主イエスと出会うことはできない、ということを示しているのだと思います。私たちの求めや願いは、死という厳しい現実によって阻まれ、覆されてしまいます。地上のつながりは断ち切られてしまいます。死は確かに、別れであり、断絶です。死という現実を見つめている限り、そこには絶望しかありません。けれども、私たちが向きを変えて、背後から呼びかけてくださる主に向き直るなら、よみがえられた主と出会うことができるのです。これまでの生き方にそのまましがみつくようにして、そのままで復活の命にあずかることはできません。しかしまさに、この死という大いなる否定の力を通して、復活の望みが確かなものとされるのです。私たちは、主イエスの死に結び合わせられて、罪に支配された自分自身に死ぬことができるからです。そして、キリストに結ばれて、キリストと共に死んだのなら、キリストの復活に結び合わされて、新しい命の交わりの中に生きるものとされるのです。
よみがえられた主はマリアに、ご自身の言葉を託されました。「私のきょうだいたちのところへ行って、こう言いなさい。『私の父であり、あなたがたの父である方、また、私の神であり、あなたがたの神である方のもとに私は上る』と」。主イエスは、ご自分の弟子たちのことを「私のきょうだいたち」と呼ばれます。ご自身の死と復活を通して、弟子たちとの関係、私たちとの関係を新しく結び直してくださいます。神の家族としてくださるのです。主は言われます。「私の父であり、あなたがたの父である方、また、私の神であり、あなたがたの神である方のもとに私は上る」。「私の父であり、あなたがたの父である方」。「私の神であり、あなたがたの神である方」。何という慰めに満ちた言葉でしょうか。私たちは、信仰を言い表し洗礼を受けることによって、主イエスとひとつに結び合わされ、主イエスの兄弟姉妹とされます。その驚くべき恵みを私たちに改めて言い聞かせるかのように、主はご自分の父を、私たちの父である方として示してくださいます。ご自分の神を、私たちの神である方として仰がせてくださるのです。そして、私たちを神の家族として、死によっても断ち切られることのない復活の命の絆によって、結び合わせてくださるのです。
天に昇られ、父なる神の右の座に着かれたキリストは、今、私たちの目で見、手で触れることはできません。終わりの日、主が再びこの地上に来てくださるときまで、主のお体は天にあるからです。それゆえ、今私たちが、目で見えるお方としてキリストにお会いすることはできません。キリストに触れることはできません。しかし、それでよいのです。死の力に勝利されたキリストは、今も生きておられます。そして、キリストの十字架の贖いと復活の勝利が正しく宣べ伝えられるところ、主が定められたように、パンが裂かれ、杯が分けられるところに、主は確かに、霊において共にいてくださるのです。
この後、私たちは、主の聖餐にあずかります。信仰を言い表し、洗礼を受けた者たちだけがあずかることのできる恵みの食卓です。洗礼は、主イエス・キリストの死に結び合わされて、古い罪の自分に死に、主の復活に合わせられて、新しい命に生きる恵みです。この恵みの中に立つとき、まさしく、主の十字架の死と復活が、二千年前の過去の出来事であるだけではなくて、今、私たちを捕え、私たちを生かす救いの出来事であることを味わいます。今、聖霊なる神が働いてくださって、二千年前の十字架と復活が、この私のための救いの出来事となるとき、死は無力なものとされ、すべての涙が拭われます。終わりの日の復活の望みの中に生かされることになるのです。
地上のあらゆるものが古びていきます。形あるものはやがてみな朽ちていきます。私たちの肉体も本当にもろいものです。愛する者を見送る悲しみと寂しさを味わった人たちも、やがては、自分自身の死の時を迎えることになります。だれも死を避けて通ることはできません。この死だけを見つめているならば、何の望みもないでしょう。けれども、死は、決して、最後の言葉ではありません。死の力をうち破ってよみがえられた主は、今、霊において私たちの間に共にいてくださいます。そして、私たちの名を呼んでくださるのです。死に向かう定めの中から、復活の命の祝福へと、名を呼んで、呼び出してくださいます。死によっても、愛がむなしくならないことを、信じさせてくださいます。そして、終わりの日には、この私たちをも、決して朽ちることなく、死ぬこともない、主と同じ栄光の体によみがえらせてくださるのです。
主が私たちの名を親しく呼んで、「さあ、起きなさい、よみがえりの朝だよ」と告げてくださる日が来ます。主にあって眠りについた者たちが起き上がり、主の御前で再会するときです。主のご復活を祝う喜びの中で、主が差し出してくださる祝福をしっかりと受けとめ、死に勝つ慰めと望みを新たにしたいと思います。