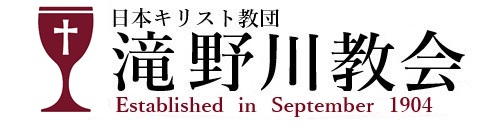2025年3月9日 受難節第一主日礼拝説教「その証しは真実」 東野尚志牧師
詩編 第34編16~23節
ヨハネによる福音書 第19章31~37節
今日、私たちは、ヨハネによる福音書の御言葉を通して、十字架にかけられた主イエスのお姿を仰ぎ見ています。ローマの総督ポンティオ・ピラトの法廷において、十字架刑の判決を受けた主イエスは、その日のうちに、総督の官邸から処刑場があるゴルゴタの丘まで、引き立てられて行きました。前の晩から眠ることも許されず、飲まず食わずで裁きの場に立たせられて、しかも、鞭で打たれたお体は、歩くのもやっとという状態であったと思われます。しかし、ヨハネは、主イエスが自ら十字架を背負って、ゴルゴタの丘へ向かって行かれた、と記していました。そして、処刑場に着くと、十字架の木に手足を釘で打ち付けられ、磔(はりつけ)にされました。他に二人の犯罪人も一緒に十字架につけられたのです。
「十字架上の七つの言葉」という表現があるのをご存じの方も多いと思います。十字架につけられた主イエスが、十字架の上で口にされた言葉を、四つの福音書から集めると、全部で七つあるというのです。マタイとマルコは同じ言葉を一つだけ、そして、ルカは三つ、ヨハネも三つ、それぞれ他の福音書にはない主イエスの言葉を記しています。最初は、主が、ご自分を十字架につけた人たちのことを執り成して祈られた言葉です。「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか分からないのです」(ルカ23章34節)。二つ目は、一緒に十字架につけられた犯罪人の一人に向けて語られた言葉です。「よく言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる」(ルカ23章43節)。同じように十字架にかけられていながら、主イエスは御国の権威をもって、救いを宣言されました。この最初の二つは、ルカが記録した言葉です。
三つ目、これは、ヨハネが記しました。愛する弟子に母マリアを託すようにして二人に語られました。「女よ、見なさい。あなたの子です」。「見なさい。あなたの母です」(ヨハネ19章26、27節)。十字架のもとで、新しい家族の絆が結ばれました。神の家族として交わりが造られたと言ってもよいと思います。四つ目は、マタイとマルコだけが記した言葉、「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」(マタイ27章46節、マルコ15章34節)。詩編22編の冒頭の言葉を引用するようにして、神に見捨てられた絶望の叫びを上げられました。本来ならば、神に背いて罪を犯し、神に見捨てられるべきは私たちでした。しかし、主イエスは、その私たちに代わって、私たちの身代わりとして、神に見捨てられてくださった。その絶望の中から、神に向かって呼びかける場所をも備えてくださったのです。
そして、五つ目と六つ目は、ヨハネが伝えました。先週の日曜日の礼拝において読んだところです。主イエスは、旧約聖書に預言された神の言葉を実現するために、「渇く」と言われました。その上で、差し出された酢を受けて、「成し遂げられた」と言われました。ヨハネによる福音書の19章30節にはこう記されていました。「イエスは、この酢を受けると、『成し遂げられた』と言い、頭を垂れて息を引き取られた」。「頭を垂れて息を引き取られた」というのですから、これが十字架上の最後の言葉かと思われます。実は、最後の「息を引き取られた」と訳されている言葉は、直訳すれば、「霊を引き渡された」となります。ルカは、これを主イエスの最後の言葉として伝えました。「すでに昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、三時に及んだ。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。『父よ、私の霊を御手に委ねます。』こう言って息を引き取られた」(ルカ23章44~46節)。まさに、すべてが成し遂げられたのを見届けるようにして、ご自身の霊を父なる神に委ねられたのです。
「頭を垂れて息を引き取られた」。神の独り子が、私たちと同じ人間として、この地上に生まれてくださいました。その主イエスの地上の命、主イエスの人としての歩みは、十字架の上で終わりました。主イエスのお体はなおも十字架の上にはりつけられたままですけれども、そのお体は、もはや動くことなく、その口はもはやひと言も言葉を発することはなくなりました。そこから、今日のところに続くのです。ヨハネによる福音書第19章の31節から37節。実際に聖書を開いて、この箇所を目にされたとき、お気づきになることがあるのではないかと思います。共同訳の聖書になって、聖書の区切りごとに「小見出し」が付されるようになりました。31節以下の段落には「イエスの脇腹を槍で突く」という見出しが掲げられています。ところが、その見出しの後に、他の福音書の並行箇所についての記載はありません。振り返ってみますと、第18章以下、具体的に、主のご受難の出来事が描かれていく中で、いつでも、太字で書かれた見出しの後に、括弧に入れて、他の福音書の並行箇所が記されていました。福音書は、それぞれの描き方は違うとしても、取り扱っている出来事は同じです。主イエスのご受難、十字架へと辿られる道筋を描いています。ですから、この並行箇所についての情報をもとにして、同じ出来事を、それぞれの福音書がどのように描いているのか、読み比べてみることもできるのです。ところが、18章と19章の中で、ただ一箇所、19章の31節から37節の段落には、他の福音書に並行記事がありません。つまりは、この段落に描かれた出来事は、ヨハネ福音書だけが記している特別な記事なのです。
他の福音書を見ると、マタイもマルコもルカも、それぞれに、主イエスが十字架の上で息を引き取られたとき、十字架に相対するように立って、すべてを見ていた百人隊長が、「まことに、この人は神の子だった」、あるいは、「本当に、この人は正しい人だった」と告白したと記しています。主イエスの十字架に相対して、主の死のさまを見つめたとき、異邦人でありながらも、その信仰を明確に言い表した人がいたと言うのです。ところが、ヨハネによる福音書だけは、この百人隊長の言葉を記していません。その代わりと言ってよいかもしれません。主イエスの死が何を意味しているのか、主イエスの死を確かめるような出来事を記して、私たちに問うているのだと思います。主の十字架と相対するように、主の死を見つめる私たちが、主イエスの死をどのように受けとめ、どのように応答するのか。ヨハネは、私たちに問いを突きつけているのです。
主イエスが、十字架の上で息を引き取られたのは、恐らく、午後3時頃のことだと考えられます。その後、日が沈むまでのおよそ3時間の間に、慌ただしく埋葬されることになります。当時のユダヤの暦では、日没と共に日が変わりました。つまり、日が変わる前に、その日のうちに、主イエスのお体を墓に納めようとしたのです。どうして、そんなに急がなければならなかったのでしょうか。ヨハネは次のように記します。「その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは、安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り降ろすように、ピラトに願い出た」。「準備の日」というのは、安息日や特別のお祭りの前日、祭儀のための準備をする日のことです。この日は、特別な安息日の前日で、準備の日であったというのです。聖書の時代、安息日は週の終わりの日、今で言う土曜日にあたります。七日ごとにめぐってきます。その日が特別であったというのは、過越祭が重なったからです。
過越祭は、ユダヤ人にとって、とても大切な祭りのときでした。かつてエジプトで奴隷生活を送っていた先祖たちが、奴隷の苦しみから解放されたことを記念するお祭りであったからです。神の人モーセが、かつて一緒に王宮で育ったエジプトの王ファラオの前に立って、イスラエルを解放するように求めました。ところが、神がファラオの心を頑なにしておられたので、交渉は進みません。そのために、エジプトには数々の災いが降りかかることになりました。細かい話をするいとまはありませんけれども、ナイル川の水が血に変わったり、蛙が大発生して川から上がってきて町の中に溢れ、家の中にまで入り込んできたり、バッタの大群に襲われたり、そんなのは序の口で、どんどん災いはエスカレートしていきました。そして、十番目、最後、最大の災いが初子撃ちでした。エジプト中の初子、人間で言えば長子、長男、そして、家畜の初子が皆、一夜のうちに撃たれて死んだのです。ファラオの息子、跡継ぎの王子も死んで、ついにファラオは心折れて、イスラエルを解放する事に同意したのです。
その夜、エジプト中の初子が撃たれた、と言いましたけれども、イスラエルの家からは一人の犠牲者も出ませんでした。イスラエルの家では、神が予めモーセを通してお命じになったとおり、家ごとに小羊を屠って、その血を家の入口の二本の柱と鴨居に塗っておいたのです。夜になって、死の使いが町中をめぐったとき、入口に小羊の血が塗ってある家は、中に入らずに過ぎ越していった。これが、過越祭の名前の由来です。ユダヤ人にとって、自分たちの救いの体験を記念する大切なお祭りであり、この祭りの時には、犠牲の小羊が屠られ、家族みんなでそれを食べたのです。過越祭の日付は、曜日に関係なく、ニサンの月の14日と決まっていました。それがたまたま、安息日と重なったのです。その特別に大切な安息日に、遺体を十字架の上に残しておかないように、日が変わって、安息日が始まる前に、つまり、日没前に遺体を十字架から取り下ろして、葬ろうとしたのです。
本来、十字架刑というのは、ローマ帝国への反逆者を見せしめとして磔(はりつけ)にして、さらし者にするというとても残酷な処刑方法でした。十字架の上でさらされて、次第に衰弱しながら死を迎えるのです。元気な若者であれば、なかなか死なずに数日間、十字架の上で呻きながら生きているということもあったようです。一瞬にして死を迎える斬首刑などよりも、よほど残酷な処罰であったわけです。ところが、翌日は特別な過越祭の安息日を迎えるということで、ローマ人には関わりのないことですけれども、ユダヤ人たちは、安息日に遺体を目に触れるところに残しておきたくなかったのです。聖書の律法に記されています。申命記の第21章22節と23節です。「ある人に死刑に当たる罪があり、処刑される場合、あなたは彼を木に掛けなければならない。あなたはその死体を夜通し、木に残しておいてはならない。必ずその日のうちに葬らなければならない。木に掛けられた者は、神に呪われた者だからである。あなたは、あなたの神、主があなたに相続地として与える土地を汚してはならない」。十字架につけられた主イエス、それはまさに、「木に掛けられた者」、「神に呪われた者」であり、その遺体を、翌日まで木に残しておかないようにしなければなりません。しかも、翌日は特別な安息日であったために、日が変わる前に、何としても遺体を葬る必要がありました。
そこで、ユダヤ人たちは総督ピラトに願い出たのです。「足を折って取り下ろすように」。足を折るというのは、まだ十字架の上で生きている死刑囚の死を早めるために、棍棒で足の骨を打ち砕くということであったようです。足を折って早く死なせて、日が沈む前に葬ってしまおうと考えたのです。ユダヤ人たちの願いは聞き届けられました。ピラトに遣わされた兵士たちが来て、主イエスと一緒に十字架につけられた二人の男たちの足を折りました。ところが、主イエスを見ると、もうすでに死んでおられたというのです。それで、その足を折ることはしませんでした。ヨハネの福音書は、そこにも、旧約聖書の預言の成就を見ています。19章36節に記されます。「これらのことが起こったのは、『その骨は砕かれない』という聖書の言葉が実現するためであった」。思い起こされるのは、詩編の34編の言葉です。詩編34編は、「私はどのような時も主をたたえよう。私の口には絶え間なく主の賛美がある」という言葉から始まる信仰の詩です。印象深い言葉が綴られており、じっくりと味わいたい詩編の一つです。今日は、福音書に合わせて、この詩編34編の16節から23節までを朗読しました。その20節と21節にこうありました。「正しき者に災いは多いが 主はそのすべてから助け出してくださる。彼の骨をすべて守り その一本も砕かれることはない」。
「正しき者に災いは多い」。誤魔化しのない、現実的な言葉です。普通ならば、「正しい者」、つまり、神さまを信じて、神さまに従う人は、決して災いを受けることはない、と言いたいところかもしれません。けれども、聖書は、私たちが直面する厳しい現実を見つめながら、そこでなお私たちに与えられる救いを語ります。主を信じる者、主に従う正しい者にも災いが及びます。けれども、主はそのすべてから助け出してくださる。災いの中にあっても、主が共にいて守ってくださるのです。神さまは、その骨をすべて守ってくださり、その骨の一本も砕かれることはない、という。この聖書の言葉が、主イエスにおいて、実現しているというのです。確かに、目に見える現実として、主イエスの足の骨が折られることはありませんでした。けれども、主イエスは十字架にかけられ殺されたのです。災いが多いなどというレベルを遥かに超えて、究極的な災いを受けられたと言ってよいと思います。しかし、聖書は、その骨が折られることはなかったという言葉で、先ほど触れた過越の小羊のことを合わせて思い起こしているのです。
出エジプト記の第12章には、エジプト脱出に際して起こった過越の出来事について記されています。それに続けて、過越の出来事を記念して毎年行われる過越祭の祝い方について詳しい規定が記されるのです。イスラエルの人たちは、それぞれの家ごとに、過越の犠牲である羊を屠り、家族でそれを食べることによって、主の救いを記念し、喜び祝いました。その食事についての規定の中に、過越の小羊の骨を折ってはならない、と記されているのです。福音書記者ヨハネは、十字架につけられた主イエスの足が折られなかったことに、この旧約聖書の言葉の実現を見ています。主イエスは、私たちのための過越の小羊として死んでくださったと告げるのです。洗礼者ヨハネが告げた言葉を思い起こします。洗礼者は主イエスを指さして言いました。「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ」。過越の小羊の死という犠牲によって、神の民イスラエルが奴隷の生活から解放されたように、主イエスが犠牲の小羊として屠られたことによって、私たちは罪と死の支配から解放されました。主イエスの足の骨が折られなかったのは、まさに、過越の犠牲の小羊として屠られたことを指している、ヨハネはそのように証ししているのです。
兵士たちは十字架につけられた二人の男の足を折りましたが、主イエスはすでに死んでおられたので、その足を折ることはしませんでした。ただし、その代わりに、本当に死んでおられることを確かめようとしたのでしょうか。十字架につけられてもう動かなくなっている主イエスの体を、兵士の一人が槍で突き刺したのです。「すると、すぐ血と水とが流れ出た」と記されています。槍で脇腹を刺した、というのは、心臓をめがけたのだと思います。槍で突き刺したのですから、血が流れ出たというのは分かります。もう心臓は止まっていますから、血が噴き出すということはなかったと思われます。しかし、血だけではなくて、同時に水が流れ出たというのです。ヨハネは、その不思議な出来事については、それを目撃した証人がいるのだと告げています。「それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者は、あなたがたにも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている」。目撃した証人、それは、十字架の足元に立っていた、主イエスに愛された弟子であったと考えられます。
福音書は、この出来事にも、聖書の言葉の実現を見ています。19章37節です。「また、聖書の別の箇所に、『彼らは、自分たちの突き刺した者を見る』とも書いてある」。旧約聖書ゼカリヤ書の12章10節の言葉が思い起こされています。「私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが刺し貫いた者のことで私を見て、独り子の死を嘆くように嘆き、初子の死を悼むように悼む」。このゼカリヤ書の言葉は、「ダビデの家とエルサレムの住民」つまり神の民である人々が、「自分たちが刺し貫いた者」のことで、深く嘆き悲しむ、と言うのです。主イエスを刺し貫いたのは、ローマの兵士です。けれども、神の民であり、主イエスの弟子である私たちが、神の独り子主イエスを刺し貫いたと言うのです。この私の罪のゆえに、神の独り子が刺し貫かれたからです。私たちではなく神が、「独り子の死を嘆く」嘆きと、「初子の死を悼む」悲しみを引き受けてくださいました。大切な御子の命を犠牲にして、御子を刺し貫いた私たちの罪を赦してくださったのです。
兵士が、主イエスの脇腹を槍で刺したとき、すぐに血と水とが流れ出た、と言います。けれども、主のお体はピクリとも動きませんでした。主イエスは本当に死なれたのだということを、福音書は告げているのだと思います。さらにまた、教会はそこに象徴的な意味を見いだしてきました。水はきよめをあらわします。血は命をあらわします。主イエス・キリストの十字架の死によって、すべての人の罪が清められ、新しい命が与えられることを示しているというのです。この水と血は、洗礼と聖餐を指していると読む人もいます。主イエスは、ご自身の犠牲の死を通して、私たちすべてを、洗礼と聖餐の恵みに招いていてくださるのです。
ヨハネの福音書は、私たちを罪と死の支配から救い出すため、十字架にかかってご自身の命を犠牲にしてくださった過越の小羊、主イエス・キリストのお姿を描きます。主イエスは私たちのために死んでくださいました。だから、私たちは死をも恐れることはありません。死の中でも、主は私たちと共にいてくださり、死の向こうへと、復活の光へと私たちを伴ってくださるからです。