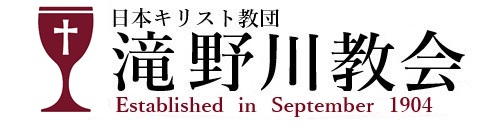2025年3月23日 受難節第三主日礼拝説教「墓にもおよぶ救いの力」 東野尚志牧師
詩編 第88編1~19節
ヨハネによる福音書 第19章38~42節
2024年度の歩みも残りわずかとなりました。次週の主日は、今年度最後の礼拝を行うことになります。午後には、定期教会総会が開かれます。2025年度の伝道計画、予算を審議し、役員の改選を行って、翌週から始まる新年度の歩みに備えることになるわけです。受難節の中で、この年度の歩みを締めくくり、新しい年度を迎えます。終わりは、新たな始まりへとつながっています。
そのような中で、今週の水曜日、3月26日には、大切な教会の仲間の葬りを行うことになりました。石川日出男兄。先週の火曜日、3月18日、主のみもとに召されました。95歳でした。数年前に胃がんの手術を受けられて、今年の1月に再発が見つかりました。再手術はせずに、すべて神さまの御手に委ねるという決断をされて、この2ヶ月を過ごしてこられました。天に召されるちょうど一か月前、2月18日に、ご自宅で聖餐礼拝を行いました。3月6日に緩和ケア病棟に入院されて、その2日後、病室をお訪ねしたときも、本当に穏やかに迎えてくださいました。ささやくような声で喉が渇いたと訴えられ、私が霧吹きで喉の奥をぬらして差し上げたのが、最後のやり取りになりました。聖書を読んで、お祈りをすると、細い声で、しかし、しっかりと「アーメン」と唱和された。今もその声は、私の耳に残っています。
聖学院中高の初代校長を務められた石川角次郎先生の孫であり、ご自身も聖学院で学ばれ、後には、教会の責任役員として長く務めを担ってこられました。今からもう7年前のことになりますが、牧師招聘の責任を負って、私のところにお電話くださったのも石川さんでした。滝野川教会にとっては、まさに長老格の存在でした。葬りの礼拝に出て、最後のお別れをしたいと望まれる方が大勢おられると思います。しかし、このたびは、ご家族の事情で、お身内のみで葬儀を行うことになりました。教会の皆さまには、そのことをご理解いただき、お祈りに覚えていただきたいと願っています。そして何よりも、私たち信仰者にとって、これが地上では最後の別れであるとしても、死ですべてが終わるのではないことを、改めて、深く心に刻みたいと思います。
『ハイデルベルク信仰問答』は、私たちの死について語ります。「わたしたちの死は、自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪の死滅であり、永遠の命への入口なのです」(問答42)。私たちは、主イエスの十字架における犠牲の死によって、罪の贖いを受けました。確かに、地上の命には限りがあり、私たちの肉の体は滅びます。けれども、終わりの日には、栄光の体によみがえらされ、主の前に共に集められて、永遠に主をほめたたえる者とされるのです。その約束を信じて、愛する兄弟をも、主の御手に委ねたいと思います。教会の皆さまには、葬りの礼拝に参列していただくことができませんけれども、ぜひ、水曜日の葬儀を覚えて、それぞれの場所で祈りを合わせていただければと願います。
その意味で言うなら、愛する兄弟の葬りを覚えながら、主の日の礼拝において、主イエス・キリストの葬りの記事を読むことができるのは、幸いなことであると思います。十字架の上で死んで、墓に葬られた主イエスは、三日目に墓の中からよみがえられました。死の中にも復活へと貫かれる命の道を開いてくださいました。だから私たちは、主に結ばれて死に、主に結ばれて生きることを信じることができます。地上の命の終わりとしての死が、主イエスの死に合わせられるとき、終わりは新たな始まりにつながることを、望み見ることができる。主イエスの葬りの出来事が、愛する信仰の仲間の葬りの場所を備えてくださったと言ってもよいのです。
さて、ヨハネによる福音書は、主イエスの葬りに、2人の人物が関わったことを記しています。最初に登場するのは「アリマタヤ出身のヨセフ」という人です。この人が、ローマの総督ピラトのもとを訪れて、主イエスの遺体を取り降ろしたいと願い出た、と言います。犯罪人として処刑された囚人の遺体を引き取るというのは、大変なことでした。囚人の身内でなければあり得ないことであり、身内であっても、願い出ることは少なかったと言われます。犯罪人の身内であると知られると、共同体の中に留まることがむずかしくなるからです。今日でも、身内に犯罪人が出れば、家族は肩身の狭い思いをすることがあります。さまざまな不利益を被ることもあります。縁を切ろうとする人もいるでしょう。処刑された囚人と、積極的に関わりを持とうとする人はいませんでした。その遺体を葬ると言っても、せいぜい、布にくるんで穴の中に放り投げるか、人里離れた所に放置して鳥や獣に遺体を食べさせるか、というくらいであったと言われます。そういう中で、アリマタヤ出身のヨセフという人が、主イエスの遺体を取り降ろして葬ることを願い出たのです。
このヨセフという人物が、主イエスを葬ったということについては、ヨハネだけでなく、マタイ、マルコ、ルカ、四つの福音書のすべてが記しています。マタイは、この人が「金持ち」であり、「イエスの弟子であった」と記しています(27章57節)。マルコは、この人が「高名な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた」と記しています(15章43節)。またルカは、「善良な正しい人で、同僚たちの決議や行動には同意しなかった」「神の国を待ち望んでいた」と記しています(23章50~51節)。最高法院である議会において、主イエスを死刑にする決議がなされた際、それには同意していなかったと言うのです。ところが、ヨハネは、この人が裕福であったとか、議員であったとか、その社会的な身分については何も記しません。ピラトに直接願い出ることができたということは、当然、高い身分にあった人であると想像はつきます。しかし、そういうことにはお構いなしに、ただひとつのことを記します。「イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していた」と言うのです。
その後に登場するもう一人の人物、ニコデモも同じような立場であったのではないかと思われます。ニコデモについては、「前に、夜イエスのもとに来たニコデモ」と記されています。すでに、同じ福音書の第3章に登場した人です。恐らく、主イエスの教えや力ある業に触れて、この方はただ者ではないと思ったのでしょう。ローマの支配下に置かれたユダヤの社会には、神が生きて働いておられるしるしを見ることができない。けれども、主イエスの言葉と業において、神の国、神の支配が見えている。それで主の教えを求めて、訪ねてきたのです。ただし、そのことを周りのユダヤ人や議会の同僚たちに知られないように、夜の闇に紛れて、ひそかに主イエスのもとを訪れました。その時の不思議なやりとりを詳しく見ることはできませんが、主イエスはニコデモに言われました。「よくよく言っておく。人は、新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない」(3章3節)。恐らくニコデモは老人であったと思われます。主イエスに尋ねました。「年を取った者が、どうして生まれることができましょう。もう一度、母の胎に入って生まれることができるでしょうか」(同4節)。すると主は言われました。「よくよく言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である」(同5~6節)。「新たに生まれる」「水と霊とから生まれる」「霊から生まれる」。そのように言葉を重ねながら、信仰によって新たに生まれる者こそが、永遠の命を生きるようになると教えられたのです。
そのときには、ニコデモは主イエスの言葉がよく分からなかったようです。聖霊の働きを知らず、肉体の命しか知らなかったからです。ニコデモは、その後、再度登場しました。第7章です。祭司長やファリサイ派の人たちが主イエスを逮捕しようとして下役たちを遣わします。主イエスを信じる者たちがどんどん増えていったので、危機感を抱いたからです。ところが、その下役たちも、主イエスの言葉に圧倒されて、手ぶらで帰ってきた。当然のこと、祭司長やファリサイ派の人たちは下役たちを咎めるのですが、そのとき、ニコデモが口を挟みました。「我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめたうえでなければ、判決を下してはならないことになっているではないか」(7章51節)。この時点で、主イエスを逮捕しようとするのは不当だと訴えたのです。ところが、同僚の議員たちから「あなたもガリラヤ出身なのか」と言って、主イエスの仲間であることを疑われると、そこで黙ってしまいます。その後、12章42節には、このニコデモやヨセフのことを暗示するような言葉が記されていました。「議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、会堂から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって告白はしなかった」。心の中では、主イエスのことを信じているにもかかわらず、その信仰を公に告白することはできず、隠していたのです。
恐らく、福音書記者は、主イエスが肉体をもって生きておられた時の状況を記しながら、そこに、福音書が書かれた1世紀の終わり頃の時代状況を重ね合わせるように描いているのだと思われます。9章にはこういう言葉も記されていました。「ユダヤ人たちはすでに、イエスをメシアであると告白する者がいれば、会堂から追放すると決めていたのである」(9章22節)。主イエスをメシア、すなわち、救い主であると告白する者は、会堂から追放する。つまり、ユダヤ人の共同体から追い出す。このような厳しい措置は、主イエスが地上を歩んでおられた頃には、まだ決まっていませんでした。その後、主イエスの十字架の死と復活を経て、教会が生まれ、伝道が進んで行く中で、ユダヤ人からの厳しい迫害が起こるようになります。主イエスに対する信仰を公に告白して、洗礼を受けた者たちは、ユダヤ教の会堂から追放されるようになるのです。教会の周辺には、主イエスの教えに心動かされ、心の中では主イエスを信じている人たちがいました。ところが、その信仰を人々の前で公に言い表すことができずに、隠している人たちがいたが大勢いたのです。恐らく、福音書記者ヨハネは、そのような人たちを励ますために、アリマタヤのヨセフとニコデモの姿を描いたのではないかと思われます。
ヨセフもニコデモも、ユダヤ人をはばかって、自分たちの信仰を公にすることができずにいました。主イエスを信じる者であることが知られると、その地位や財産を失うことになるかもしれません。主イエスの弟子でありながら、そのことを隠して生きてきたのです。ところが、主イエスが十字架につけられ、殺された日、ヨセフとニコデモは、勇気を出してピラトのもとを訪れ、主イエスの遺体を引き取って埋葬しました。主イエスの死と葬り、この大事な場面において、もはや信仰を隠していることができなくなり、主イエスを信じる者であることを明らかにしました。ただ心の中で信じているだけではなくて、主イエスに従って行く弟子となったのです。そのようにして、主の復活のための備えに関わることができました。復活の栄光が現わされる墓を備えることができたのです。福音書記者ヨハネは、この福音書の最初の読者となった教会の仲間たちに、またその周囲にいる人たちに、信仰の決断を促していると言ってよいのです。
さらには、それから二千年を経て、今、この福音書を読んでいる私たちに対しても、御言葉は迫ってきます。心の中で主イエスを信じて、主イエスの教えを自分なりに守って生きていればよいのではないか。洗礼を受けたいと言って、家族を説得する自信がない。洗礼を受けることで、仕事の仲間たちからも浮いてしまうかもしれない。それならば、無理をせずに、波風を立てずに、心の中で信じていようと退いてしまいがちな現代人に対しても、信仰を公に表し、告白することの大切さを告げているのです。
福音書記者は、ヨセフが主イエスのお体を葬った墓は、「誰もまだ葬られたことのない新しい墓」であったと記しています。しかも、その墓は園のなかにあったというのです。私たちは、墓地が公園になっているところを見慣れているかもしれません。けれども、当時、園の中にある墓というのは、王の葬りために用いられる特別な墓所でした。福音書記者ヨハネは、主イエスが「ユダヤ人の王」として、全世界の救い主として、王のための墓に葬られたと告げているのかもしれません。しかも、その墓は、誰も葬られたことのない新しい墓です。神への献げ物は、それまでに用いられたことのない初物でなければなりませんでした。つまり、この墓は、神である主イエスに献げられた墓であり、主イエスはまことの王として葬られたということを証ししているのです。マタイによる福音書によれば、その墓は、ヨセフが自分のために用意していた墓であったといいます。裕福であればこそ、出身地から離れたエルサレムの中に、自分のための墓を用意することができたのかもしれません。ヨセフは、自分の死のときに備えて用意した墓を主イエスにお献げしたのです。
ニコデモも同様であったと思われます。福音書記者は記します。「前に、夜イエスのもとに来たニコデモも、没薬とアロエを混ぜた物を百リトラばかり持って来た」。ユダヤの埋葬においては、遺体を安置する横穴に香料を添える習慣がありました。ニコデモは、その習慣に従って、百リトラもの香料を携えてきたと言うのです。聖書の巻末の換算表によれば、1リトラは326グラムとあります。百リトラと言えば、33キロ近くの重さになります。それほどの量の没薬とアロエを、予め主イエスの葬りのために用意していたとは思えません。恐らくそれは、自分の葬りのために用意していたのではないでしょうか。ニコデモは年老いたあった老人であったと言われます。そう遠くない自分の死に備えていたのです。いずれにしても、ヨセフは自分の死に備えて用意していた墓を主イエスにお献げし、ニコデモもまた自分の死に備えて蓄えておいた香料を主イエスにお献げしました。それによって、主のお体の葬りが整えられたのです。
ヨセフやニコデモだけでなく、私たちもある程度の年齢になると、自分の墓を備えることを考えたり、自分の葬式代に充てるくらいのものは用意しておこうと考えたりするのかもしれません。それも大事なことだと思います。けれども、私たちの死、私たちの葬りもまた、主イエスの死と葬りによって支えられているということを、忘れてはならないのだと思います。主イエスは、私たちのために死んでくださり、私たちのために葬られたのです。そして、地上の歩みの終着点と見なされる墓を、復活の栄光の現れる場所としてくださいました。もはやすべての望みが絶たれた場所、暗闇に閉ざされた場所であった墓を、よみがえりの栄光で照らしてくださいました。墓をも突き抜けるようにして、よみがえりの道を開いてくださいました。ヨセフとニコデモは、自分自身の葬りのために備えていたものをすべて主にお献げすることによって、主の死に合わせられ、新たに生まれる救いの望みを表わした、と言ってもよいのではないでしょうか。その日は準備の日でした。その日、隠れた弟子たちは、その信仰をはっきりと現わし、主の葬りに仕えることを通して、主イエスの復活の備えをしたのです。
ユダヤ人たちを恐れて、それまで隠していた主イエスへの信仰を公にすることには、勇気が必要であったと思います。確かに、ヨセフもニコデモも、勇気を出して、自分たちの信仰を公にしました。けれども、それぞれに勇気を振り絞って、恐れに打ち勝ったというのではありません。自分のために備えた墓と香料を主イエスに献げ、それによって自分自身を主イエスにお献げして、主の真実な弟子として立てられたとき、すべての恐れから解放されたのです。私たちはいろいろなものを恐れ、不安を抱きます。自分がまわりにどう思われているか、ひとの目を恐れます。病への恐れがあり、生活の不安もあります。その恐れの究極は、死への恐れだと言ってよいと思います。しかし、主イエスの死に合わせられるとき、主のよみがえりにも合わせられることを信じることができる。死で終わる命につきまとう不安や恐れは、復活の光によって取り除かれるのです。
愛する者の死と葬りに直面すときにも、死を突き抜けた、栄光の主を望み見て、慰めと勇気を与えられたいと願います。信仰を隠すことなく、公に告白し、主とひとつに結ばれる洗礼を受けた者は、主の死に合わせられて古い罪の自分に死に、主の復活に合わせられて新しい命を生きる者とされました。主に結ばれた命は、地上の命の終わりとしての死によっても空しくならず、復活の朝の訪れを望み見ることができるのです。