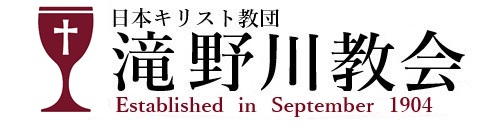2025年3月2日 主日礼拝説教「成し遂げられた救い」 東野尚志牧師
イザヤ書 第55章9~11節
ヨハネによる福音書 第19章28~30節
新しい月、3月を迎えました。2024年度の最後の一か月となります。来月から始まる新しい年度の教会の活動のために、その備えをする月でもあります。お手元の週報第4面に記されておりますように、今月の最後の主日、3月30日には、礼拝に引き続いて、定期教会総会を開催することになります。2025年度の伝道計画、また予算を審議し、2025年度の役員を選出します。4月の第一主日には、役員の任職式が行われますので、慌ただしい運びになります。いずれにしても、教会創立120周年をお祝いした2024年度の歩みを締め括って、新たな年度への準備を整える大切な時を迎えているのです。
そのような中で、今週の水曜日からレントに入ります。「受難節」とも呼ばれます。かつては、断食と祈りをもって、悔い改めを深くする期間として定められていました。初期の教会では、クリスマスのお祝いはありませんでした。年に一度、主のよみがえりを祝うイースターの前夜に洗礼式が行われるようになったと言われます。イースターに先立つ受難節は、受洗志願者の学びと準備の期間でもありました。カトリック教会では、受難節の始まる日に、悔い改めのしるしとして、額に灰をつける儀式が行われます。それで、レントの始まる日は「灰の水曜日」、Ash Wednesdayと呼ばれます。なぜ水曜日から始まるのかというと、主の復活を祝うイースターに先立つ40日の期間を数えたからです。「四旬節」とも呼ばれます。文字通り、40日間を意味する言葉です。
ご承知の方も多いと思います。聖書において、40という数字は、象徴的な意味を持ちます。40年、40日40夜、という言葉が出て来ます。神による吟味を示す数字だと言われます。イスラエルの民は、エジプトでの奴隷生活から解放された後、40年にわたって、シナイ半島の荒れ野を旅することになりました。それは、厳しい試練の時でした。神に背いた世代は荒れ野で滅ぼされ、荒れ野で生まれ育った新しい世代が約束の地カナンに入っていくことになりました。荒れ野の40年は、イスラエルの民にとって、食べ物も水もない荒れ野で、ただ神が与えてくださる命の糧によって生かされるという特別な恵みを味わう時でもありました。神の言葉によって生きる、信仰の訓練の期間でもあったのです。モーセは40日間シナイ山に留まって神から十戒を授かりました。主イエスもまた、荒れ野で40日40夜、断食をされました。それは、メシアとしての働きを始めるために、必要な備えの期間でした。こういう象徴的な数字を大切に受けとめて、イースターに洗礼を志願する者たちは、それに先立つ受難節に、40日間、断食と祈りをもって、学びと備えの時を過ごしたのです。
40日と言いました。けれども、実際に、受難節の期間を数えてみると、46日あります。その中に、6回の日曜日が含まれているからです。受難節といえども、主の復活を記念する主の日には断食をしません。6回の日曜日を除いて40日を数えるので、実際には46日間、イースターから遡って行くと、必ず水曜日から始まることになります。いよいよ、今週の水曜日から、受難節に入ります。来週の日曜日は、受難節第1主日ということになるわけです。私たちの救い主である主イエスのご受難を覚えて、祈り深く過ごすことができるようにと願います。
受難節を前にして、今日は、主イエスが十字架の上で息を引き取られる場面を読むことになりました。聖書協会共同訳の聖書では、わずか3節から成る段落に「イエスの死」という見出しが掲げられています。福音書記者ヨハネは、十字架にかけられた主イエスの最後の言葉を記しています。30節を見ると、主イエスは「成し遂げられた」と言って息を引き取られたのです。実は、同じ言葉が28節にも用いられています。「この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、『渇く』と言われた。こうして、聖書の言葉が実現した」。「すべてのことが今や成し遂げられた」、つまり、主イエスの十字架の出来事によって、すべてのことが成し遂げられたというのです。以前の口語訳聖書では、「すべてが終わった」と訳されていました。どちらも、翻訳としては間違っていません。けれども、日本語から受ける印象は少し違うかもしれません。
「すべてが終わった」というと、もうそこですべて断ち切られてしまって、後は何も続かない寂しさを感じてしまいます。「終わってしまった」という言い方があるように、そこには、すべてが断ち切られてしまったことに対する悲しみや嘆きを伴う、否定的な響きがあるのです。とりわけ、ここでは主イエスの死が描かれるわけですから、死ですべてが終わった、というと、もうすべての望みがそこで絶たれてしまったような印象を受けてしまいます。それに対して、「成し遂げられた」という日本語を読むと、そこには、達成感があり、完成された満足や肯定的な響きが感じられます。主イエスは、どのような思いで、この言葉を口にされたのでしょうか。
さらに言えば、福音書は、「成し遂げられた」という同じ言葉を用いておりながら、そこにはズレが生じていることに気づきます。28節で「この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り」と言いながら、だから「成し遂げられた」と言われたというのではありません。まだそこにつながっていないのです。主イエスは、すべてのことが成し遂げられたのを知って、「渇く」と言われた、というのです。しかも、それによって、「聖書の言葉が実現した」というのです。この時点では、まだ新約聖書が生まれていませんから、「聖書」と言えば、私たちの言う「旧約聖書」です。つまり、主イエスがなさったこと、主イエスが語られたことによって、旧約聖書が伝えている神さまの言葉が実現したというのです。口語訳聖書では、「それは、聖書が全うされるためであった」と訳しています。旧約聖書に預言されていたことが実現するために、聖書の言葉が現実になるために、主イエスは「渇く」と言われたと告げるのです。
「聖書の言葉が実現した」と言われて、すぐに思い起こされるのは、詩編22編の言葉です。詩編22編の16節に記されています。「力は素焼きのかけらのように乾ききり 舌は顎に張り付いた。あなたは私を死の塵に捨て置かれた」。口が渇いて、舌が上顎に張り付くようだと語ります。口がカラカラに渇いてもうあとは死を待つばかりだというのです。この詩編22編は、主イエスを十字架につけた兵士たちが、主イエスの上着や下着を分け合っている場面でも思い起こされていました。同じ19章の23節以下です。「兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚織りであった。そこで、『これは裂かないで、誰のものになるか、くじを引こう』と話し合った。それは、「彼らは私の服を分け合い 衣をめぐってくじを引いた」という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこのとおりにしたのである」。この詩編22編は、深い嘆きの言葉から始まっていました。「わが神、わが神 なぜ私をお見捨てになったのか」。これは、マタイとマルコの福音書によって、主イエスが十字架の上で叫ばれた言葉として引用されています。主イエスは、まさに、詩編22編をなぞるようにして、十字架の上で、神に見捨てられた絶望の叫びを口にされ、兵士たちがご自分の服を分け合い、くじを引く様子を御覧になりながら、舌が上顎に張り付くような死に至る渇きの中で、「渇く」と口にされたのです。
主イエスの渇き、それは確かに、肉体の渇きです。主イエスは、前の晩から、弟子の裏切りによって捕らえられ、裁かれ、鞭で打たれて血まみれになり、息も絶え絶えの中で茨の冠をかぶせられ、さんざん嘲られ、さらし者にされて十字架刑を言い渡されました。ふらふらになりながらも、ご自分がつけられる十字架を背負って、処刑場までやって来られた。着ているものは剥ぎ取られて腰布一つ、手や足に太い釘を打たれ、裸で磔にされているのです。普通に鼻から息を吸って口から吐くなどということはできません。だらしなく口を開けてゼーゼー言わせて息をするしかありません。肺が圧迫されて息苦しく、どんどん渇きが増していったと思われます。釘を打たれた手や足から血が滴り落ちて、体の水分も失われていきます。主イエスは、神の独り子であるにもかかわらず、私たちの身代わりとなって、私たちの罪をすべて背負って、十字架にかかってくださいました。肉体で味わう痛みや苦しみを極限まで味わいながら、喉が張り付く渇きの辛さを訴えられたのです。
私たちは今、十字架につけられているわけではありません。喉が渇いたら、すぐに水を飲むこともできるし、コーヒーや紅茶、ジュースでも、何でも自由に口にすることができます。肉体の渇きは、水分を補給すれば癒やされます。被災地でライフラインがとまり、あるいは、瓦礫に挟まれて身動きができず、簡単に渇きを癒やせない命に関わる状況に陥ることもあります。しかし、それは公的な救助や援助が届くまでの一時的なものです。けれども、魂の渇きは、さらに深刻なのではないでしょうか。肉体の渇きは、水分を補給すれば癒やされます。でも、魂の渇きには直ぐに利くものがありません。なかなかひとに理解してもらうこともできません。自分で抱え込んで、どんどん孤立していきます。詩編63編2節に、こういう言葉があります。「神よ、あなたこそわが神。私はあなたを探し求めます。魂はあなたに渇き 体はあなたを慕います 水のない乾ききった荒れ果てた地で」。魂の渇き、それは、神への渇きだというのです。神が共にいてくださることが分からなくなる渇きです。この渇きは、神が応えてくださるまで、癒やされることがないのです。
「私は渇く」。主イエスの渇きは、肉体の渇きだけでなく、魂の渇きをも現わす言葉であったと思います。十字架上での主の言葉を伝えたヨハネの福音書は、別の場面でも主の渇きについて記していました。ヨハネによる福音書の第4章、主イエスがサマリアの地方を通って行かれ、シカルという町の井戸のそばで座っておられたときのことです。サマリアの女が水を汲みに来たとき、主イエスは「水を飲ませてください」と言って、声をかけられました。真昼時の炎天下、主イエスは渇きを覚えておられたのです。そこから、主イエスとサマリアの女の対話が始まりました。その対話を通して、主イエスは、この女性が抱えていた魂の渇きに触れて行かれます。そして、言われました。「この水を飲む者は誰でもまた渇く。しかし、私が与える水を飲む者は決して渇かない。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る」(4章13~14節)。永遠の命に至る水を与えることのできるお方が、今、「渇く」と訴えておられるのです。私たちの渇きをすべて引き受けるようにして、救い主が渇きを覚えておられるのです。
「こうして、聖書の言葉が実現した」。「渇く」という言葉は、詩編22編だけではなくて、69編の言葉をも思い起こさせます。詩編69編22節です。「彼らは私の食物に毒を入れ 渇く私に酢を飲ませようとします」。「酢」というのは、文字通りの「酢」ではなくて、酸っぱくなったぶどう酒のことです。ヨハネの福音書は、主イエスが十字架の上で「渇く」と言われたとき、それを聞いた人たちが何をしたかを記しています。19章29節です。「そこには、酢を満たした器が置いてあった。人々は、この酢をいっぱい含ませた海綿をヒソプに付け、イエスの口元に差し出した」。酸っぱくなった安いぶどう酒に、痛みを麻痺させる薬が混ぜられていたようです。十字架刑の苦しみを和らげて、死を早めるために受刑者に与えたと言われます。それをたっぷり含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけて、主イエスの口元に差し出したのです。
差し出された酢を受けて、主はあの最後の言葉を口にされます。19章の30節です。「イエスは、この酢を受けると、『成し遂げられた』と言い、頭を垂れて息を引き取られた」。主イエスは、十字架の上で、ご自分のなすべき業がすべて成し遂げられたことを見ておられます。主イエスの十字架の死において、私たちを罪と死の支配から救い出そうとされた父なる神の御心が成し遂げられ、救いのご計画が実現したのです。神の私たちに対する御心は、同じ福音書の3章16節にはっきりと記されていました。「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」。この父なる神の御心と救いの御業が成し遂げられたのです。主イエスの十字架の死において、私たちに対する神の愛が貫かれました。大切な独り子の命を犠牲にしてまでも、私たちを滅びの道から救い出そうとする神の熱情、神の愛が実現したのです。
父なる神さまだけではありません。主イエスもまた、お選びになった弟子たちを愛し抜かれました。ヨハネの福音書において、受難の物語が始まった第13章は、こんな言葉で始まっていました。「過越祭の前に、イエスは、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれた」。最後まで愛し抜かれた。極みまで愛された。ここで、「最後まで」と訳されている言葉も、完成、終わりを意味する言葉です。主イエスの愛が、極みまで貫かれ、その愛の業が成し遂げられ、完成するのです。主イエスは、弟子たちの足を洗うという象徴的な業をもって、その愛を印象深く現わされました。そして、弟子たちにも、互いに愛し合い、仕え合うようにと教えてくださったのです。主の愛が、私たちの魂の渇きを癒やしてくださいます。主が私たちを愛していてくださる。この神の愛と出会ったら、私たちの心は豊かに潤されるのです。
荒れ野で五千人の大群衆をわずか五つのパンと二匹の魚で十分に食べさせた後、主イエスは、言われました。「私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない」(6章35節)。主イエス・キリストにおいて、旧約聖書の言葉が実現していることを知らされます。今日は、福音書に合わせて、旧約聖書イザヤ書55章の9節から11節までを読みました。同じ55章の1節では、こういう言葉が告げられています。「さあ、渇いている者は皆、水のもとに来るがよい。金のない者も来るがよい。買って、食べよ。来て、金を払わず、代価も払わずに ぶどう酒と乳を買え」。また3節で言われます。「耳を傾け、私のところに来るがよい。聞け。そうすればあなたがたの魂は生きる」。御言葉を聞くことによって、私たちの魂は潤されるのです。生きた神の言葉として、主イエスは私たちのところに来てくださいました。そして、父なる神から託された愛の業を成し遂げてくださったのです。
命のパンの宣言の後、主はさらに言われました。「よくよく言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたがたの内に命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである」(6章53~55節)。今、私たちの前に、主イエスの肉と血がそなえられています。主イエスの肉である命のパンに与り、主イエスの血である救いの杯を受ける時、私たちの間に、生ける主が共にいてくださり、私たちを永遠の命の糧で養ってくださいます。決して渇くことのない命の水が、私たちのうちに満ち溢れ、溢れ出て、この渇いた世界を潤していくのです。「成し遂げられた」。十字架から響かせられる主の勝利の宣言を、感謝をもって受けとめたいと思います。どうか、主の招きに応えて、洗礼を受け、聖餐にあずかる豊かな恵みを味わってください。そのために、主は私たちのところに来てくださり、十字架にかかり、私たちの救いを成し遂げてくださったのです。