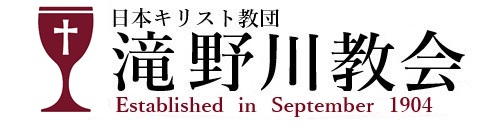2025年11月2日 召天者記念礼拝説教「天から与えられる住みか」 東野尚志牧師
ヨブ記 第19章23~27節
コリントの信徒への手紙二 第5章1~10節
昨日、朝日新聞の朝刊を開いたとき、「山手線、丸くなって100年」という見出しの記事が目に飛び込んできました。日本の鉄道事業は、すでに150年を超える歴史を刻んでいます。そんな中、今から140年前、1885年に現在の山手線の原形となる「品川線」が一部開業されました。その後、少しずつ路線を延ばしていく間に、郊外と都心をつなぐ「中央線」も貫かれます。そして、今から100年前、1925年11月1日、ついに「山手線」が、丸くつながって環状運転を開始したというのです。私はその記事を読みながら、今から100年前、大木英夫先生の有名なたとえ話の素材が整えられたのだと思って、何だかうれしくなりました。
先日は、神学校日礼拝の説教者として、日本同盟基督教団の飯田仰先生をお迎えしました。礼拝の後、2人で萬盛庵に出かけて一緒に食事をしながら、親しく語り合いました。大木英夫先生の名前が出たとき、飯田先生は真っ先に、大木先生が発案された「山手線と中央線のたとえ話」の話をされたのです。このたとえは、教派、教団の枠を越えてよく知られているのだと知りました。それほどに、印象深く、秀逸なたとえです。聞いた人の心にくっきりと刻まれて、誰かに話したくなる、そういう話なのです。その意味するところを、ここで繰り返す必要はないと思いますが、ごく簡単に言うと、大木英夫先生は、丸くつながった山手線を、東洋的な輪廻の思想やギリシア哲学の永遠回帰の思想になぞらえ、一方の中央線は、初めがあり終わりがある、直線的な聖書的歴史観を示すたとえとして用いられました。その分かりやすい違いとして、山手線では、うっかり居眠りをして降りる駅を過ぎてしまっても、また一眠りすれば、ぐるっと回って戻って来る。けれども、中央線で居眠りすると終点まで行ってしまう。そういう誰もが経験しそうなことを織り交ぜながら、ヘレニズム的、ギリシア的な世界観とヘブライズム的、聖書的な歴史観の違いを分かりやすく説かれたのです。しかもそれを、実際に電車に乗っていて居眠りしたときに思いついた、というので、実に愉快な話です。
飯田先生から、大木先生のたとえ話、ほかにもありますか、と尋ねられました。それで、自転車のたとえや、タクシーのたとえをご紹介すると、いたく感動しておられました。今度、使わせてもらいます、とおっしゃった。また、どこかで大木先生のたとえ話が広められていくのではないかと思います。
私たちは、聖書を通して、創世記の天地創造物語から始まってヨハネの黙示録まで、この世界には、始まりがあり終わりがあることを知らされました。それは、その歴史の中に生きている私たちの人生にも、始まりがあり終わりがあることにつながります。東洋的な輪廻の思想においては、私たちが今生きている現世だけではなくて、前世があり、来世があると教えます。現世には確かに、始まりとしての誕生があり、終わりとしての死があるとしても、それは、何度も何度も輪廻の中で繰り返されるのだと教えます。今、こんな不幸な目に遭っているのは、前世で大きな過ちを犯したからに違いない。来世で不幸にならないように、現世で良い行いをして功徳を積んでおこう。そんなふうに人生の教えが説かれます。けれども、聖書的な歴史観を受け継いでいるキリスト教会では、私たちの命が、乗り物としての体を交換しながら、何度も繰り返されるものだとは考えません。私たちの人生は一度限りです。だからこそ、その一度の人生における命はかけがえのないものであり、またそこでの出会いもかけがえのない大切な意味を持ちます。私たちの地上の命には、ただ一度の始まりがあり、ただ一度の終わりを迎えることになるのです。
私たちの多くは、日本の国で生まれて、意識しないままに、仏教的な考え方や教えに馴染んできたのかも知れません。けれども、不思議な導きを得て、聖書に触れて、教会に来るようになりました。さらに聖書のみ言葉を学ぶ中で、この世界と私たち自身に、深く関わっておられるお方があることを知るようになりました。この世界も私たちも、決して、偶然、ここに存在しているわけではないと知りました。私たちを愛して、ご自身に似せて私たちを造ってくださり、私たちを見守り、私たちに呼びかけ、私たちの応答を求めておられる方があると知りました。私たちを愛して、この世界と私たちをお造りになった創造主である神を信じるようになりました。それによって、私たちは、山手線にたとえられる東洋的な世界観から、中央線にたとえられる聖書的歴史観に乗り換えた、と言ってもよいのです。
始まりがあり終わりがあるというのは、もっと正確に言えば、すべてをお始めになり、すべてを終わらせる方がおられるということです。私たちは、そのお方と出会い、そのお方を信じるように招かれているのです。そして、今、私たちが生きているのは、私たちを愛して、私たちに命を与え、存在を与えてくださった方があるからだと知りました。さらに言えば、その私たちが、自らの造り主である神のもとから迷い出て、造り主を無視し、背を向けて、自分が神であるかのように勘違いしていたことを知りました。私たちは、その自らの罪のために、神の御前から失われ、滅びを刈り取るしかない者になってしまったのです。それにもかかわらず、神は私たちを憐れんでくださり、愛してくださって、私たちを罪から解放するために、ご自身の独り子であるイエスさまを救い主として送ってくださいました。御子イエスは、私たちの罪をすべてその身に負って、ご自身の命を犠牲にして、私たちの身代わりとして罪の償いをしてくださいました。さらには、死の力を打ち破り、よみがえって、私たちのために、新たな命の道を開いてくださったのです。私たちは主イエスを信じ、主とひとつに結ばれる洗礼を受けることによって、古い罪の自分に死んで、神のもの、神の子として新しく生まれるのです。
確かに、主イエスを信じて洗礼を受けた者たちは、この地上の命において、すでに新しい命を生き始めています。日々、新たにされる命を生きています。けれども、私たちの肉体は、日々、確実に老いていきます。そして、地上の命の終わりの時として、死を迎えます。もっとも、まだ幼くして、また若くして、厳しい病や思いがけない事故によって命を落とすこともあります。しかし、たとえ長く生き抜いたとしても、ほとんどの人が100年に到達する前に、地上の命を終えて行くのです。誰一人例外なく、この地上に生まれたからには、必ず、地上を去る時を迎えます。遅い早いの違いはあっても、死は確実に私たちのもとを訪れるのです。
この地上の命が、繰り返されることのない一度限りのものであればこそ、死んだ後、私たちがどうなるのか、ということについて、誰もが問いを抱くようになります。その時が近づいてくれば来るほど、この問いは私たちを悩ませることになります。それはもはや「ひとごと」ではなくて、自分自身のことになるからです。今の流行りの言葉で言えば、「自分ごと」として、死を考えざるを得なくなる。死んだ後のことが気になるのです。そんなことを心配する時間もないくらいに、突然の死に襲われる方が幸せだと思う人がいるかもしれません。あるいは、死んだ後のことなど考えても仕方がない。死んだら「無」になるのだと考える人もいます。けれども、信仰をもって生きている者は、決して、死んだら「無」になるとは考えません。むしろ、死は一つの通過点であり、『ハイデルベルク信仰問答』の言葉を借りて言えば、「永遠の命への入口」であると教えられているのです。
最初の教会の優れた伝道者パウロもまた、この私たちが目で見ることのできない生活、死んだ後の生活について、たとえを用いて語ります。死で終わる地上の生活を続けている私たちが、死んだ後、どうなるのかということ、しばしば私たちを悩ませる問いについて、たとえで語るのです。先ほど朗読したコリントの信徒への手紙二の第5章1節と2節をもう一度お読みします。「私たちの地上の住まいである幕屋は壊れても、神から与えられる建物があることを、私たちは知っています。人の手で造られたものではない天にある永遠の住まいです。私たちは、天から与えられる住みかを上に着たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあって呻いています」。「幕屋」「建物」、そして「住まい」という3種類の言葉が用いられます。「地上の住まいである幕屋」という言い方で、私たちの地上の生活は、幕屋での生活のようなものだと言うのです。イスラエルの民は、かつて羊を飼う遊牧民として生きていたとき、幕屋を張ってそこに住みました。移動式のテントです。移動式ですから、簡易なものであり、弱くもろいものでもあります。私たちの地上の生活は、弱く、もろいテント生活をしているようなものだと言うのです。それは、旅人としての生活です。
しかも、2節では、私たちは、この地上の幕屋の中で、呻いていると語ります。後の4節でも同じ言葉を繰り返しています。「この幕屋に住む私たちは重荷を負って呻いている」というのです。新共同訳や口語訳の聖書では「苦しみもだえている」と訳していました。もちろん、日々の生活の中で、さまざまな苦労があり、悩みや痛みがあり、また悲しみや嘆きがあって苦しみもだえている、呻いている、というのは、私たちにもよく分かることだと思います。そして、そのように呻き、もだえ苦しみながら、ついには、死の時を迎えることになるのです。それを1節の冒頭では、「地上の住まいである幕屋が壊れる」と表現しました。私たちの地上の生活、肉体をもってする生活は、決して、永遠に続くわけではありません。やがては終わる時が来るのです。
しかしながら、この地上の幕屋が壊れて、それで終わりということにはなりません。死んだら終わりと言うことにはならない、とパウロは語ります。でもそれは、ギリシア哲学の思想のように、肉体の死は、魂の解放であるということでもありません。死によって、魂は肉体の牢獄から解放されて自由になるというのではない。肉体を脱ぎ捨てたら、魂は裸になってしまうということではありません。パウロは、脱ぎ捨てるのではなくて、むしろ、天から与えられる住みかを上に着るのだと言うのです。私たちが、この地上の幕屋にあって苦しみ呻いているのは、この幕屋を脱ぎ捨てるためではなくて、その上に着ようとしているからだと言うのです。
いったい、何を上に着るのでしょうか。ここでは、「天から与えられる住みか」「天からの住まい」としか、書かれていません。あらゆる朽ちるものに対して、私たちを守ってくれるものを着るということですけれども、それが何であるかについては、はっきりとは書かれていません。ただ「死ぬべきものが命に呑み込まれてしまう」と記されています。死が命に呑み込まれてしまうようなものを着ようとしている、というのです。死を越える新しい命というふうに考えれば、ガラテヤの教会に宛てた手紙の中でパウロが述べている言葉を思い起こします。それをここに重ね合わせることができるかもしれません。パウロは言いました。「キリストにあずかる洗礼を受けたあなたがたは皆、キリストを着たのです」(ガラテヤの信徒への手紙3章27節)。人の手で造られたものではない天にある永遠の住まいを着るというのは、私たちが、この地上にあって、キリストを着ることと言ってよいのです。キリストを着たならば、罪の裸をさらすこともなく、死ぬべきものが命に呑み込まれてしまうことになる。そう考えて良いのではないでしょうか。
私たちは、死んだ後も、無になってしまうわけではありません。肉体という幕屋を脱ぎ捨てて、裸になってしまうのでもありません。私たちの罪をすべて覆うように、義なるキリストをまとわせていただくことで、死によっても空しくなることのない、復活の命を身にまとうことになるのです。確かに、それは、私たちが死んだ後のことに関わります。けれども、この地上の命のある間に、主イエス・キリストを救い主と信じ、主とひとつ結ばれる洗礼を受けることによって、私たちは、死を突き抜けて復活の命に至る救いの道を歩むものとされるのです。死は、永遠の命へと入口となります。洗礼においてキリストを着る。そのことが、確かに私たちの救いとなり、永遠の命の望みとなることを保証するために、神は、私たちに聖霊を与えてくださいました。聖霊なる神が、私たちの信仰の望みを保証してくださいます。保証と訳される言葉のもとの意味は「手付金」ということになります。私たちが自分で考え出して、勝手に望んでいるとしたら、それは不確かなことであり、幻想に過ぎないと言われるでしょう。けれども、私たちにはすでに、手付金として聖霊が与えられているというのです。
復活されたキリストは、今天におられ、私たちは地上にいます。この地上の幕屋の中で呻いています。けれども、私たちにはキリストの霊である聖霊が与えられているのです。聖霊なる神が、キリストと私たちをしっかりと結び合わせてくださり、キリストを着た者として守ってくださいます。聖霊なる神が、私たちの内に働いて、私たちの信仰を確かなものとしてくださり、私たちに愛の実を結ばせてくださり、終わりの日の望みを必ず成し遂げてくださるのです。確かに、キリストを着ていると言いながら、私たちはなおも罪に惑わされ、死に脅かされています。しかし、キリストを身にまとって、天にある永遠の住まいに迎えられる日を、信じ望むように、キリストの霊である聖霊が私たちの内に宿って、私たちをふさわしい者へと造り変えてくださいます。主に喜ばれる者となるように。終わりの日、神の御前に立たせられることを恐れるのではなく、むしろ、喜びをもって待ち焦がれる者となるよう、聖霊は私たちの内に、力強く働いてくださるのです。
6節と8節で、2回も繰り返して「安心しています」と語られます。新共同訳と口語訳では「心強い」と訳していました。今、キリストは天におられ、私たちは地上の幕屋にあるとしても、主はご自身の霊である聖霊において、いつも私たちと共にいてくださいます。だから私たちは心強く、安心することができます。地上を生きる一日一日が、終わりの日の完成につながる歩みであることを思いながら、安心して、今日、この日の業に励むことができるのです。すでに「天から与えられる永遠の住みか」を身にまとい、キリストと共に、天にある信仰の先達たちを覚え、記念しながら、聖徒たちに続く歩みをしっかり刻んでいきたいと願います。