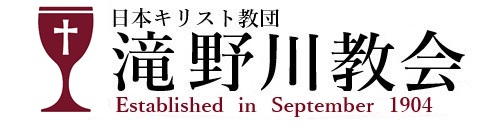2025年10月5日 世界聖餐日 主日礼拝説教「仮住まいの旅人として」 東野尚志牧師
歴代誌上 第29章10~20節
ペトロの手紙一 第2章11~12節
今から45年前のことです。高校を卒業する直前、まだ18歳でした。私は生まれて初めて、ひとりで不動産屋を訪ねて、アパートを借りる契約をしました。4月から大阪の大学に通うために、一人暮らしをすることになったからです。寮生活をしていた京都から大阪まで、一人で合格発表を見に行って、大学合格を確認したその日のうちに不動産屋を訪ねました。家賃や仲介料のほかに敷金や礼金というのがあって、敷金から退去するときの修繕費が支払われて差額が返還されるという説明を受けました。それを聞いたとき、なるべく部屋を汚したり、傷つけたりしないようにして、修繕費が多くかからないようにしようと思いました。大学卒業と同時にまた引っ越すことになると分かっていたからです。
考えてみれば、生まれてからこれまで、一度も持ち家に住んだことがありません。父親は公務員でしたから、官舎で育ち、引っ越しを繰り返しました。大学卒業と同時に編入学した神学校でも寮生活、神学校を卒業して伝道者になってからは、留学の期間を除いて、教会が用意してくださる教師住宅に住んできました。やがて牧師を辞めれば、住宅を出て、新たな住まいを見つけなければなりません。この地上に、帰る家があるわけではないのです。まさに、地上では旅人、仮住まいの身ということになります。
人間とは何かを定義した言葉として、一番よく知られているのは、「ホモ・サピエンス」という言葉だと思います。「知性を持つ人」という意味です。そのほかにも、「ホモ・ファーベル」、ものを作る人、工作人、あるいはまた、「ホモ・ルーデンス」、遊ぶ人、遊戯人という定義もあります。オランダの歴史家ホイジンガの言葉です。人間の特質は、遊びを通じて文化を創造する点にあると捉えました。そんな中で、忘れがたい、心惹かれる呼び名に、「ホモ・ヴィアトール」というのがあります。「旅する人」という意味です。私たちの人生は一つの旅であるというのは、多くの人の共感を呼ぶのではないでしょうか。引っ越しを繰り返してきた身には、実感がありますけれど、たとえ、同じ場所に暮らし続けていたとしても、私たちの人生は、さまざまな出会いや経験を経ながら、生涯、旅を続けていると言って良いのではないかと思います。
ペトロの手紙もまた、先ほど朗読した2章の11節において、「寄留者」「滞在者」という言葉を用いています。「愛する人たち、あなたがたに勧めます。あなたがたはこの世では寄留者であり、滞在者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい」。同じところを、新共同訳聖書ではこんなふうに訳していました。「愛する人たち、あなたがたに勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい」。こちらの方が、直感的に言葉が分かりやすいと思って、今日の説教題は「仮住まいの旅人として」としました。けれども、間違えてはならないと思います。聖書が、私たち信仰者について、「旅人」「借住まいの身」と呼ぶとき、それは、ただ、この地上で定まった家を持たず、転々と引っ越しを続けているということではありません。「この世では寄留者であり、滞在者」であると言うとき、この世を超えたところに、本当の魂の故郷があるということを告げているのです。
すでに、聖書の別の箇所の言葉を思い起こしておられる方があるかもしれません。ヘブライ人への手紙の第11章を見ると、旧約聖書に登場する信仰の勇者たちのことを思い起こしながら、13節以下で告げています。「この人たちは皆、信仰を抱いて死にました。約束のものは手にしませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、滞在者であることを告白したのです。彼らはこのように言うことで、自分の故郷を求めていることを表明しているのです。もし出て来た故郷のことを思っていたのなら、帰る機会はあったでしょう。ところが実際は、彼らはさらにまさった故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです」(ヘブライ人への手紙11章13~16節)。
使徒パウロは、フィリピの教会に宛てた手紙の中で告げています。「しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから、救い主である主イエス・キリストが来られるのを、私たちは待ち望んでいます」(フィリピの信徒への手紙3章20節)。神を信じている者たちの国籍は、この地上にではなく、天にあるというのです。天にある本当の故郷にあこがれながら、そこへ帰る日を目指して、地上ではよそ者のように生きている、というのです。
振り返ってみれば、ペトロの手紙一は、これまでずっと、あなたがた、すなわち、教会につながる私たちが何者であるのか、何者とされているのかを、繰り返し教えてきたのです。キリスト者とは何者か、その正体について描いてきました。人は誰でも、自分が何者であるか、自分の正体をはっきりと理解してこそ、どのように生きるべきかを見いだすことができるのだと思います。自分が何者であるかも分からないままでは、生き方も定まりません。そこでペトロの手紙は、2章9節で「あなたがたは、選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です」と告げて、続く10節において、旧約聖書ホセア書の言葉を引用しながら「かつては神の民ではなかったが 今は神の民」と告げます。そして、2章11節では、これまで述べてきたことを受けとめて「あなたがたはこの世では寄留者であり、滞在者」なのだと告げるのです。そこに信仰者の独特なアイデンティティがあるからです。
新共同訳聖書のように、「旅人」で「仮住まいの身」というふうに訳すと、詩の言葉のような柔らかな感じがします。けれども、聖書のもとの言葉の意味には、もっと激しい意味が込められています。それは元に戻すことのできない、大きな身分の変化を告げる言葉です。私たちの聖書で、「寄留者」と訳されている言葉は、市民権を持っていない異国人を指します。旅人というならまだしも、難民ということにもなります。「滞在者」と訳される言葉は、異郷に一時的に滞在している人を指します。今住んでいる国には国籍を持たない、寄留の外国人としての一時的な滞在者、在留外国人です。かつて、私たちがこの世の民であったときには、この世の市民としての権利を持つ定住者でした。しかし、神の民とされたということは、この世の支配と守りの中から、神の支配に移されたということです。この世は安住の地ではなくなり、一時滞在の場所になったということなのです。この大きな身分の変化を描くとき、使徒パウロは新しい創造、という言葉を用いています。
私たちは、洗礼を受けることによって、自分自身がどのような者となっているのかを、よくわきまえる必要があるのだと思います。神の国の民とされたということは、私たちにとっての本国が、この世界の中のどこかにではなくて、神のもとにあるということです。私たちの国籍は天にあるのです。だから、天に国籍を持つ者として、この地上にあっては、寄留者、滞在者として生きるのです。ペトロは、キリストを信じる者、キリスト者とは何者か、ということについてさまざまな言葉を用いて描きながら、今、そのすべてを締め括るようにして、私たちがこの地上では、旅人であり、仮住まいの身であるということを、改めて強調するように語ります。なぜ、そんなにこだわるのでしょうか。それは、私たちがあまりにも忘れっぽいからです。聖なる神の民とされているにもかかわらず、すぐにそのことを忘れてしまいます。この世に属する者たちと同じように考え、同じように振る舞い、神の民として生きることを忘れてしまうのです。それは、イスラエルの民の歴史の中で繰り返されたことでした。
イスラエルの民は、神によって選ばれ、エジプトの奴隷生活の中から救い出されて、神と契約を結びました。当然、そこから、神のもの、神の民としての生き方を喜んで選び取って行くことを期待されていました。ところが、荒れ野を旅する試練の時代が終わり、約束の地カナンに定住するようになると、神の導きを忘れてしまいます。やがて生活が安定して豊かになり、財産を蓄えて王国を築き、力と富を手にするようになると、高慢になりました。神を信じ、神を頼り、神に従う必要はないと思い始めて、ついには神を忘れ、神に背を向けてしまったのです。それはまた、私たちの身にも起こりうることだと、ペトロは戒めるのです。
先ほどは、ペトロの手紙の言葉に合わせて、旧約聖書に記されたダビデの祈りの言葉を読みました。ダビデは神殿を建てることを志し、すべての準備を整えて、自分の子であるソロモンにその業を託して祈ったのです。その中に、こういう言葉がありました。「私たちの神よ、今こそ私たちはあなたに感謝し、誉れある御名をほめたたえます。取るに足りない私と、私の民が、このように自ら進んで献げたとしても、すべてはあなたからいただいたもの。私たちは御手から受け取って、差し出したにすぎません。私たちは、先祖が皆そうであったように、あなたの前では寄留者であり、滞在者にすぎません」(歴代誌上29章13~15節)。地上における莫大な富も、献げ物も、すべては神さまからいただいたものであり、それを神の御手から受け取って、差し出したに過ぎない、と語ります。莫大な献げ物を誇るのではなく、神の恵みを誇る。それは、自らが地上においては、寄留者であり、滞在者であることを心得ているからです。すべては神から出ており、神に献げるべきもの。この世の過ぎ去る富に惑わされることなく、神のものとして生きる確かさがここにあります。それは、ペトロの手紙の言葉に響き合います。
ペトロは語ります。「愛する人たち、あなたがたに勧めます。あなたがたはこの世では寄留者であり、滞在者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい」。「肉の欲」と言えば、私たちはすぐに、肉体的な欲望のことと思うかも知れません。けれども、その内実は、この世での喜びや楽しみに心奪われ、地上での成功や富を求めることだと言ってよいと思います。神のご支配のもとに移されて、神の民とされているにもかかわらず、なおもこの世に定住する者のように、この世の富や力を求め続けているならば、私たちも忘れてしまいます。この世では旅人であり寄留者であることを忘れてしまう。私たちの本国である天に憧れ、天を目指す巡礼の旅を生きていることを忘れてしまう。大切な旅の目的を忘れさせてしまうような、この世の誘惑を退けるようにと、ペトロは勧めます。この見える世界に最後の望みを置くのではなくて、天を仰ぎ、神に望みを置いて生きるようにと勧めます。主イエス・キリストがそこからお出でになる、天に望みを置いて生きるのです。
続けてペトロは語ります。「また、異教徒の間で立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らはあなたがたを悪人呼ばわりしていても、あなたがたの立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります」。天に望みを置き、天を仰いで生きる旅人の歩みは、「訪れの日」に備える生き方となります。主が再び来られるときには、すべての者が神を崇めるようになることを望み見ながら、迫害や誤解に耐えて、証しの生活を刻んでいくのです。ここで言う「立派な行い」というのは、主の日毎に礼拝を献げる、礼拝者としての営みを指すと言って良いと思います。主の日の礼拝を守ることにも、さまざまな誘惑が忍び寄ります。神を信じない人たちにとって、毎週、毎週、日曜日の朝、礼拝へと出かけて行く生き方は、理解に苦しむでしょう。しかし、そこにこそ、神を信じる者にとって、最も喜ばしい、また祝された神との生きた交わりがあります。信仰を同じくする者たちとの喜ばしい交わりがあります。神にかたどって造られた人間の、最もふさわしい生き方がそこにあるのです。
旧ソ連の圧制のもとで迫害に耐えて伝道し、多くの受洗者を生んだロシア正教会の司祭であり長老でもあったアレクサンデルという人がいました。この人は、人間というのは何よりも「ホモ・リトゥルギクス」だと教えました。「ホモ・リトゥルギクス」というのは、「礼拝する人、礼拝する人間」ということです。礼拝に常にあずかっている人は、その顔つきまで変わり、声まで変わると教えたのです。一週間の中に主の日が備えられ、自分の業を止めて神の業にあずかる、この礼拝の一日が備えられることによって、私たちの全生涯が変えられていくのです。神さまは、私たち人間が、神を礼拝する者、「ホモ・リトゥルギクス」として生きるように求めておられるのだと思います。そのために、七日ごとに礼拝の日を備え、私たちを礼拝へと招いてくださるのです。主の日から主の日へ、礼拝から礼拝へと導かれながら、神のもの、神の民、天の故郷を目指す巡礼者としての歩みが整えられていくのです。信仰の旅路を続けていくのに必要な糧を、主は礼拝において与えてくださいます。感謝と喜びをもって、主のもてなしにあずかりたいと思います。