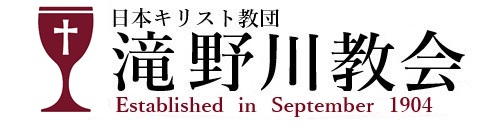2025年10月26日 宗教改革記念礼拝説教「キリストの足跡に続く」 東野尚志牧師
イザヤ書 第53章1~12節
ペトロの手紙一 第2章18~25節
毎年、10月最後の主日と11月最初の主日は、教会の過去を振り返る特別な礼拝が続きます。本日は、宗教改革記念礼拝、そして、次週の主日は召天者記念礼拝を行うのです。時は、16世紀の初めに遡ります。すでに、教会では11月の最初の日、つまり11月1日、天に召された聖徒たちを記念する礼拝を行うようになっていました。もともとは殉教者や聖人を記念して個別に行われていたのが、8世紀頃には11月1日に、すべての聖人を記念するようになっていたと言われます。やがて、11月1日は、All Saints’Day、「諸聖人の日」という祝日になります。そして、翌日の11月2日はAll Souls’Day、「諸魂の日」と呼ばれて、信仰をもって亡くなったすべての人の魂を記念する日となります。とりわけ、祝日である諸聖人の日、11月1日には、教会に出かけて礼拝をすることが重んじられるようになっていきました。
ドイツのヴィッテンベルクのお城の教会にも、11月1日、多くの信徒たちが遠くから近くから巡礼にやって来ました。教会の中に、聖人たちが遺した聖遺物が収められていて、この日に巡礼をすると、何十回分もの巡礼に相当する功徳があるとされていたのです。もっとも、そのような功徳を求める呪術的な信仰は、やがてプロテスタント教会によって否定されることになります。ローマ教会の熱心な修道僧であったマルティン・ルターは、11月1日に多くの巡礼者が集まるのに目をつけて、その前の日、10月31日に、95ヶ条の提題をお城の扉に掲示したのだと言われます。できるだけ多くの人に見てもらうためです。当時のローマ教会が、大聖堂修理の資金集めのために、贖宥状、いわゆる免罪符というお札を売り出したことを批判して、95ヶ条にわたる問題提起を公にしたのです。まるで罪の赦しをお金で買うことができるかのような教えは、キリストの十字架による赦しの恵みを貶めるものと思われたのです。この95ヶ条の提題をきっかけにして、ドイツから始まりヨーロッパ全土を巻き込んでいく宗教改革運動が起こりました。その結果、ローマ教会から分かれた、プロテスタント教会が生まれることになったわけです。
ルターが、95ヶ条の提題を公にした1517年10月31日は、後にプロテスタント諸教会において、宗教改革記念日として覚えられるようになります。そして、聖人崇拝を否定したプロテスタントは、11月の最初の日曜日を、天に召されたすべての信徒たちを記念する日として祝うようになります。私たちの教会が属している日本基督教団は、そういう歴史を受け継いで、一年の行事暦の中、10月31日を「宗教改革記念日」、11月第1主日を「聖徒の日(永眠者記念日)」と定めました。もちろん、この場合の「聖徒」は、いわゆる「聖人」ということではありません。新約聖書における「聖徒」「聖なる者たち」という呼び名を受けて、キリストに結ばれたすべての信徒たち、すべてのキリスト者を意味します。天に召された信仰の先輩たちを記念するのです。
私たちの教会は、毎年、宗教改革記念日である10月31日の直前の日曜日の礼拝を、「宗教改革記念礼拝」として位置づけています。そして、続く11月最初の日曜日には、天に召された教会の仲間たちを覚えて、「召天者記念礼拝」を行うのです。合わせて午後には、教会墓地に出かけて、墓前礼拝を行います。教会の歴史を振り返り、信仰の先達を記念する特別な礼拝が続く中で、今日は、ペトロの手紙一の第2章、18節から25節の御言葉を読むことになりました。今日は特に、21節に記された「模範」という言葉に目を留めていただきたいと思います。「模範」というのは「お手本」ということです。「その足跡に続くようにと、模範を残された」とあります。私たちは、信仰の先達を覚え、また模範として、遺された足跡に続くように歩んでいるのです。
一面の雪に覆われた銀世界をご覧になったことがあるでしょうか。私は昔、神学校の卒業旅行でクラスの仲間と一緒に万座温泉に出かけたときのことを思い出します。朝起きて外に出ると、夜の間に雪が降り積もって、どこが道路でどこが畑か分からないくらいに、一面の銀世界。いくつも温泉があって、外に出て別棟の温泉に出かけるとき、一番乗りをするのは緊張します。初めての場所で、降り積もった雪の下がどうなっているのか分からないのです。道路の端が分からないと、うっかりして溝に落ちてしまうかも知れません。でも、先に歩いた人の足跡が残っていれば安全です。雪を踏みしめた足跡に自分の足を重ねるようにして歩いて行けば、決して、溝に落ちることはありません。先に道を付けてくれた人がいれば、安心してその跡を辿っていくことができるのです。足跡に続く、という場合の一つのイメージです。
もちろん、雪道だけではありません。少し前に「国宝」という映画が話題になって、私も妻と一緒に観に行きました。歌舞伎の世界が描かれています。芸の道には必ず師匠がいます。師匠に弟子入りすると、弟子は師匠をお手本にして、足の運びや手の動き、首の動かし方まで、師匠の真似をすることから基本を身につけるのです。ただ技術を磨けばそれでよいということにはなりません。師匠の芸を通してその生き方にも倣いながら、芸の道を深めていきます。生きた模範、お手本がすぐ側にいてくれるのです。歌舞伎だけではありません。お花やお茶にしても、あるいは、書の道にしても、また音楽にしても、すべて最初は、師匠の真似をすることから始まるのだと思います。学ぶことはまねぶこととも言われます。すべての学びはまねることから始まると言ってよいかもしれません。
信仰の道にも似たようなところがあると思います。初めて礼拝に出たとき、何をどうしてよいのか全く分からずに途方に暮れるかも知れません。けれども、まずは、隣りに座ってくれた人や、前に座っている人の真似をすることから始めるのではないでしょうか。讃美歌を歌うとき、その人が立てば一緒に立ちます。お祈りをするときも、隣の人と同じようにしていれば間違いはありません。そうやって、礼拝の流れの中に身を置いて、すでに礼拝することを身に着けている人たちの真似をすることから始まります。ただし、同じように聖餐を受けることだけはできないので、ちょっと寂しい思いを味わうかもしれません。そこは申し訳ないところです。
何回か礼拝に来るようになり、祈祷会にも出て、初めて自分でお祈りするときも、それまでじっと聞き続けてきた他の人たちのお祈りの言葉を真似ることから始まるのではないでしょうか。中学生くらいの人が、「御在天の父なる神さま」なんて難しい言葉で祈り始めると、ちょっと微笑ましく感じたりします。ああ、祈りの言葉が受け継がれているなあ、と思います。一人で聖書を読んで学んでいればよいというのではなくて、信仰の先輩たちと一緒に聖書を読み、一緒に祈りを合わせ、一緒に過ごしていく中で、信仰に生きる道を学び、御言葉を生きる道をなぞっていくのです。お手本は周りにたくさんあります。実は、自分がお手本にしている人も、かつてはそのまた先達をお手本にして学んだはずです。そうやって、ずーっと遡って辿っていけば、主イエス・キリストまでつながります。ペトロは言います。「あなたがたは、このために召されたのです。キリストもあなたがたのために苦しみを受け、その足跡に続くようにと、模範を残されたからです」。信仰における模範やお手本は、イエス・キリストにまでつながります。そうでなければ、それは、何か異質なものが入り込んで、途切れていることになります。一番最初の模範が、忠実に受け継がれていることが大事なのです。
ペトロはここで、特に、主イエス・キリストが受けられた苦しみについて語っています。今、苦しんでいる者たちに、理不尽な苦しみに耐えている者たちに、神の独り子であるイエス・キリストが、私たちのために受けてくださった苦しみを思い、その足跡に続いていくようにと促すのです。ペトロは勧めます。18節、「召し使いたち、心から畏れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、気難しい主人にも従いなさい」。この段落に続く第3章の1節にも、同じような勧めが記されています。「同じように、妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためです」。どちらも「従いなさい」と勧めています。しかも、心から尊敬できて、喜んで従いたくなるような相手に従えというのではありません。むしろ、気難しくて理不尽な要求をする厄介な主人に対しても、いやいやではなく、心から恐れ敬って従うのです。優しくて理解のある夫だけでなくて、むしろ、御言葉に従わず、妻の信仰を快く思っていないような理解のない夫に対しても従うようにと言うのです。
ここに出てくる「召し使い」というのは、身分としては奴隷ですけれども、家の労働に携わった奴隷のことを言います。戦争に負けて捕虜になった人たちが、個人の家に買われて家事に仕えたのです。当時のローマ帝国には、数千万人の家事奴隷、「召し使い」がいたと言われます。国が戦争に負けて捕虜になる前は、自由人として暮らしていた人たちです。自分の国では、学者や医者として活躍していた人もいたでしょうし、芸術家もいれば、法律や財政の専門家もいたはずです。ですから、家の奴隷として働くときも、子どもの家庭教師として学問や習い事を教えることを命じられる人もいれば、家の財産管理や会計の仕事を委ねられる人もいたようです。その才能が認められて大事にされる場合は幸いです。けれども、そうでないこともあります。主人よりも学問があり、教養があり、あらゆる面で自分の主人よりも優れた能力を持つ奴隷もいたわけです。それがかえって災いして、主人に妬まれ、わざと意地悪される人たちもいたのです。その理不尽な仕打ちに耐えなければなりませんでした。
家の中で何かトラブルが起これば、何でも召し使いのせいにされてしまいます。何かものが無くなれば、真っ先に召し使いが犯人と疑われて、否応なしに鞭で打たれる。後から無くした物が出て来ても、主人は謝りもしません。何か主人の気に入らないことがあれば、怒鳴りつけられ、叩かれ、蹴られもする。奴隷は主人の持ち物と見なされていましたから、不当な扱いを受けても我慢するしかありません。無慈悲で気難しい主人に買われてしまった不運を嘆きながらも、扱いがさらに悪くならないように、主人に忠実に仕える振りをする。でも、心の中では主人を馬鹿にしたり、蔑んだりすることで、自分を慰めるしかなかったのではないでしょうか。そういう奴隷たちの中には、救いを求めて、キリスト者の集まりに顔を出す人たちがいたのだと思います。どうやって、理不尽な現実の中で生きていけば良いのか、どこに生きる意味を見いだせばよいのか、必死に求めていたのではないでしょうか。
それは、二千年前の奴隷たちだけの話ではないと思います。現代の私たちもまた、同じような苦しみを味わうことがあるのではないでしょうか。確かに、現代の日本に、奴隷という身分はありません。けれども、会社や学校で、あるいは親戚付き合いやご近所の人たちとの交わりにおいて、すぐに自分が上に立って、人を見下したり、支配しようとしたりする人がいます。身分としての奴隷ではなくても、奴隷のようにこき使われて、不当な苦しみを味わうことがあると思います。相手の方が明らかに間違っているのに、それを指摘するとかえって根にもたれて、意地悪されたりする。どうして自分がこんな目に遭わなければならないのか、自分の境遇を嘆きながら、理不尽な力関係の中で、それを変えることもできず、苦しみに耐えるしかないことがあるのです。
そんなとき、ペトロが召し使いに対して告げた言葉を、改めて、しっかり味わいたいと思います。気難しい主人にも従うようにと命じた後、ペトロはその理由を告げます。19節と20節です。「不当な苦しみを受けても、神のことを思って苦痛を耐えるなら、それは御心に適うことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも、何の誉れになるでしょうか。しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心に適うことです」。「御心に適うこと」という言葉が2回繰り返されています。新改訳の聖書では「神に喜ばれること」と訳しています。かつての口語訳聖書は、「それはよみせられること」と訳しました。実は、聖書のもとの言葉一つの単語です。「カリス」。通常は、「恵み」と訳される言葉です。「善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の恵みです」と告げているのです。理不尽な扱いに文句を言うのではなく、黙ってそれを耐え忍ぶこと、それは「恵み」なのだと言うのです。なぜなら、そこでこそ、私たちは、主イエス・キリストの苦難とつながることができるからです。主の足跡に続く者となるのです。
自分自身が「不当な苦しみ」を耐え忍ぶことによって、初めて分かることがあるのです。それを語っていくのが、22節以下の言葉です。ここを読んで、あのイザヤ書53章に描かれた「苦難の僕の歌」と良く似ていることに気づかれたと思います。明らかに、ペトロは、預言者イザヤの言葉を思い浮かべながら、私たちのために、不当な苦しみを背負ってくださった主イエスのお姿を描くのです。「『この方は罪を犯さず その口には偽りがなかった。』罵られても、罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に委ねておられました」。主イエスがお受けになった苦しみを、苦難の僕、苦難の奴隷の姿として描きます。自分は少しも悪くないのに、理不尽な仕打ちを受けて苦しめられる中から、主イエスの十字架の苦しみを仰ぎ見るようにと指し示すのです。
「この方は罪を犯さず その口には偽りがなかった」。そうです。キリストは、ただ一人、生まれながらに罪のないお方でした。そのお方が罪人とされたのです。私たちの罪を背負ってくださったのです。そして、罪人として神から見捨てられてくださった。本来ならば、私たちこそが、神に背いた罪人として、神から見捨てられ、裁かれなければならない者であったのです。けれども、私たちを罪の裁きから救うために、罪のないお方が、罪人として裁かれる理不尽な苦しみを引き受けてくださったのです。「不当な苦しみ」を理不尽に受けたというなら、誰よりも、キリストこそが、不当な苦しみを受けながら、それを父なる神の御心として受けとめて、神から見捨てられる絶望的な苦しみを完全に味わい、耐え忍んでくださったのです。
私たちは、案外、のんきなところがあります。頭で分かったつもりでも、体で分かっていないところがあります。罪のないお方であるキリストが、私たちに代わって罪を背負ってくださった。十字架の苦しみを担ってくださった。口ではそう言いながら、それがどういうことであるか、よく分かっていない。けれども、不当な苦しみが自分の身に降りかかって、自分自身のこととして忍耐を迫られるとき、その苦しみに耐える涙の中から、初めて、イエス・キリストの十字架の苦しみのほんの一部でも、分からせていただくことができるようになる。だから、それは恵みだと言うのです。「罵られても、罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に委ねておられました。そして自ら、私たちの罪を十字架の上で、その身に負ってくださいました。私たちが罪に死に、義に生きるためです。この方の打ち傷によって、あなたがたは癒やされたのです」。アーメン。イエスさま、ありがとうございます。そう言って、十字架の主の前にひれ伏すとき、私たちの救いを歌う賛美の歌が聞こえて来ます。「あなたがたは羊のようにさまよっていましたが、今は、魂の牧者であり監督者である方のもとへ立ち帰ったのです」。
理不尽な苦しみに耐えることの中で、主の十字架の苦しみを思い、主の足跡に従っていくならば、私たちは、その苦難を突き抜けて、復活の勝利にあずかるものとされます。主イエス・キリストこそは、苦難に耐える者の模範であり、復活の模範でもあります。信仰のみ。恵みのみ。キリストのみ。改革者たちが残した足跡を踏みしめながら、主に従い行く恵みと祝福を分かち合いたいと願います。