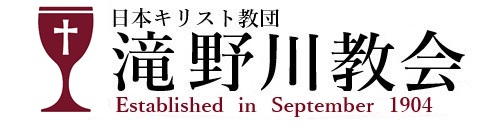2025年10月19日 主日礼拝説教「キリストの支配のもとに」 東野尚志牧師
箴言 第24章17~22節
ペトロの手紙一 第2章13~17節
私たちが日頃、聖書を開いて読んでおりますと、自分の心に突き刺さるような言葉と出会うことがあります。聖書全体の中で、その言葉が浮かび上がるようにして、心に響いてくるのです。そういう言葉に出会うとうれしくなって、自分の聖書に線を引く人もいるでしょう。書き抜いてよく見えるところに掲げたりするかもしれません。しかし、そうかと思えば、逆に、聖書の中に、どうしてこんな言葉があるのだろうと思って、戸惑いを覚えるような箇所にぶつかることもあるのではないでしょうか。もしかすると、今日、私たちに与えられた聖書の言葉も、すんなりとはのみ込めない、戸惑いを覚えさせる言葉のひとつであるかもしれません。
「すべて人間の立てた制度に、主のゆえに服従しなさい」と命じられています。「神に服従しなさい」「神の言葉に従いなさい」というのであれば分かります。しかし、ここでは、人が立てたすべての制度に従うようにと命じられているのです。それがどのようなものを指しているのか、続けて具体的に記されています。「それが、統治者としての王であろうと、あるいは、悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるために、王が派遣した総督であろうと、服従しなさい」。神ではなくて、王や総督など、この世の権威に服従するようにと命じるのです。
ペトロの手紙が書かれた時代は、すでに、ローマ帝国の権力によって、教会が厳しい迫害にさらされていたと考えられます。ローマ皇帝を神として崇めることが強要される中で、主イエスを神として告白している教会は、ローマの支配に逆らうものとみなされました。皇帝を神として礼拝することを拒んだ者たちは、牢に入れられ、容赦なく命を奪われました。ローマ皇帝かイエスか、どちらが神か、という問いにさらされたのです。
それは、決して、二千年前の遠いところの話ではありません。この日本においても、16世紀の終わりから17世紀にかけて、イエス・キリストを救い主として信じる人たち、いわゆるキリシタンに対して、厳しい迫害が行われました。明治の初めになっても、250年続いたキリスト教の禁止令は、なおそのまま残されていました。密かに信仰を守り続けていた潜伏キリシタンたちが、捕らえられ殺されたのです。諸外国の抗議を受けて、キリスト教禁止の高札が撤去されたのは、明治の代になって6年もたってからのことでした。
さらに、今から80年前、第二次世界大戦の敗戦を迎えるまで、戦時体制の中で、キリスト教は敵性宗教と見なされました。天皇のキリストとどちらが偉いかと問われて、キリストへの忠誠を貫いた牧師たちは逮捕され、多くの人が獄中で命を落としています。国家や政治的権力の支配に対して、キリスト者どのように対処すればよいのか、これは、キリストの教会がこの世にある限り、避けて通ることのできない問題であると言えます。
そういう中で、ペトロの手紙は、政治や権力による人間の支配に対して、キリストを主と崇めるキリスト者はどのような態度をとるべきかを教えます。キリスト者の生き方を指し示すのです。少し遡ってみると、すでに、その大前提となる私たち信仰者の現実、実存についてはっきりと描かれていました。今日の箇所に先立つ、第2章11節と12節の言葉をご覧ください。「愛する人たち、あなたがたに勧めます。あなたがたはこの世では寄留者であり、滞在者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らはあなたがたを悪人呼ばわりしていても、あなたがたの立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります」。
私たちは皆、かつてはこの世に属する者たちでした。けれども、イエス・キリストを信じて、キリストとひとつに結ばれる洗礼を受けた者たちは、教会に加えられ、神の民の一員とされます。キリストを信じる者たちは、この世に属する者ではなく、神に属する者となりました。パウロの言葉を借りれば、天に国籍を持つ者となったのです。だからこそ、この世にあっては、寄留者、旅人であり、一時的に滞在しているに過ぎない者とされています。私たちは、やがて、本当の故郷である天に帰るのです。この世において、異教徒たちに囲まれながら生きるキリスト者に対してペトロは勧めました。「異教徒の間で立派に振る舞いなさい」。「立派に」という言葉は、「美しい」と訳される言葉でもあります。キリストを信じる者たちが、この世にあって美しく生きる。その道を、具体的に描いていく中で、まず初めに、避けて通ることのできない現実、この世の政治的な権力に対して、どのように対処すべきかを説いていくのです。
「すべて人間の立てた制度に、主のゆえに服従しなさい」。ここで「制度」と訳されているのは、「造られたもの」を意味する言葉です。私たちがこの世で生きていくために造られた、さまざまな仕組みを指しています。そういう仕組みの最初に取り上げられたのが、政治の仕組み、国家との関わりということになります。政治的な支配者に対する態度について勧めました。「それが、統治者としての王であろうと、王が派遣した総督であろうと、服従しなさい」。実は、この後も、私たちを取り巻くさまざまな制度、仕組みを取り上げていくことになります。2章の18節以下では、「召し使いたち」という呼びかけの言葉から分かるように、主人に仕えている僕が、その主人に対してどのような態度を取ればよいのかを語ります。そして、第3章に入ると、1節に「同じように妻たちよ」と呼びかけられています。妻が夫に対してどのように生きたら良いのかが語られていくのです。つまり、まずは国家の権力や政治的支配者に対して、続いて、僕が主人に対して、さらに妻が夫に対してというように、政治的・社会的な仕組みや結婚の仕組みについて語って行きます。それを「制度」と呼んでもよいし、「秩序」と言い換えることもできると思います。
つまり、冒頭に掲げられた「すべて人間の立てた制度に、主のゆえに服従しなさい」というのは、その全体に及ぶ原則を述べていると考えることができます。引き続いて語られていく政治の制度や社会の制度、結婚の制度、それはいずれも、人間が立てた制度ですから、決して、完全なものではありません。いや、むしろ、そこには欠けがつきまとっています。なぜなら、私たち人間は皆、罪を負っているからです。人間が立てた制度には、罪による欠けや弱さが染みついているのです。だからこそ、「服従しなさい」と言われても、簡単には納得できない反発を覚えるのは当然かもしれません。特に、昨今の政治の混乱や、節操のない多数派工作、庶民の苦しみを見ないで権力にすり寄って私服を肥やす政治家たちを見ていると、ため息が出ます。王や総督といった統治者たち、今日で言えば、大統領や首相、政権についている者たち、また裁判官も警察権力も、人間がそれを担う以上、罪があり欠けがあります。冤罪も起きるのです。それでも、無秩序な無政府主義よりはよほどましと言わなければなりません。奴隷にとっての主人も同様です。18節ではわざわざ「善良で寛大な主人にだけでなく、気難しい主人にも従いなさい」と告げています。夫もそうです。「たとえ御言葉に従わない夫であっても」と語ります。いつも優しくて、穏やかな夫だけでなく、御言葉に従わず、妻が教会に行くことを快く思わない夫、すぐ不機嫌になってしまう夫であっても、自分の夫に従いなさい、と言うのです。この箇所は、いずれ改めて、詳しく読むことになります。
つまり、尊敬すべき、立派な支配者、立派な主人、立派な夫であるから服従せよ、と言うのではありません。むしろ、そうではない相手に対しても服従することで、異教徒の間で、美しい証しを立てることになるのだと言うのです。ただし、すべて無条件に、服従しなければならないということではありません。たった一つだけ、どうしても守らなければならない条件があります。それは、「主のゆえに」という一句にかかっています。どうして、私たちは、人間が立てた制度に従わなければならないのか、それは「主のゆえに」だと言うのです。敵をも愛されたキリストの愛のゆえにです。新共同訳聖書では、これを「主のために」と訳しました。私たちが、すべて人間が立てた制度に服従するのは、主のため、主の栄光のためであるというのです。
人間が立てた制度であれば、決して、永遠のものではありません。それもまた、時代に応じて変わっていくものであり、過ぎ去ることもあります。新しい制度が立てられることもあるのです。しかし、その制度の中で、悪を行う者が処罰され、善を行う者が褒められることがなされているならば、その制度に従うことは神の御心にかなうのだとペトロは語ります。「善を行って、愚かな人々の無知な発言を封じることが、神の御心だからです」と告げるのです。大事なことは、主のゆえに、主のために、そして、神の御心によって、です。だから、もしも、この世の権力が、私たちに対して、神の御心に逆らうことを強いるならば、その権力に従い続けることはできません。ここに、キリスト者の抵抗権の余地が生まれます。この世の権威や力が、明らかに、神の御心に逆らい、私たちを主イエスから引き離そうとするなら、相手がどのように強大な力を誇っていても、抵抗する勇気を持たなければなりません。この世の権威に逆らわなければならない事態が生じることもあるのです。
いずれにしても、大事なことは、私たちがこの世の権威に従い、この世の制度や仕組みに従うとき、この世の奴隷になって、卑屈な思いを抱きながら、強いられて、いやいや従うということであってはならないということだと思います。御言葉は、むしろ、「自由人として行動しなさい」と告げています。私たちは、強いられて、いやいや従うのではなくて、自由に自分で選び取って、この世の支配や制度、秩序に従うのです。自分から進んで、主のゆえに、主のために、この世の権威に従う。奴隷は主人に従う。妻は夫に従う。自由な人間として服従するようにと言うのです。そう言いながら、聖書は、この自由というのが、正しく行使することの実に難しいものであることをよく知っています。だからこそ、「自由人として行動しなさい」と告げた後、続けて語ります。「しかし、その自由を、悪を行う口実とせず、神の僕として行動しなさい」。この世の支配から解放されて自由になった。だから、自分の思うままに生きて良い、というのではありません。むしろ、神の僕として生きることを求めるのです。聖書は、私たちが、神の僕、神の奴隷として行動することこそが、真実な意味で自由な人として生きる道であると語るのです。
キリストのものとされたキリスト者は、神こそがまことの主人であり、自分は神に仕える僕とされていることを知ります。そして、神を主人として生きることを知った者は、他の一切の主人から自由にされているのです。しかし、そこに勘違いが忍び込んできます。自分は本当の主人と出会った。だから、これまでの主人にはもはや従う必要はないと考えてしまう。神を知らない愚かな者たちに従う必要はない。石破さんはキリスト者だから、まことの神を知っている。けれども、今度、首相になるかも知れない高市さんは、本当の神を拝むことを知らず、自分を神としている愚かな存在だ。私が仕えている上司は、気難しくて自分の不満を部下にぶつけて苦しめるだけの存在だ。まことの神を知らない愚か者である。あるいは、私の夫は、まるで私のことを家政婦か何かのように、奴隷のように見ているけれども、あれは神を信じていない怠け者だ。自由を得たとたんに、自分の周りの他の人たちを軽蔑し、軽んじ始める。信仰を持たないということで、神を知らないということで、自分よりも劣った存在のようにひとを見下すようになる。ペトロの教えがあるから、一応は従う振りをするけれども、それは表面的なことで、心の中では相手を蔑んでいる。しかし、それは、自由をはき違えている。ペトロはそう言うのです。与えられた自由を、悪を行う口実にしてはならない、と言うのです。
そして、この段落全体を締めくくるようにして勧めを語ります。17節です。「すべての人を敬い、きょうだいを愛し、神を畏れ、王を敬いなさい」。これこそが、神の僕となることで、本当の自由を味わい知った者の生きる道だと説くのです。「すべての人を敬いなさい」。ここで言う「すべての人」というのは、文字通り、すべての人です。そこには、何の条件付けもありません。自分が尊敬したいと思う人だけを敬って、そうでない人を低く見るというのではありません。人種や身分、家柄や出自、奴隷か自由人か、男か女かといった区別に拠らずに、お互いを敬う、リスペクトする。その根拠はどこにあるでしょうか。神がすべての人を造られたのです。神はキリスト者だけを造ったのではありません。神がすべての人を造り、キリストはすべての人の罪を背負って、十字架に死なれました。その人が自覚しているかどうか、信じているかどうかにかかわらず、キリストはすべての人の救い主です。相手に腹を立てるとき、相手を見下してしまいそうになるとき、私たちは、思い起こすのです。キリストは、このきょうだいのためにも死なれたのだ。私のためだけでなく、今はまだキリストの救いを信じていないこの人のためにも死なれた。だからこそ、すべての人を軽んじることなく、すべての人を、キリストが重んじておられる存在として敬うのです。
「きょうだいを愛し」と続きます。「きょうだい」とひらがなで書かれているのは、男性だけでなく女性も含めて、兄弟姉妹すべてを指しています。教会の仲間、信仰の仲間の間で、互いに愛し合い、仕え合いながら、神の民として共に歩むことを意味します。私たち教会の交わりの中にも、尊敬すべき信仰の先達が数々おられます。その信仰の証しに倣い、その愛の業に学びたいと思います。愛するというのは、互いに無関心ではいないということです。喜んでいる人と共に喜び、悲しんでいる人と共に悲しみます。だからこそ、助けを必要とする兄弟姉妹の傍らに寄り添って祈り、群れから離れてしまった者たちのことを覚えて、主の前に執り成し、互いに支え合う仲間として生きるのです。
さらに、「神を畏れ、王を敬いなさい」と勧めます。先ほど、合わせて朗読した旧約聖書箴言の中では、「主と王を畏れよ」と勧められていました(箴言24章21節)。イスラエルの社会では、神が王を選び立て、王は神の権威を担いました。だからこそ、主なる神と王は一体となって「主と王を畏れよ」と告げられます。けれども、この世の王は、神を知りません。だからと言って、軽蔑して、無視して良いのではなく、「王を敬いなさい」と勧めます。これは、特別ではなく、「すべての人を敬い」というときに用いたのと同じ言葉です。しかし、神は、ただ敬うだけの存在ではありません。「神を畏れ」よ、と言うのです。神はただ一人、私たちが信じ畏れ、礼拝すべき方なのです。
ある人が言いました。「神を畏れる者は、神以外の何ものをも恐れないが、神を畏れない者は、神以外のすべてのものを恐れる」。まことの神を信じ畏れている者は、地上の旅路において、何が起こっても、恐れることはありません。しかし、神を知らない者は、すべてのものを恐れる。この場合は、恐怖を意味する恐れでしょう。ヨハネの手紙の中に印象深い言葉があります。「愛には恐れがありません。完全な愛は、恐れを締め出します。恐れには懲らしめが伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです」(ヨハネの手紙一4章18節)。神を信じ畏れ、神を愛する者は、この世の権威や秩序による力を、いたずらに恐れる必要はありません。神から与えられている自由をもって、この世の秩序を守り、上に立つ者を敬い、敬意を持って従うのです。ひとの目を気にすることなく、神の御前に、神に愛されている神の僕として、神の目に恥じることのない歩みを求めて行きたいと願います。