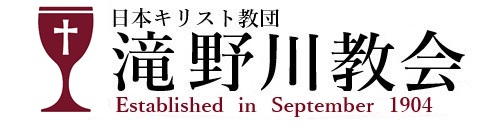2025年8月24日 主日礼拝説教「神の言葉によって、新たに生まれる」 東野尚志牧師
イザヤ書第40章6~8節
ペトロの手紙一第1章22~25節
もう今から 45 年前のことになります。1980 年の春、私は、京都にあります仏教系の高校を卒業して、大阪の大学に入学しました。大学に入って間もない頃のことです。キャンパスの中を歩いていると、数名の学生に声をかけられました。何かのサークルの勧誘であったと思います。呼び止められて、一枚の絵を見せられたのです。45 年も前に、一度見たきりの絵です。けれども、その絵は、今もくっきりと、私の心に焼き付いています。
こういう絵でした。――断崖絶壁。その崖っぷちに、一本の木が生えています。木の枝が、崖の下に低く垂れ下がっています。その枝の先に、一人の男がぶらさがり、しがみついているのです。崖の上には、お腹を空かせた虎が大きな口を開けて迫っています。一方、崖の下には沼があって、こちらにはまた、大きなわにが口を開けて待ち構えているのです。力尽きて、手を放してしまえば、そのまま、わにの口へと落ちて行きます。しかしまた、力を振り絞って木によじ登り、崖の上に上がれば、虎の餌食になります。まさに絶体絶命の状況です。さらにやっかいなことがありました。この男が必死にすがりついている木の根っこを、白いねずみと黒いねずみが交互にかじっているのです。
ところが、この危機的な状況において、男は別のことに気を取られています。必死に木の枝にすがりつきながらも、その枝の付け根にある蜂の巣から滴り落ちる蜜をなめて、うっとりとしている――そういう絵です。
これは、私たち人間の生の現実を現した絵である、と聞かされました。今にして思えば、仏教の教えを絵に現した仏画の一つであったと思います。いろんなヴァージョンがあるようです。大事な役割を演じているのは、白いねずみと黒いねずみです。白いねずみは昼、黒いねずみは夜を現わします。昼と夜が交互に繰り返しながら、一日、一日と時は過ぎて、私たちは確実に、死へと追いやられていきます。もちろん、途中で力尽きれば、すぐにでも死んでしまいます。手を放せば、落ちて行くのです。待ち構えた死の口に飲み込まれてしまいます。けれども、必死に耐えていたとしても、時は確実に過ぎ去ります。そして、必ず死の時を迎えることになるのです。
ところが、そのようにして、日々刻々、死へと向かう存在であるにもかかわらず、ひとときの空しい快楽に酔いしれて、自分自身をごまかして生きている。死を忘れて生きている。それが、私たち人間の生の現実だというのです。私たち人間は死すべき存在であり、死に向かって生きているということ。それは、誰も否定することのできない事実です。それにもかかわらず、普段はそのことをあまり意識していないのかもしれません。忘れている。忘れようとしている。けれども、時折、自分の身近な人が事件や事故に巻き込まれたり、病に倒れたり、あるいは、自分自身に重い病が見つかったりすると、急に死の陰が迫ってきます。その時になって、あわてふためいてしまうのです。「メメント・モリ」。汝、死すべきものであることを忘れるな。という言葉を思い起こさせられます。
先ほど朗読した、ペトロの手紙一の第 1 章最後の段落において、ペトロは、旧約聖書の預言者イザヤの言葉を引用しながら語っています。「人は皆、草のようで その栄えはみな草の花のようだ。草は枯れ、花は散る」(1 章 24 節)。預言者は、私たち人間の存在のはかなさを、ごまかすことなく見つめています。私たちの生涯を野の草や花になぞらえたのです。野の草は、たとえひととき、美しい花を咲かせたとしても、やがて草は枯れ、花は散ります。永遠に、いつまでも咲き誇ることはできません。枯れて、散るときが来るのです。
私たちも同じように、ひととき、華やかな栄光に包まれたと思っても、やがては人生の終わりの時を迎えることになります。私たちの命は、決して、永遠に続くのではありません。すべてのものが古びて行き、滅びへと向かいます。たとえ、今は健やかであっても、やがて年老いて、死の時を迎えます。時間の中に生きている私たちは、死に向かう定めから逃れることはできません。やがては、枯れるようにして、命を散らすのです。
この地上において、どれほどに大きな財産を築き上げたとしても、あるいは、どんなに高い地位についたとしても、すべては過ぎ去ります。死によって空しくなります。誰も、この死の力から自由になることはできません。私たちは、死に向かって生きている、と言わざるを得ないのです。死がまだ遠い先の話に思えたときには、忘れていられたかもしれません。死を忘れて、生を楽しむ。しかし、時は残酷です。青年の日々は過ぎ去り、次第に肉体は老いていきます。いや、年老いる前に、突然、命が取り去られることもあります。愛するものや、親しいものの死に直面するとき、人間は死ぬのだということを、改めて、否応なく、思い知らされるのです。私たちの存在がいかにはかないものであるかを思い知らされるのです。
旧約の預言者は、イスラエルの民の体験を元にしながら、徹底的に、人間の空しさを見つめています。命のはかなさを見つめています。人間の営みの中に、永遠と呼べるものは何一つないことを、徹底的な醒めた目で見つめているのです。形あるものはもちろんのこと、私たちの魂も決して永遠ではありません。あらゆるものは、古びて行き、廃れて行きます。この地上には、何一つとして確かなものは存在しないことを、預言者は見つめています。
引用されているもとのイザヤ書の言葉を見ると、さらに厳しい言葉が記されています。「すべての肉なる者は草その栄えはみな野の花のようだ。草は枯れ、花はしぼむ。主の風がその上に吹いたからだ」(イザヤ 40 章 6~7 節)。確かに、時が過ぎれば、草は枯れ、花はしぼみます。けれども、それは、単なる自然的なこと、というだけではありません。主の風がその上に吹いたからだ、というのです。主の風、すなわち、神の裁きの息が吹きつけるとき、私たちの存在は、たちどころに消え去ってしまう。そこにこそ、本当のはかなさを見ていると言ってよいのだと思います。ところが、預言者は続けて語るのです。「まさしくこの民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。しかし、私たちの神の言葉はとこしえに立つ」。神の裁きの息が吹けば、たちどころに消え去ってしまうようなはかない人間に対して、とこしえに立つ神の言葉が語りかけられているのです。
ペトロは、預言者イザヤの言葉をなぞるようにして語りました。「こう言われているからです。『人は皆、草のようで その栄えはみな草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。』これこそ、あなたがたに福音として告げ知らされた言葉なのです」(1章24~25節)。徹底的に、人間の中に潜む罪の空しさを見つめながら、永遠に変わることのない神の言葉によって立たせられる。そこに、地上の朽ち行く定めと罪の力から解放されて、自由になった神の子の命があります。決して古びることのない、神につながる命があるのです。
ペトロは、この神につながる命について、語ります。「あなたがたは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生ける言葉によって新たに生まれたのです」(1章23節)。確かに、この地上の事柄はすべて過ぎ去って行きます。私たちの命も過ぎ去ります。けれども、神の言葉は生きています。神の言葉は決して過ぎ去ることもなければ、変ることもありません。私たちは、永遠から名を呼ばれて、永遠の神の言葉によって、新しく生まれさせていただいた、というのです。神によって名を呼ばれ、三位一体の神の名によって洗礼を受けるならば、新しい命をいただくことができる。決して古びることも滅びることもない永遠の命を生きるものとされる。私たちが、主イエス・キリストの十字架による救いを信じて、洗礼を受け、キリストと一つに結ばれるならば、死の力を打ち破ってよみがえらされた、キリストの復活の命に結ばれることになるのです。
み言葉は私たちに告げています。「あなたがたは、真理に従うことによって、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい」(1章22節)。「清い」という言葉が繰り返されます。これは、私たちが洗礼を受けた時に感じる最初の清々しさを指しているのではありません。最初の感動、最初の喜び、最初の愛、それは大事です。けれども、すぐにこの世の生活に巻き込まれてしまって、最初の感動は薄れていきます。最初の喜びもすり切れていきます。愛はつまずいてしぼんでいきます。洗礼を受けて、新しく生まれたはずなのに、気がついたら、何も変っていない。もとの生活に戻っていたりするのです。
しかしながら、間違えてはならないと思います。ここでいう「清さ」は、私たちが感じる清々しさというのとは違います。私たちの感覚を問題にしているのではありません。この清さは、神とつながることによって与えられる清さです。この地上のただ中に存在し、生活しながら、なおこの世から自由であり、永遠なる神につながって生かされている清さです。私たちは、この清さを、真理に従うことによって与えられました。真理そのものであるイエス・キリストと一つに結ばれることによって、この真理に生きる者とされました。私たちは、この真理によって支えられているからこそ、神のもとに留まり続けることができます。虚無の中に落ちて行かず、神のものとして生かされるのです。
すべてが朽ち果てていくこの世の空しさの中で、私たちは、この変わることのない、確かな真理に立つことができます。イエス・キリストという真理に従うのです。永遠の神の言葉が、人となって私たちの間に宿られた、このイエス・キリストこそは、私たちの存在を支える神の真理、神の信実です。この真理によって捕らえられ、この真理に堅く立ち、この真理に聞き従うことによって、私たちは、神の子として、神のもとに留まり続けることができます。神を父と呼び、主イエスを長子とする神の家族、主にある兄弟姉妹として、偽りのない兄弟愛に生きるものとされるのです。
週の初めの日の朝早く、主イエス・キリストは墓の中からよみがえらされました。だからこそ、私たちは今、週の初めの日に共に集い、キリストの復活を記念しながら、神が与えてくださるまことの新しさを喜び祝うことができます。すべてのものを支配し、すべてのものを滅びへと定めていた死の力は、キリストの復活によって打ち破られました。主イエスと一つに結ばれ、主の死に合わせられて、罪に対して死んだ者は、主とともに生きる新たな命の恵みにあずかっています。確かに、私たちの生まれながらの体も魂も、日々古びて行きます。滅びへと向かっています。私たちは、自分の力で新しくなることはできません。むしろ、私たちの弱さと罪深さのゆえに、新しくなろうと思い、変わろうと願いながら、変われないのが私たちの現実です。
けれども、私たちは、自分の決心や自分の努力で新しくなるのではありません。主イエス・キリストに結び合され、神の変わることのない生きた言葉によって新しく生まれるのです。主イエス・キリストの救いを信じて、主と一つに結ばれる洗礼を受けた者たちは、もうすでに、罪と死の力による支配から解き放たれて、神の愛に生きる者とされています。そして、すべての人が、洗礼を受けて、神の言葉によって新しく生まれる恵みへと招かれているのです。
確かに私たちの地上の命は、いつか終わりの時を迎えます。しかし、それで、すべてが終わるのではありません。主が再びこの地上に現れてくださる終わりの日、私たちもまた復活の体をいただいて、主の御前に喜び集うものとされます。その終わりの日の祝福を先取りするようにして、今、聖餐の恵みを通して、永遠の命にあずかり、復活の喜びの前味にあずかります。蜂の巣からしたたる蜜よりも甘い、神の生ける言葉によって養われるのです。
「草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることがない」。アーメン。