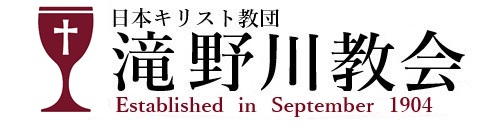2025年8月17日 主日礼拝説教「落胆しないで祈り続ける」 東野ひかり牧師
詩編 第94編18-19節
ルカによる福音書 第18章1~8節
+++++++++++++++++
詩編 94:18-19
18私が「足がよろめく」と言ったとき/主よ、あなたの慈しみが私を支え
19思い煩いが私の内を占めるときも/あなたの慰めが私の魂に喜びを与える。
ルカ 18:1~8
1イエスは、絶えず祈るべきであり、落胆してはならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。
2「ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。3その町に一人のやもめがいて、この裁判官のところに来ては、『相手を裁いて、私を守ってください』と言っていた。4裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかったが、後になって考えた。『自分は神など畏れないし、人を人とも思わないが、5あのやもめは、面倒でかなわないから、裁判をしてやろう。でないと、ひっきりなしにやって来て、うるさくてしかたがない。』」6それから、主は言われた。「この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。7まして神は、昼も夜も叫び求める選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。8言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」
+++++++++++++++++
先週の8月15日は、敗戦から80年を覚えて、日本中で、様々な形で、祈りがささげられたことを思います。先週だけではなく、既に今年に入ってから、3月の東京大空襲の日、6月の沖縄慰霊の日、そして8月6日の広島の原爆の日、9日の長崎の原爆の日と、それぞれ記念の日を迎える度ごとに、平和を求める祈りがささげられてきました。長崎が最後の被爆地であるようにという祈りは、これまでもこれからも、私たち皆の、切なる願いであり祈りです。繰り返し私たちは、戦争の悲惨を、過ちを、二度と繰り返してはならないと、平和を求める祈りをささげてきました。しかしそのように祈りを重ねながらも、今この時も戦争をしている国々がある現実、戦争のゆえに飢えて死んでいく人々・子どもたちがいるという現実は、常に重苦しく私たちの心の中にありました。平和を祈りながら、戦争がなくならない現実への悲しみ・痛みを覚え、心のどこかに無力感や空しさを覚えることもあったのではないかと思うのです。でもそれでもと、沈み込みそうになる心を励ましながら、祈り続けてきた私たちではないかと思います。
今朝聞きましたルカによる福音書第18章は、主イエスが弟子たちに「絶えず祈るべきであり、落胆してはならないことを教えるために」たとえをお話になったと始まります。今朝は、主イエスが「絶えず祈るべきであり、落胆してはならないこと」をお教えになった、ということをめぐって、しばらくご一緒に思いをめぐらせてみたいと思っております。
「落胆してはならない」と訳されました言葉は、以前の翻訳では「失望せずに」「気を落とさずに」と訳されていました。同じ言葉が、新約聖書の他のところでは「たゆまず」とも訳されます。「たゆまず善を行いなさい」というふうに用いられている言葉でもあります。「落胆する」という言葉の元のギリシャ語を辞書で引きますと、「失望する、落胆する、気落ちする、気がくじける、疲れる、うんざりする」という意味が並んでいます。最近よく使われる言葉に「心が折れる」というのがありますが、それもこの言葉の意味として当てはまるかもしれません。主イエスは、弟子たちに、つまりは私たちに言われるのです。「落胆しないで、気を落とさないで、たゆまず、くじけず、疲れることなく、うんざりしないで、絶えず祈りなさい。心が折れたなんて言わずに、たゆまず、祈り続けなさい。」主イエスは、弟子たち・私たちにそう言っておられます。
しかし私たちは、平和を求めて祈りながら、どんなに祈っても、今も戦争が続いている現実に、ある落胆をも覚えざるを得なかったのではないでしょうか。祈ることにも少し疲れてしまうような、うんざりしてしまうような、心が折れそうになるというような、そういう気持ちと戦わなければならなかったのではないでしょうか。とりわけイスラエルが、世界中から「非人道的」と非難されながらもなおガザへの攻撃を止めないことに、落胆を大きくさせられてきたのではないかと思います。平和の実現を求めて祈り続けることに、くじけそうになりながら、心折れそうになりながら、落胆する心と戦いながら、しかしそれでも、と、祈ってきたのではないかと思うのです。
私たちは、実に様々なところで、それぞれの人生の中で、信仰生活の中で、「落胆」を経験いたします。祈っても祈っても変わらない世界の実情に、祈りも信仰も無力だと、空しいと、落胆する。それだけでなく、神を信じて生きていても、神に祈っても、何も変わらない、神は無力だというように、神さまに落胆するということもあると思います。そしてまた、人とのかかわりの中で、人に落胆し、何よりも自分自身に深く落胆させられる、ということもあります。教会生活・信仰生活の中でも、時に私たちは、人にも、神さまにも、落胆させられる思いと戦わなければならないことがあります。様々な、辛い厳しい経験をいたしますとき、私たちは、「神さまはどうしてこんなことをなさるのか、いったい私がどんな悪いことをしたというのか」と、心も折れ、落胆する中で、神さまのみ心が分からなくなり、神さまにもすっかりがっかりして落胆して、祈ることもできなくなり、信仰も崩れてしまうということさえ起こるのです。多くの人が、そういった様々な試練や困難の中で、落胆し、祈れなくなり、祈らなくなって、信仰を失ってしまい、教会を去ってしまう。教会を去らずとも、教会にとどまっていても、その信仰はすっかり萎えてしまう、そういうこともあると思います。しかしそういう私たちに、主イエスは言われるのです。「絶えず祈るべきであり、落胆してはならない」、「落胆しないで、絶えず祈り続けなさい」と。
もう10年以上前になりますが、聖学院教会におりました頃、礼拝でこのルカ福音書の第18章が読まれたことがありました。その頃の私は、まさに落胆していました。自分の人生はもう終わったというような気持ちにさえなっていました。自分自身に落胆していました。礼拝も休みがちでした。信仰が萎えるというのはああいうことを言うのだろうと思うのですけれど、礼拝に行くにしても、行かなければいけないから行く、ただそれだけで、喜びも何もありません。行かねばならないと、その日、ようやく礼拝に行きました。礼拝ではルカ福音書の講解説教が続いていましたが、「いつの間にかもう18章まできていたのか」と思いながら、礼拝に出ていました。この箇所が読まれました。新共同訳の言葉です。「イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。」この何げない言葉を聞きましたとき、不思議なことにこんなふうに思ったのです。「ああ、イエスさまは、弟子たちが気を落として祈れなくなるのをご存知だったのだ」と、そう思ったのです。そして何だか安心したのです。イエスさまは、私たちが気を落とすことがあると、落胆することがあると、知っておられるのだ、祈れなくなってしまうことがあると、知っておられるのだと、そう思って、何だかとてもほっとしたのです。イエスさまは、気落ちして祈れなくなってしまう弟子たちのこと、私たちのことを分かっておられて、ここでこういうふうにおっしゃって励ましていてくださる、イエスさまがその両手で気落ちする心を支えていてくださるように思いました。この全く何げない、「イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために」という言葉が、光り輝いて見えた、そういう経験をしました。改めて思うのですけれど、喜びも何もなくても、ただ行かなければならないから行くという、そういう礼拝の出方であっても、重い心を抱えたままに礼拝に行った、礼拝の場に身を置いた、ということが大切だったのだと思います。み言葉が、向こうから打ちひらかれて光を放つ、という経験を与えられました。
今朝は、合わせて詩編第94編の言葉を読みました。「私が「足がよろめく」と言ったとき/主よ、あなたの慈しみが私を支え/思い煩いが私の内を占めるときも/あなたの慰めが私の魂に喜びを与える。」この詩編を歌った信仰者も、深い落胆を味わっています。何か大きな困難の中にあって、自分の足がよろめき、心が思い煩いに占められるという経験をしています。ある人は、この「足がよろめく」というのは、固い地面の上を歩いていて、たとえば今日のようにとても暑くて、クラっとしてふらっとよろけるとか、ちょっと何かにつまずいてよろけるとか、これはそういう程度のことではない、と言います。そうではなくて、ここで言われていますのは、歩いている地面そのものが、足もとから崩れ落ちて、深い奈落の底によろめき落ちていく、すべり落ちていくという、そういう経験を言っているのだというのです。この「足がよろめく」というのは、人生に思わぬ穴があいて、深い苦しみの底に落ちてしまうというような、「魂が底から落ちる」というような、そういう経験を言っているというのです。
「落胆」という日本語の漢字は、「胆が落ちる」と書きますが、深い落胆は、胆が、心が、魂が、その底から落ち、崩れて、深い奈落の底に落ちていく、というようなことかもしれないと思います。それは、立っている足もとが地面から崩れ落ちるような経験、ではないかと思います。私たちは、それぞれの長い、あるいは短い信仰生活、人生の中で、そういうような試練の経験を、それぞれにする、させられると思います。それは自分や家族の病気や思いがけない怪我であったり、人間関係の破綻であったり、災害であったり、愛する人との死別であったり、それらすべてであったりするでしょう。この詩編の詩人も、そういう何かしらの試練・困難の中にいます。足もとが崩れ落ちて深い穴の底に落ち込んだような経験をしています。けれどそこで、「あなたの慈しみが、私を支えた」「あなたの慰めが、私の魂に喜びを与えた」と言いました。主の慈しみが、主の慰めが、深く落ちていくような魂を、深い穴の底で、下から支えていてくださったと、深く暗い穴に落ちたようなところで、あなたの慰めが私の魂を支え、喜びを与えた、と歌っているのです。
主イエスは、私たちの魂が、私たちの心が、深く落胆することを知っておられます。私たちが祈れなくなることを知っていてくださるのです。「落胆してはならない、祈り続けなさい」と主イエスが言われるとき、それは、その落胆を、その苦しみを、その辛さを、悲しみを全く知らないところで、全く関わりのないどこか遠くから、叱りとばすように「落胆するなんて不信仰だ、祈れなくなるなんて不信仰だ、祈り続けなさい」と冷たく命令した、というのではなくて、そうではなくて、十字架を目前にして、弟子たちが信仰を失うこと、目覚めて祈ることもできなくなること、深くふかく落胆することをご存知で、その弟子たちを十字架に釘づけにされる両の手で支えるようにして、「落胆してはならない、祈り続けなさい」と励ましておられる、そういう言葉だと、私はそう思うのです。私たちの落ちていく魂を、崩れ落ちる足もとを、崩れ落ちていきそうになる私たちの信仰を支えながら、主は言われるのです。「落胆してはならない、祈り続けなさい」と。
主イエスは、そのように弟子たち・私たちを支え励ましながら、「絶えず祈るべきであり、落胆してはならないことを教えるために」、ここで不思議なたとえをお話になります。ひとりのやもめが、その町の「不正な裁判官」に「相手を裁いて、私を守ってください」と、繰り返し何度も訴える、という話です。この裁判官は、「神を畏れず、人を人とも思わない」冷酷無比で不正な、とんでもない裁判官です。しかし、このやもめが、繰り返しひっきりなしにやって来ては訴えてくるので、「面倒だ、うるさくてしかたがない」から、「裁判をしてやろう」と重い腰を上げる、そういう話です。このたとえによって、主イエスは「落胆しないで絶えず祈るべきこと」を教えられた、というのです。不正な裁判官は、やもめが「うるさくてしかたがない」と言います、この言葉は、新共同訳では「わたしをさんざんな目に遭わすに違いない」となっています。これは元の言葉では、「わたしをぶん殴りかねない」という、そういう意味の言葉です。やもめの訴えを聞かなければ、このやもめはこの裁判官を叩きのめしかねないという、そういう何とも激しいやもめの姿を描き出しながら、こういうふうに祈ればよいと、主はおっしゃったのです。
「落胆しないで祈り続けよ」と、主イエスが言われるときの、その祈りは、お行儀のよい祈りではないのです。椅子にきちんと座って、お布団の上に正座をして祈るというような、整った形の祈りではないのです。「助けて、苦しい、正しく裁いて私を守って」と、正しい裁判をしてくれるはずの裁判官に、激しく訴え続けているだけの、祈りとも言えないような「叫び」です。神さまに殴りかかるような勢いで、なりふり構わず、昼も夜も叫び求め続ける、そういう祈り・叫びでよい、「落胆しないで祈り続けなさい」と教えておられるのです。不正な裁判官でさえ、このやもめのために重い腰を上げて裁判をしようとしたのだから、ましてや神は、正しい裁きをしないはずがない、神は必ずあなたの訴えを、祈りを、叫びを聞いてくださる、放ってはおかれないと、主は約束していてくださるのです。
人生の様々な試練の中で、困難の中で、私たちは落胆して祈らなくなり、祈れなくなり、心も魂も信仰も、崩れ落ちてしまうような経験をすることがあります。しかしそのとき、主は言われるのです。血の流れる両の手で、崩れ落ちる私たちを支えて言われるのです。「落胆してはならない、私がここにいる、私が支えている、祈りなさい」と。私たちは、こう祈ってさえよいのではないかと思うのです。「祈れません、もう信じられません、祈りたくもありません、もう神さまなんて信じたくありません」そう叫んでさえよいのではないかと思うのです。主イエスは、裁判官に殴りかかるような勢いで、「私のために正しい裁きをしてください」と訴えたやもめの話をなさりながら、なりふり構わず、「もう祈れない、もう信じられない、私を助けて、私を守って」と、そう叫んでよいのだと、言ってくださったのだと思うのです。「落胆してはならない、たゆまず祈りなさい。神さまに殴りかかるように叫んだってよい、祈り続けなさい。」そう励ましていてくださる。落胆して崩れ落ちていく私たちの魂を下から支えながら、「祈り続けよ」と励ましていてくださるのではないかと思うのです。「たゆまず祈れ、叫べ、あなたの叫びを神は必ず聞いてくださる。たゆまず祈れ、叫べ、神は必ず平和を実現してくださる。神は必ず確かに、この世界にも、あなたの人生にも、正しい裁きを行われる。」主イエスは、落胆する私たちの魂を、底が抜けて落ちていく魂を、崩れ落ちて行く足もとを支えながら、今日も私たちを支え、励ましていてくださいます。