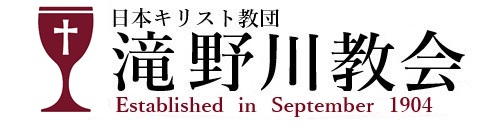2025年7月6日 主日礼拝説教「あなたの居場所はここに」 東野尚志牧師
申命記 第 7 章 6~11 節
ペトロの手紙一 第 1 章 1~2 節
先週の水曜日、7 月 2 日の朝、教会員の大場千代子さんが天に召されました。96 歳でした。ご長男の庸助さんから、もう口からものを食べることができなくなったというご連絡を受けて、前の日に、妻ひかりと一緒に、飛鳥晴山苑をお訪ねしたところでした。私たちがお訪ねしたときは、少し目を開けて、お分かりくださったように思いましたけれど、耳元で讃美歌を歌っていると、気持ちよさそうに寝息をたて始められました。けれども、確かに聞こえていると感じました。後で、施設のスタッフの方が、私たちが讃美歌を歌い始めたら、心電図の波が変わって安定した、と伝えてくださいました。
その翌日の朝になって、大場さんが静かに息を引き取られたという連絡を受けました。びっくりしました。こんなに早くとは思いませんでした。同時に、前の日にお会いできてよかったと思いました。待っていてくださったのかもしれないと思いました。安心して、すべて委ねて逝かれたのだと思いました。今から 73 年前、24 歳のクリスマスに、千葉儀一牧師から洗礼を授けられました。キリスト者となってからは、イエス・キリストによる救いを一人でも多くの人に伝えたいと思って、伝道者になることを志したときもあったそうです。教会では長く、伝道部の部長を務められました。教会の入口に立って、教会に来た人たちを心から歓迎しておられた姿を覚えておられる方も多いと思います。大場さんと握手をしたことのある方も多いはずです。あの力強い握手を懐かしく思います。握手をすると、いつも、先生凝ってると言って、手のツボを強く押して、マッサージしてくださったのを思い起こします。
先週の日曜日(6 月 29 日)、礼拝において今年度の年間聖句を取り上げ、礼拝後に引き続いて年間聖句をめぐる学びをしたところでした。その御言葉が、大場千代子さんの信仰の生涯と響き合うように感じました。週報を開いた右下の欄に記してある聖句です。「あなたがたは、選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、あなたがたを闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある顕現を、あなたがたが広く伝えるためです」。闇の中に沈み込んでいた私たちのところに、まことの光である主イエス・キリストが来てくださいました。私たちを命の光で照らしてくださり、救いの光の中へと招き入れてくださいました。イエス・キリストにおいて、神ご自身が私たちに現れてくださったのです。このお方、神の顕現そのものである主イエス・キリストを、広く伝えていく。それが、神の民とされた私たち教会の大事な使命なのです。
大場千代子さんは、その若い日に、主イエス・キリストと出会いました。その喜びに突き動かされるようにして、それ以後出会うすべての人たちに、主イエス・キリストの救いを伝えたいと心から願っておられたのではないかと思います。愛する家族にも信仰を伝えたいと願われました。少々、強引なところもあって、その熱心さが裏目に出るようなこともありました。けれども、ひと筋に、主イエス・キリストへの忠誠を貫いた人であったと思います。そのために、いろんなことを犠牲にして来られたとも思います。誤解を招いたこともあります。けれども、いつも、主イエス・キリストの救いの光に照らされて、喜んで信仰に生き抜いたと言ってよいのではないでしょうか。まことの光であるキリストを伝えたいと願われたのです。私たちの教会にとって、大切な信仰の先輩であり、仲間である大場千代子さん、その葬りを教会で行うことができなかったのは残念ですけれど、私たちの記憶の中に大切に刻んで、祈りに覚えたいと思います。また残されたご家族のためにも、祈りたいと思います。その伝道の志と情熱をしっかり受け継いでいきたいと願います。
さて、今年度の年間聖句として、ペトロの手紙一の第 2 章の言葉が選ばれたのを受けて、この機会に、ペトロの手紙の全体を読んでいきたいと思いました。長く続いたヨハネによる福音書の講解説教が終わったところでもありました。先に第 2 章の御言葉を読んだのですけれども、改めて、第 1 章に戻って、ペトロの手紙一を読んでいきます。手紙というのは面白いと思います。小説や論文とは違います。手紙は、何かを伝えるために書かれます。それを書いた人があり、受け取る人がいるのです。死を前にして、最後に何か伝えたいことはあるかと訪ねられて、私の生涯が私のメッセージだと語った伝道者がいました。大場千代子さんの死に際しては、ご家族の事情もあり、教会で葬儀の礼拝を行うことはできませんでしたけれども、火葬前に時間をもらって、短い礼拝を行うことができました。その準備のために、大場さんが書き残された証しの言葉などをいくつも読んでいると、大場さんから届いた手紙を読んでいるような気がしてきました。大場さんの遺言を聞いているような気がしてきたのです。
私の手元に、大場千代子さんが 90 歳の誕生日を迎えられたときに、私宛にくださった自筆の手紙があります。別紙に祈りの言葉が綴られていました。
「イエス様、みことばをください。みことばは力があり、主の霊がやどり、罪人をゆるし、愛を増し加えてくださる。感謝、アーメン。イエス様、みことばをください。みことばには、主の霊がやどり、祈りを与えてくれる、アーメン。イエス様、みことばをください。みことばは、祈りを与えてくださる。そして、ゆるされて愛を深く知る、アーメン。九十才の誕生日に、感謝して、千代子」。
主の御言葉を求め続けた大場千代子さんの信仰が、素朴な言葉で繰り返されています。イエスさまへの祈りとして綴られていますけれども、大場さんの信仰を伝える手紙としても心に響きます。新約聖書の中に、数多くの手紙が収められているというのも、うなずけるところではないかと思います。そこには、福音を伝えようとする伝道者たちの祈りと情熱が溢れているのです。
ペトロの手紙は、その名の通り、ペトロが書いた手紙ということになります。当時の手紙の習慣にならって、最初に手紙の差出人と受取人について記された後、短い挨拶の言葉が綴られています。ペトロは、自分の名前を記すとき、「イエス・キリストの使徒ペトロから」と書きました。「使徒」という言葉を用いるときには、少し躊躇を感じたかもしれません。生まれつき、根っからの漁師であったペトロが、ある日、突然、主イエスと出会って、従うように招かれました。舟や網を捨てて、父親や雇い人もその場に残したまま、主イエスについて行きました。恐らく、その時、30 代半ばであったと思われます。あるとき、主イエスから、「あなたがたは私を何者だと言うのか」と問われると、弟子たちを代表するように、ペトロは答えました。「あなたはメシア、生ける神の子です」。すると主はペトロに言われました。「バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを現したのは、人間ではなく、天におられる私の父である。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。陰府の門もこれに打ち勝つことはない」(マタイ 16 章 15~18 節)。ペトロにとって、誇らしい出来事であったと思います。
ところがすぐその後で、主イエスがご自分の苦難と死について予告を始められると、「そんなことがあってはなりません」と言って、ペトロは主の道に立ちはだかります。すると、主イエスは「サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者だ。神のことを思わず、人のことを思っている」と言われました(同 23 節)。こっぴどくお叱りを受けたのです。さらには、主イエスが十字架につけられる前の晩、捕らえられ連行された大祭司の屋敷の中庭で、主イエスの弟子であることを自ら否定してしまします。ペトロのガリラヤなまりに気づいた人が、ガリラヤから出て来た主イエスの仲間の一人ではないかと問い詰めると、「そんな人は知らない」と言って誓い始めた(マタイ 26 章 69~75 節)。三度も主イエスのことを知らないと言って、自ら主の弟子であることを否定してしまったのです。
主イエスとの関係を否定して、主を裏切ってしまった。深い挫折と後悔の涙に沈んだペトロ。そのペトロが再び立ち上がることができたのは、復活された主イエスが、もう一度、ペトロを召し出してくださったからです。三度の裏切りを上書きするように、主は三度、ペトロに愛を問われました。「ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか」。ペトロはその問いに対して、三度繰り返して、「はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存じです」と答えました。すると、主は、「私の小羊を飼いなさい」。「私の羊の世話をしなさい」と言って、ペトロを牧者としての務めに任じられたのです。主の赦しと愛と信頼の中で、ペトロは立ち直ったのです(ヨハネ 21 章 15~19 節)。
ガリラヤ出身のペトロは、伝道者・牧者としての生涯の最後のときを、ローマで過ごしたようです。復活の主の召しに応えて、ローマにいる主の羊たちを導き、養いました。そして、ついには、ローマで殉教の死を遂げたと言われます。ペトロの最後に関わる伝説が残されています。「クォ・ヴァディス」という小説に描かれ、映画にもなりました。紀元 64 年、ローマを襲った大火災に端を発した皇帝ネロによる大迫害の中、ペトロはまた逃げ出します。もちろん、周りの信徒たちが、何とかペトロを逃がそうとして、説得し、脱出させたのです。ところが、迫害に苦しむ羊たちを後に残してローマから離れようとしたペトロに、再び復活の主が現れます。主イエスは、旅人の姿で、ペトロが今逃げ出してきたローマへ向かおうとしておられるのです。ペトロは主に尋ねます。「クォ・ヴァディス・ドミネ」(主よ、いずこに行かれるのですか)。すると、主は答えて言われました。「あなたがローマのキリスト者たちを見捨てたので、あなたに代わって私が行く。もう一度、十字架にかけられるために」。それを聞いて、ペトロは道を引き返して、迫害のただ中に戻り、ローマで殉教の死を迎えます。しかも、最後に十字架につけられるとき、主イエスと同じ姿では申し訳ないと言って、逆さではりつけになることを願ったと伝えられます。
ペトロの手紙一が書かれたのは、90 年代のことだと考えられています。ペトロが亡くなった後のことです。第 5 章の最後、手紙の結びのところに、このように記されています。「私は、忠実な兄弟と認めているシルワノによって、あなたがたに短い手紙を書き、勧め、これこそが神の真実の恵みであることを証ししました。この恵みの内に踏みとどまりなさい」(1ペトロ 5 章 12 節)。ここに名前が挙がっているシルワノは、使徒言行録の中ではシラスという呼び名で知られています。恐らく、ペトロの信頼を得ていたシルワノが、ペトロの死後、ペトロの言葉を思い起こしながら、ペトロの信仰に立って、ペトロとひとつになって綴った手紙だと言ってよいのではないかと思われます。同じように、厳しい迫害にさらされていた一世紀末の小アジアの信徒たちに宛てて、その信仰を励まし、力づけるために、この手紙は書かれたのです。「イエス・キリストの使徒ペトロから」。ペトロの失敗や挫折、それをペトロ自身の証しの言葉として聞き続けたシルワノが、主イエスによって使徒とされたペトロの遺言を伝えたとも言えます。私たちは今、その手紙をペトロの手紙として読んでいるのです。
ペトロからの手紙の受取人については、「ポントス、ガラテヤ、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散し、滞在している選ばれた人たち」と記されています(1 章 1 節)。小アジアの各地、今のトルコの中央から北部にかけて離散し、滞在していた信徒たちです。私たちの聖書、聖書協会共同訳の聖書が「滞在している」と訳した言葉を、以前の口語訳聖書では「寄留している」と訳していました。また新共同訳聖書では「仮住まいをしている」と訳しました。つまり、定住しているのではなくて、旅人のように仮の宿りをしていたということです。ローマ帝国からの厳しい迫害にさらされたキリスト者たちは、ひとつの場所に留まって礼拝をすることができずに、小アジアの各地に離散して、仮住まいの身で礼拝していました。それは、天に国籍をもちながら、地上では仮の宿りをしている私たちキリスト者の姿をよく現わしています。天を故郷として生きるということは、やがては天に帰るべき者として地上を生きることを意味します。本当の故郷は天にあって、地上では仮住まいなのだから、地上の生活はどうでもよいということではありません。むしろ、天にしっかりと足場を据えているからこそ、主が与えてくださった地上の生活に対して、使命と責任をもって生きることになります。
キリストは教会の頭(かしら)、教会はキリストの体です。復活して天に上られたキリストは、ご自身の体である教会を通して、この地上の世界に、御心を行おうとしておられます。そのために、招かれた私たち一人ひとりを、ご自身の体の部分として用いようとしておられるのです。天とつながる地上の足場である教会こそは、命の砦であり、伝道の拠点です。ここに私たちの地上における魂の居場所があると言ってよいのです。
手紙の受取人についての記述は続きます。「すなわち、父なる神が予知されたことに従って、霊により聖なる者とされ、イエス・キリストに従い、また、その血の注ぎを受けるために選ばれた人たちへ」(1 章 2 節)。父なる神が、予め立ててくださった救いのご計画に基づいて、独り子イエスがこの地上に来てくださいました。主が十字架の上で流された血潮によって、私たちの罪はすべて贖われました。私たちは、聖霊の働きによって、教会へと導かれ、復活の主によって、罪の赦しにあずかる洗礼へと招かれているのです。「霊により聖なる者とされ」とあります。「聖なる者」。それは、私たちが自分で自分を清め高めることではありません。神に選ばれ、神のものとされた、それが「聖なる者」の真実です。しかも、私たちが聖なる者とされ、イエス・キリストに従い行く者となるために、尊い御子の血が注がれたのです。
ペトロの手紙は、この手紙を受け取る者たち、つまり、私たちについて、「その血の注ぎを受けるために選ばれた人たちへ」という、とても生々しい言葉づかいを用いています。私たちは、自分の決心で信仰を貫くのではありません。ペトロのように、私たちも繰り返し、信仰につまずき、挫折を味わいます。試練にさらされれば、信仰がぐらついて、つぶやきが口をついて出て来ます。まことに、情けない思いを繰り返し味わいます。けれども、主イエスは、私たちにご自身の血を注ぎかけて、私たちを新しい契約の中に入れてくださいました。この主イエス・キリストの真実が空しくなることはありません。キリストの注がれた血の真実が、私たちの信仰を守ってくださるのです。ここ、主がおられるところに、私たちの本当の居場所があります。われらここに生きる。
大場千代子さんが、生涯、忘れることのなかった言葉、試練やつまずきの中で、繰り返し思い起こした言葉、それは、結婚の決意をさせたお連れ合いの言葉でした。「人を恐れず、神のみを恐れる」。この「人」の中には、自分自身も入っているのだと思います。自分の弱さに惑わされたり、人の顔色をうかがったりするのではなくて、ただキリストの真実により頼み、神のみを信じ畏れる。繰り返し、この言葉を思い起こし、復活の主の前に立ち帰ることができたのです。地上では仮住まいです。大場千代子さんは、ご自身の本当の故郷である天に帰られました。天に迎えられました。私たちも、天の確かさに支えられながら、この地上にあって、主の救いの光に照らされ、御言葉を生きる者でありたいと願います。神が与えてくださる「恵みと平和」が、私たちの地上の歩みを守り支えてくださるのです。