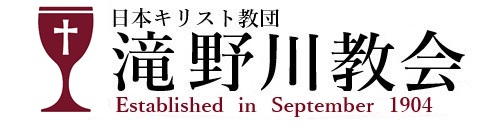2025年6月15日 主日礼拝説教「時が良くても悪くても」 東野尚志牧師
イザヤ書 第 55 章 8~13 節
テモテへの手紙二 第 4 章 1~5 節
先週の日曜日、私たちは聖霊降臨主日の礼拝を共に祝いました。主イエス・キリストの十字架と復活の出来事から 50 日を経て、天から約束の聖霊が降ったことを記念する礼拝でした。「すると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他国の言葉で話しだした」。使徒言行録第 2 章は、そのように告げています。いろいろな国から集まって来ていた巡礼者たちに、言葉の違いを超えて、使徒たちの語る福音が通じたのです。聖霊を受けた弟子たちは、聞いている人たちに通じる言葉、分かる言葉で、神の偉大な業を語り始めました。イエス・キリストの十字架と復活による救いを力強く証ししたのです。
聖霊を受けることによって、福音を宣べ伝える群れとして教会が生まれました。それで、聖霊降臨日は教会の誕生日とも呼ばれます。二千年前のその日から、教会は主イエス・キリストの十字架と復活による救いを語り続けてきました。エルサレムで生まれた教会は、多くの信徒を生み出し、信徒たちが散らされて生まれた教会もまた、その伝道活動を通して、地中海世界に次々に教会を建てました。福音はローマを経てヨーロッパに、さらには全世界に宣べ伝えられ、世界各地に主の教会が建てられて来ました。そして、この日本にも福音が伝えられ、主の教会が生まれました。私たちが今、こうして共に連なっている滝野川教会は、聖学院の学院教会として誕生してから今年で 121 年になりますけれども、さらに歴史を遡れば、二千年前の聖霊降臨日の礼拝からつながっているのです。
聖霊降臨日の翌週の日曜日は、教会の暦において「三位一体主日」と呼ばれてきました。私たちの教会が属している日本基督教団の暦も、「三位一体主日」という呼び方を取り入れています。この呼び名にこだわる必要はありませんけれども、このように呼ばれてきた理由も分かると思います。神がお造りになったこの世界に、二千年前の最初のクリスマス、神の御子であるイエス・キリストが来臨され、さらにその後の十字架と復活、昇天を経て、約束の聖霊が降臨されたことによって、父・子・聖霊が揃った、という感覚なのだと思います。もちろん、それは、地上的・人間的な感覚であって、神は永遠に父・子・聖霊なる三位一体の神です。御子も聖霊も永遠の初めから御父と共におられるのです。
ヨハネによる福音書の第 1 章冒頭には、天地万物が造られた創造の業に、第二位格の言なる神が参与しておられたことが印象深く歌われています。「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った」(ヨハネ 1 章 1~3 節)。そして「言は肉となって、私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」(同 14 節)。永遠の初めから神と共におられた第二位格の言なる神が、クリスマスの時、私たちと同じ人間のひとりとして地上に宿られたのです。また創世記の第 1 章冒頭には、次のように記されています。「初めに神は天と地を創造された。地は混沌として、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた」。第三位格である神の霊も、天地創造の初めから神と共におられました。その神の霊である聖霊が、二千年前のペンテコステの日、この地上に激しく降って来られ、教会が生まれたのです。
今日、私たちに与えられた御言葉は、神の霊を受けて、聖霊に生かされる教会が、この地上において、神から託されている務めは何であるのか、そのこと明確に告げています。「御言葉を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを続けなさい」。二千年前のペンテコステの日、天から降った聖霊は、炎の舌のように分かれ分かれに現れて、一人ひとりの上に宿りました。だからこそ、教会は、一つの霊である聖霊に満たされながらも、一人ひとりに与えられる霊の賜物は異なっています。そのそれぞれに異なった賜物が生かされ用いられ、さまざまな奉仕の業が担われることを通して、福音伝道という教会に与えられた大きな使命が豊かに実を結んでいくことになるのです。
確かに、教会には、さまざまな奉仕の業があります。教会の運営のために役員会が招集され、教会学校の働きがあり、毎週の礼拝も多くの奉仕によって支えられています。礼拝に備えての会堂清掃の働きがあり、奏楽の奉仕にあたるオルガニストは、練習を重ねて礼拝に備えます。週報を作成する働きもあり、特別な祝祭日のときには、お花を生ける奉仕があります。礼拝当日も、受付の奉仕や配餐・献金の奉仕があり、オンライン配信の奉仕もあります。時に応じて昼食準備の奉仕もあります。休んでいる教会員に連絡を取ったり、週報棚の印刷物などを送ったり、教会員相互の交わりを保つための奉仕もあります。いろいろな奉仕の働きに支えられながら、教会は、御言葉を宣べ伝え、福音を証しする務めを展開していると言ってよいのです。
「御言葉を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを続けなさい」。この命令は、直接的には、テモテへの手紙二を書いた使徒パウロから、この手紙を受け取ったテモテに向けて告げられた言葉です。使徒パウロにとっては、同労者であり、時には、我が子と呼ぶほどに愛したテモテに宛てて書かれた手紙なのです。先輩伝道者であるパウロが、伝道者としては後輩である年若いテモテに宛てて、どうしても伝えなければならないと思ったことを記した手紙です。遺言と呼んでよいような言葉も見受けられます。先ほど朗読した箇所の直後の段落の言葉は、次のように続くのです。「私自身は、すでにいけにえとして献げられており、世を去るべき時が来ています。私は、闘いを立派に闘い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今や、義の冠が私を待っているばかりです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるでしょう。私だけでなく、主が現れるのを心から待ち望むすべての人に授けてくださるでしょう」(2テモテ 4 章6~8 節)。殉教の死を覚悟している言葉です。終わりの日には、正しい審判者である主が、義の冠を授けてくださると言うのです。
それは確かに、伝道者パウロから伝道者テモテに告げられた言葉です。だから「御言葉を宣べ伝えなさい」というのは当たり前だと思われるかもしれません。それは伝道者の務めだと言われるかもしれません。けれども、パウロはここで、ただ伝道者だけが心得るべきことを記しているのではないと思います。伝道者はもちろんですけれども、「御言葉を宣べ伝える」という主イエス・キリストから教会に託された働きを担っていくために、御言葉を中心として、教会全体の信仰と奉仕の姿勢が整えられることを願っているのです。御言葉を宣べ伝えるのは伝道者だけではありません。御言葉を聞いて、御言葉を食べて、御言葉を生きる信仰者たちの存在を通して、その生き方を通して、御言葉は証しされ、伝えられていくのです。
だからこそ、パウロは、「御言葉を宣べ伝えなさい」という勧めを語る前に、御言葉を聞いて、御言葉を生きる私たちすべての信仰の姿勢を正そうとして語ります。「神の前で、そして生きている者と死んだ者とを裁かれるキリスト・イエスの前で、その出現と御国とを思い、私は厳かに命じます」(4 章 1 節)。何とも仰々しい大げさな表現のように感じられるかもしれません。でも、この言葉を読むとき、私はいつも、背筋が伸びる思いがします。それまで、椅子に深く座って、背もたれに体重を委ねていても、神の前で、キリスト・イエスの前で、厳かに命じます、と言われると、すっと背筋が伸びるのです。この 4 月から始まった、NHK の朝ドラ「あんぱん」を毎朝楽しく見ていますけれど、このところ、80 年前のあの戦争の時代に入って、見ているのが辛い場面もあります。主人公が軍隊に入って、先に入隊した兵士から殴られたりしている。でも、そういう場面に、上官がやって来ると、みんな立ち上がって、直立不動で敬礼する。
上官どころではありません。主イエス・キリストが来られるのです。寝転んだまま、座ったままというわけにはいきません。サッと立ち上がるでしょう。イエスさまは友だちだから、寝転んだままでいいと思う人はいないはずです。むしろ、立ち上がって、駆け寄って、すぐ側に行きたいと思うでしょう。いやもしも、私たちの側で、主を恐れて、近づくのを躊躇していたとしても、主イエスの方から、私たちに近づいて来てくださいます。私たちに歩み寄って、私たちを立ち上がらせてくださるのです。使徒パウロは、神の前に、主イエス・キリストの前に立っています。主イエスが裁き主としての権能をもって再び現れてくださる終わりの日、神の国が完成されるその日を望み見ています。そして、神の御前に立つ者として語るのです。裁き主である主イエス・キリストの御前に立つ者として語るのです。厳かに命じる、というのは、神の権威によって語ろうとしていることを意味します。それは、ただパウロが語る言葉ではなくて、父なる神と主イエス・キリストが、パウロを通して教会に命じておられる言葉として伝えようとするのです。
「御言葉を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを続けなさい」。時が悪い、というと、迫害の厳しい時代のことを思い浮かべるかも知れません。この日本においても、80 年前までの十数年間は、教会にとって厳しい時代であったと思います。それを、自分自身の経験として覚えている人はどんどん少なくなっていきます。信仰のゆえに迫害を受けて、牢に入れられた牧師たちもいました。獄死した人たちもいました。戦後のキリスト教ブームは、良い時であったと言えるのでしょうか。しかし、それが一時的なブームとして過ぎ去ってしまったことを思うと、時が良いとか悪いとかいうのは、私たちが判断することではないのだと思います。時代の風向きは変わるからです。「時が良くても悪くても」というのは、良い時と悪い時を分けるのではなくて、むしろ、どんなときでも、どんな時代になっても、いついかなる時も、絶えず熱心に、御言葉を宣べ伝えるということだと思います。パウロは続けて語りました。「忍耐と教えを尽くして、とがめ、戒め、勧めなさい」。忍耐しながら、教えを尽くす。もう今の時代に、御言葉は古くさくて響かないとか、もっと時代にあった言葉、人の心に感動を与えるような話をしなければならないというのではないのです。
もしも、御言葉が語られているのに、それが心に届かないとしたら、語る者にも聞く者にも、祈りが足りないということかもしれません。聖霊なる神の働きを求め、聖霊なる神の働きに委ねる祈りが足りないのです。あの二千年前のペンテコステの日のように、聖霊なる神が降ってくださり、聖霊なる神が私たちの間に働いてくださるとき、神の偉大な業を語る言葉は、言葉の壁を越えて、聞く人の心に届きました。分かる言葉になりました。そして、人を生かす言葉になりました。主イエス・キリストの十字架と復活を告げる福音の言葉が、救いの出来事となるためには、人間の知恵をどれほど尽くしても充分とは言えません。むしろ、主の十字架の救いを告げる素朴な言葉と共に、聖霊なる神が働いてくださるとき、救いが実現するのです。二千年前の主イエスの十字架が、今、この複雑な時代、さまざまな悩みや苦しみを抱えている私の救いになるというのは、理性的に考えて説明のつく話ではないのです。あなたは聖霊を受けていますか。そんなふうに問われたら、自信を持って聖霊を受けた、と答えられない人もいると思います。信者に対して、何年何月何日、何時何分、私は聖霊を受けた、という証しを求める教派もあります。そんなの、私も答えることなどできません。けれども、もし今、私たちが、主イエス・キリストを私の救い主として信じているとしたら、それは、紛れもなく、聖霊を受けているからです。聖霊の働きなしに、主イエスの十字架と復活が私の救いだと信じることなどできないからです。
聖霊なる神の働きを信じることができないとき、私たちが陥りがちな過ちについて、パウロは鋭く語ります。「誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時、人々は耳触りのよい話を聞こうと、好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話へとそれて行くようになります。しかしあなたは、何事にも身を慎み、苦しみに耐え、福音宣教者の働きをなし、自分の務めを全うしなさい」(4 章 3~5 節)。「誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます」と語ります。今、そのような時代がすでに来ているのではないでしょうか。インターネットの世界にはいろんな言葉や情報が溢れています。中には、まことしやかに語られる作り話やフェイクニュースもあります。特に、災害時など、フェイクニュースを信じた人たちが、良かれと思ってその情報を拡散して、ますます混乱が広がったりします。何が本当のことか、分からない。そういうとき、人は、自分の聞きたい話を受け入れるようになります。認知機能にバイアスがかかるようになる。人は自分の信じたいことを信じるようになる。主が告げてくださる御言葉よりも、耳触りのよい話に惹かれていくのです。
同じテモテへの手紙二の第 3 章には、終わりの日に起こることが告げてられています。3 章の 1 節からお読みします。「このことを知っておきなさい。終わりの日には困難な時期がやって来ます。その時、人々は、自分自身を愛し、金に執着し、見栄を張り、思い上がり、神を冒瀆し、親に逆らい、恩を知らず、神を畏れなくなります。また、情けを知らず、和解せず、人をそしり、自制心がなく、粗暴になり、善を好まず、人を裏切り、向こう見ずになり、気が変になり、神よりも快楽を愛し、見た目は敬虔であっても、敬虔の力を否定するようになります」(3 章 1~5 節)。これはいつの話でしょうか。今、この偽りや対立に満ちた世界の有り様そのものではないでしょうか。二千年前、主イエスがこの地上に来られたときから、すでに終わりは始まっているのです。やがて主が再び来られる時、神の国、神さまのご支配が完成されます。その時まで、私たちは、時代の声や悪しき霊に惑わされることなく、神の言葉に聞き従い、聖霊の力に守られて、主が私たちのために成し遂げてくださった十字架と復活による救いにあずかって、御言葉の真実を証しする者として歩み続けるのです。
パウロは言いました。「神の前で、そして生きている者と死んだ者とを裁かれるキリスト・イエスの前で、その出現と御国とを思い、私は厳かに命じます。御言葉を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを続けなさい。忍耐と教えを尽くして、とがめ、戒め、勧めなさい」。私たちは、主の日毎の礼拝において、生ける神の御前に立ち、まことの主であるイエス・キリストの御前に立ちます。そして、見えない神の言葉としての説教と、見える神の言葉としての聖餐に養われて、御言葉に満たされ、御言葉を生きる者とされるのです。私たちは、この礼拝を終えると、神の御前からそれぞれの生活の場へと遣わされて、家族や友人、仕事の仲間たちと共に過ごす新たな一週の歩みを始めます。御言葉が私たちの心に刻まれ、霊なる主が私たちの内に宿ってくださって、これから出会っていく人たちに、私たちの存在と生き方を通して、御言葉を伝えていくことができれば幸いです。そのためにも、主の日毎の礼拝を重んじ、週の半ばに行われる聖書研究・祈祷会を大切に受けとめていただきたいと思います。御言葉にどっぷりと浸かって生きる。聖霊の力を求めて祈る。この世の悪しき霊や偽りの情報に惑わされないためにも、御言葉と真理の霊を求め続けてください。御言葉を求めることにおいて、怠惰であってはなりません。私たちが御言葉を守るのではなく、御言葉が私たちを守ってくださるのです。