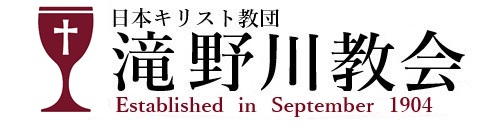2025年3月30日 受難節第四主日礼拝説教「復活の光に照らされる」 東野尚志牧師
詩編 第30編1~6節
ヨハネによる福音書 第20章1~10節
受難節の中で、2024年度の最後の主の日を迎えました。今日は3月30日、2024年度は明日の月曜日で終わります。今週の火曜日から2025年度の歩みが始まるのです。そういう意味では、ギリギリですけれども、本日、礼拝に引き続いて、2024年度第2回の定期教会総会を開催します。2025年度の活動計画、予算を審議します。役員の半数改選を行って、2025年度の体制を整えるのです。3週間後には、主のよみがえりを祝う、復活主日の礼拝を行うことになります。その意味では、まだ受難節のまっただ中にいるわけです。
ところが、この朝、私たちに与えられた聖書の箇所は、イースターの礼拝の先取りのような感じになります。4年前、2021年の9月の初めからヨハネによる福音書を読み始めて、20章までたどり着きました。先週は、十字架につけられたイエスさまのお体が、十字架から取り降ろされて、まだ誰も葬られたことのない新しい墓に納められたところを読みました。主イエスのお体の埋葬を行ったのは、ユダヤの最高法院の議員であったとされる、アリマタヤ出身のヨセフとニコデモの二人でした。実はこの二人とも、心では主イエスのことを信じていたにもかかわらず、ユダヤ人たちを恐れて、それを公にせずに隠していました。けれども、大切な先生である主イエスの死を前にして、地上の別れに直面して、もう隠してはおけなくなりました。そのことで、自分たちの身に危険が及ぶとしても、議員の身分を失うことになるとしても構わない。主イエスが、自分たちのために、命を捨ててくださったのに、自分たちが黙って隠れているわけにはいかないと思ったのです。主イエスの愛に応えようとして、ローマ総督ピラトに埋葬の許可を求めました。そして、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、丁寧に主イエスのお体を墓に葬ったのです。
その日は、準備の日でした。ユダヤ人にとって、民族の解放を記念する祭り、過越祭の備えの日でした。その上に、七日ごとに区切られた一週間の終わりの日、つまり安息日に備える日であったわけです。安息日が始まると、もう葬りはできなくなります。ヨハネの福音書以外、マタイ、マルコ、ルカのいわゆる共観福音書を見ると、日が沈んで、安息日が始まってしまう前に、慌ただしく主イエスのお体を墓の中に納めたような描き方がなされています。それで、掟に従って安息日を休んだ後、安息日が明けるのを待ちかねたように、数人の女性たちが、香料を携えて墓に行った、というふうに記しているのです。せめてものこと、主イエスのお体に香料を塗って、整えようとした、という流れになるわけです。
ところが、ヨハネの福音書を見ると、アリマタヤ出身のヨセフが、恐らく、自分のために用意していた新しい墓を、主イエスにお献げしたというのは、他の福音書と共通しているのですけれど、ヨハネ福音書では、そこにもう一人、以前、夜の闇に紛れて、こっそり主イエスを訪ねて教えを請うたニコデモがいたと記しています。しかも、ニコデモは、没薬とアロエを混ぜた香料を百リトラばかり持ってきたというのです。換算すると33キロくらいになります。大変な量です。遺体のそばに置くのには十分すぎるほどの量だと思います。大体、重くて運ぶのも大変だったはずです。恐らくはこれも、すでに高齢であったニコデモが、自分の葬りのために、前もって用意していたと思われる香料を、主イエスにお献げしたと考えられます。そういう意味では、確かに時間は限られていたとしても、とても丁寧に、主イエスのお体を葬ったのです。だから、ヨハネ福音書では、安息日が明けるのを待って、数人の婦人たちが香料を携えて墓に行ったというふうにはなっていません。その必要はなかったからです。
安息日が明けた日、つまり、週の初めの日の出来事を、ヨハネは次のように描きます。20章1節、「週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た」。すでに、香料はたっぷり添えられていますから、改めて、持って行く必要はありませんでした。しかも、ヨハネによる福音書では、マグダラのマリアは、一人で墓に出かけたように描かれています。このあたりも、他の福音書とは、少し描き方が違うのです。ただし、朝早く、まだ暗いうちにでかけたというのは、共通しています。でも、主イエスのお体に香料を塗りに行くという目的はありません。マリアは何のために、お墓に行ったのでしょうか。ヨハネは何も記していません。しかし、恐らくは、何かをするために行ったというのではなくて、ただ主イエスの近くにいたかったということではないかと思います。
このマグダラのマリアと呼ばれる女性は、ヨハネの福音書では、主イエスの十字架の場面、19章において初めて登場しました。「イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた」(25節)と記されていました。4人の女性のうち3人までが同じ「マリア」という名前でした。この4人の女性たちと主イエスの愛しておられた弟子が、十字架の足下に立っていたのです。ヨハネの福音書では、「マグダラのマリア」とだけ記されていて、ガリラヤ湖の西岸マグダラ出身の女性であったということしか分かりません。ヨハネの教会においてはよく知られた存在で、改めて紹介する必要はなかったということかもしれません。マルコとルカの福音書では、「以前イエスに七つの悪霊を追い出していただいた女」というふうに記されています。七つの悪霊に取りつかれ、苦しめられ悩まされていたところを、主イエスによって解放していただいた、救っていただいたのです。それ以来、ガリラヤからずっと主イエスに付き従ってきたのだと思われます。主イエスに深く感謝し、また心から愛し慕っていたのでしょう。愛する主イエスの死を悲しみながら、墓へ行って一人涙を流して、在りし日の思い出に浸ろうとしたのかもしれません。
ところが、薄暗い中を歩いて墓に着くと、びっくりしました。墓の入口を塞いでいた石が取りのけてあったのです。入口から中を覗くと、主イエスのお体がありません。その二日前、ヨセフとニコデモが主イエスを葬るところをちゃんと見ていました。場所も確認しました。間違えてはいません。しかし、墓は空になっていたのです。墓が開かれて、空になっている。驚いたマリアは、すぐに走り出しました。シモン・ペトロと主イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って知らせました。「誰かが主を墓から取り去りました。どこに置いたのか、分かりません」(2節)。「分かりません」と訳された動詞は、複数形の主語をとる形になっています。新共同訳聖書では「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません」と訳されていました。実際には、マリアは一人ではなくて、一緒に行った仲間がいたのかもしれません。けれども、あたかもマリア一人であったような描き方をしているのは、11節以下、次週の礼拝で読む箇所で、マリアが大事な働きをするからです。マリアの存在に集中しようとしたのではないかと考えられます。
いずれにしても、墓が空であった。墓の中に、主イエスのお体がなくなっていた。それが、客観的な事実です。しかしながら、その事実をどのように解釈するかは、ひとによって違います。マリアは、墓が空であったという事実の原因・理由を考えました。そして、誰かが、主イエスのお体を墓の中から運び出して、どこかに置いた、と考えました。死んだ体が、勝手に自分で動くはずがありません。誰かが夜中にやって来て、イエスさまのお体をどこかへ移した。死体が消えてしまうはずはないので、その移された場所に、置かれたままであるはずです。でも、その場所が分からないと言って慌てたのです。マリアにとっては、墓が空であったということが、そのまま、主イエスの復活のしるしにはなりませんでした。主イエスが復活して、ご自分の足で、墓から出て行ったなどということは、とても考えられないこと、あり得ないことだと思われた。自分の常識的な判断の枠組みの外にあるのです。それよりは、誰かが盗み出したという方が納得できます。どこかに置かれている。置かれた場所にあるはず。ただその場所が分からないので慌てているのです。
マリアは、慌てたまま走り出して、弟子たちのところへ、特に、ユダが欠けた11人の弟子たちの中では代表格であったペトロのところに、そしてまた、主イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、自分が見たこと、そこから判断したことを伝えました。「誰かが主を墓から取り去りました。どこに置いたのか、分かりません」。もしかしたら、この二人なら事情を知っているかもしれない。いや、事情が分からなくても、どうしたらよいか、分かるかもしれない。そう思って知らせに行ったのです。
事情を聞いたペトロともう一人の弟子は、恐らく、それぞれ別の場所からそれぞれに飛び出したのでしょう。墓へ向かって走りました。そして、墓へ向かう道で一緒になったのだと思います。二人が墓へ向かって走ったのは、もちろん、マリアが訴えたことを自分たちの目で確かめたいと思ったからでしょう。びっくりして、そんなはずはないという思いも抱きながら、とにかく、じっとしていられなくなって、すぐに墓に向かって走り出したのです。ヨハネの福音書は、ここに面白いことを記しています。「二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子のほうが、ペトロより速く走って、先に墓に着いた」。先に話を聞いたのは、ペトロの方でした。ペトロの方が先に走り出したのでしょう。ところが、「もう一人の弟子」がその後を追いかけて、ペトロに追いつきました。しばらくは、一緒に走ったのかもしれません。でも「もう一人の弟子」の方が、足が速かったのです。恐らく、こちらの方が、年が若かったのでしょう。10代半ばくらいだと思われます。一方のペトロは30代くらいでしょうから、遅れをとりました。「もう一人の弟子」の方が先にお墓に着いたというのです。
ところが、この「もう一人の弟子」は、自分の方が先にお墓に着いたにもかかわらず、先に中に入ろうとしないで、ペトロが着くのを待ちました。ただ、身をかがめて墓の中をのぞくと、主イエスのお体を包んでいた亜麻布が置いてあるのが見えました。でも中には入らずに、ペトロが着くのを待ったのです。ようやく、遅れたペトロが到着すると、ペトロの方が先にお墓に中に入って、亜麻布が置いてあるのを見ました。さらに、主イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布とは離れた場所に、丸めてあったというのです。墓の入口で待っていた「もう一人の弟子」もペトロの後から中に入ってきて、確認しました。これは明らかに、年長者に対する礼儀をわきまえたということでしょう。また、弟子たちの中では代表格であったペトロに対する尊敬を表わしたということでもあると思います。
ところが、ここに、一つ注目すべき点があります。8節にこう記されているのです。「それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も中に入って来て、見て、信じた」。確かに、この「もう一人の弟子」は、年長者であるペトロに敬意を払っています。ペトロよりも早く走って墓に着いたのに、ペトロに先を譲りました。先に墓の中に入ったペトロは、中に残っていた亜麻布と頭の覆いを見ました。ただし、見ただけです。ところが、後から中に入った「もう一人の弟子」は、「見て、信じた」と言われるのです。なるほど、マリアが訴えたように、墓の中に主イエスのお体はありませんでした。墓は空になっていました。けれども、主イエスの体を包んでいた亜麻布が丁寧に解かれて、頭を包んでいた布が離れたところに丸めてあったということは、主のお体は誰かに盗み出されたのではないことを物語っています。もしも、遺体を盗み出すのであれば、亜麻布を解かずに、包んだままで運び出すはずです。頭の覆いもそのままであったはずです。墓の中の様子は、主イエスが、ご自分で頭を覆っていた布をはずして、体を包んでいた亜麻布を丁寧に解いて墓から出て行かれたことを指し示している。後から墓に入った「もう一人の弟子」は、それを見て、信じたのです。主イエスは、墓の中から解き放たれた。主イエスを捕らえてがんじがらめにしていた死の力が打ち破られた。墓が空であった事実の意味するところを「信じた」のです。
ここで「もう一人の弟子」と記されているのは、主イエスが愛しておられた弟子です。ヨハネによる福音書において、とても重要な位置づけを与えられている人です。そして、しばしば、ペトロよりも優位に立っているかのように描かれているのです。最後の晩餐のときに、主イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰かと問うた弟子です。主の十字架の足元に立って、主の母であるマリアを託された弟子です。そして、この後、21章まで読み進んでいくと、この福音書を書いた人のようにも見られます。伝統的には、弟子のヨハネであると考えられてきましたけれど、ヨハネから始まった教会の指導者であったと考えられます。この福音書が書かれた頃、すなわち、1世紀の終わり頃の状況を考え合わせると、ここに登場するペトロは、ペトロから始まったエルサレムのユダヤ人の教会を表わしており、もう一人の弟子は、異邦人の地に生まれた異邦人教会を表わしているというふうにも読まれてきました。
キリスト教会は、最初、エルサレムのユダヤ人教会から始まりました。やがて、福音は異邦人に伝えられ、どんどん広まって、有力な異邦人教会がいくつも生まれてきました。しかし、そういう中でも、ユダヤ人教会は、自分たちこそ本家であるとして、異邦人教会を軽く見ることが多かったようです。逆に異邦人教会は、伝統や律法にこだわる古い体質のユダヤ人教会を批判的に見る傾向がありました。そういう中で、ヨハネ福音書を記した人は、ぶつかり合って、批判し合うのではなくて、同じ方向に向かって一緒に走る仲間であることを大事にしようとしたのです。若くて走るのも速く力のあるもう一人の弟子が、先輩の弟子に対する尊敬を忘れなかったように、異邦人教会はユダヤ人教会への敬意を失ってはならない。また、ユダヤ人教会も、異邦人教会を侮ることなく、その霊的な力と広がりを認めるようにと説くのです。
それは、今日の教会の中でも当てはまることかもしれません。時として、昔から教会に連なって教会の伝統を重んじる人たちと、新しく教会に加わって来た人たちとの間に、対立が生じることもあるかもしれません。そういう時にも、信仰の先輩たちへの敬意を忘れないことが大事であると同時に、信仰に入ったばかりの若い信仰者を侮ることのないように、いやむしろ、主が言われたように、後の者が先になり、先の者が後になるということを、心しなければなりません。しかし、何よりも大事なことは、主イエスに向かって走る、主とお会いするために一緒に走るということです。早いか遅いかは問題ではありません。長いか短いかも問題ではありません。見るだけではなくて、見て、信じることが求められているのです。
しかしながら、「見て、信じる」ことが大事なのだとすると、その後に続く言葉に悩まされてしまうかもしれません。ヨハネの福音書は語ります。「イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである」。信じたのに、理解していなかった、というのは、どういうことでしょうか。確かに、「見て、信じた」とありましたけれども、それでは十分ではないということでしょうか。理解するというのは、「イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉」が分かるようになるということです。主イエスは、神さまの救いの御心とご計画によって、十字架におかかりになり、死者の中から復活されました。その神さまのご計画による救いを、二人はまだ理解していなかったのです。しかし、壮大な神さまの救いのご計画を理解しなければ、信じられないということではありません。信じることによって、理解するようになるのです。信じて、復活された主イエスと出会うことによって、主イエスの十字架と復活において成し遂げられた神の大いなる救いのご計画が分かるようになるのです。
もしも、すべてを理解してから信じようと思っていたら、いつまでもその時は来ないかもしれません。むしろ、信じることによって、聖書と神のご計画を理解するようになるのです。壮大な神の愛と救いが分かるようになるのです。分かったら信じられるということではありません。信じることによって分かるのが、信仰の世界なのです。人は心で信じて義とされ、口で告白して救われます。この救いの中に入れられることによって、神の物語が分かるようになり、その大いなる物語の中で、自分に与えられた使命を知るようになるのです。
ヨハネの福音書を読み続けてきて、受難節の中で、復活の記事を読むことになりました。先週の水曜日には、教会の仲間の葬儀を行いました。主イエスが死んで、墓に葬られ、墓の中から復活してくださったことによって、私たちにとっても、死が終着点ではなくて、死の先に、墓の先に、復活の光を望み見ることができるようになりました。受難節の中でも望みと喜びを先取りすることができるのです。 教会暦を厳密に守る教会では、受難節の間は「ハレルヤ」を歌わず、結婚式などのお祝いごとも慎むと聞いたことがあります。しかし、主は復活してくださいました。受難節にあっても、復活の主の現臨にあずかりながら、喜びと感謝をもって、共に「ハレルヤ」と歌いたいと思います。